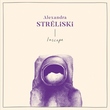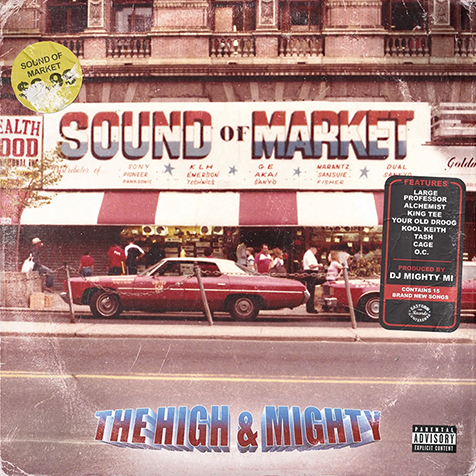カナダ出身のピアニスト/作曲家、アレクサンドラ・ストレリスキ。ポスト・クラシカル・シーンでは数少ない女性アーティストであり、映画「ダラス・バイヤーズクラブ」(2013年)の劇伴を手掛けたことでその名を広く知らしめた。そんな彼女が本人名義のオリジナル・アルバムとしては、約9年ぶりとなる2作目『Inscape』を完成。オーウェン・パレットらの諸作をリリースしてきたカナダの名門、シークレット・シティからのリリースとなる同作でも、素朴で手触り感を残した鍵盤のタッチと、流れるようにドラマチックなメロディーは健在だ。イノセンスと荘厳さが共存している鍵盤の調べは、聴き手にさまざまな感情を喚起してくれる。ストレリスキは『Inscape』にどんな風景を投影したのか。音楽ライターの原典子が考察した。 *Mikiki編集部
現代人が求める、ピアノの音だけに身をゆだねるひととき
ピアノほど振り幅の大きい楽器もそうないだろう。クラシック、ジャズ、ポップス……あらゆるジャンルにおいてピアノは多彩な音色を繰り出すが、近年はポスト・クラシカルのフィールドでも大きな役割を果たしている。なかでもピアノ一台でみずからの音楽世界を表現するコンポーザー/ピアニストのアルバムが海外を中心に好セールスを記録し、ストリーミングでも驚異的な再生回数を誇っていることは注目に値する現象だ。ヴォーカルもビートもない、静謐なピアノの音だけに身をゆだねるひとときは、情報過多な社会に生きる現代人にとっては瞑想(メディテーション)と言えるのかもしれない。
ユップ・ベヴィン、ジュリアン・マルシャル、リオピーなどソロ・ピアノ作品を発表しているアーティストは多くいるが、ピアニストとしての彼らの出自はさまざま。クラシックを学んだ人もいれば、独学で習得した人、ジャズ・バンドで弾いていた人もいる。本稿でご紹介するアレクサンドラ・ストレリスキはクラシックの専門教育を受けた人であるらしい。フレーズの歌わせ方や、映像で見る弾き姿がそのことを物語っている。
フランスのパリとカナダのモントリオール(仏語圏であるケベック州最大の都市)で育ったストレリスキは、2010年にファースト・アルバム『Pianoscope』を自主レーベルよりリリース。その後、同じモントリオール出身の映画監督、ジャン=マルク・ヴァレと出会い、映画「ダラス・バイヤーズクラブ」「雨の日は会えない、晴れた日は君を想う」(2015年)などの音楽制作を担当して世に知られることとなった。そしてカナダのレーベル、シークレット・シティと契約、この度リリースされたのがセカンド・アルバム『Inacape』である。

ALEXANDRA STRÉLISKI 『Inscape』 Secret City(2019)
人間の内面の旅を描くアルバム『Inscape』
〈Inscape〉という言葉は〈Interior〉 と〈Landscape〉を合わせた造語だという。自身の内側に広がる風景、といった意味だろうか。そのイメージはアルバム冒頭に収められた“Plus tôt”のミュージック・ビデオを観るとより鮮明になる。〈あなたは宇宙の一部ですか? それとも宇宙はあなたの一部ですか?〉という問いかけとともに、顕微鏡を覗き込む女性の映像が流れる。人体という宇宙で精子と卵子が出会い子どもが生まれ、地球上の動植物とともに自然の一部として成長していく。『Inscape』はその人間の内面の旅を描くアルバムであり、子ども時代が旅のはじまりというわけだ。くぐもったピアノの音色が、色褪せた8ミリフィルムの映像とともに遠き日の記憶を呼び覚ます。
アルバム全篇を通して印象的なのが、このピアノの音色と響きである。クラシックの世界では、大きなコンサートホールでいかに響かせるか、遠くまで音を飛ばすことができるかが重視されるが、ここに聴く響きはその真逆。素朴な温かみを持つ、柔かで丸みのある音色は、インティメイトな空間で、誰かのためにではなく自分のために弾くピアノにほかならない。
2曲目の“The Quiet Voice”では、少女が口ずさむ歌のように、付点のリズムでメロディーを奏でていく。ストレリスキは理論よりも直感に従って曲を書くタイプだと語っているが、この曲には心に浮かんだメロディーをそのまま指先で紡いでいるかのごとき純粋さがある。続く“Par la fenêtre de Théo”ではより躍動感が増し、生気を帯びた少女の足取りはスキップから小走りになる。