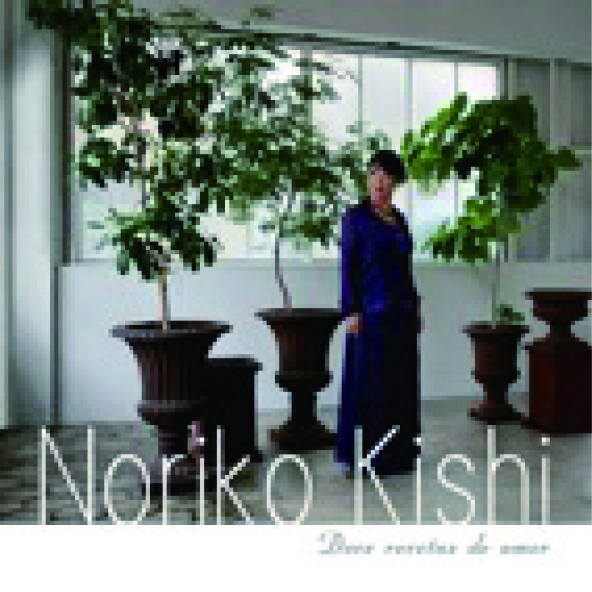年明け早々、寺井尚子のラテンジャズ・ライヴを観た。ゲスト、岸のりこ。バンドの主軸は、岸自身の最新セカンド『恋の12の料理法』を支えるつわものたち。強靭なラテン・グルーヴを、甘美な音色でスリリングに切り込む寺井。尖った硬質の歌声で、まったり円熟のレパートリーを紡ぐ岸……相性は抜群だった。
以前から共演機会をもつ両者には、奇しくも中西俊博との縁、ラテンという共通項がある。岸のサルサ・バンド初参加のきっかけが、当時オルケスタ246のメンバーだったバイオリニスト、中西よりのお誘い。彼女はサルサに没頭し、ラテン界の重鎮・見砂直照と知り合い可愛がられた。やがて本格的なキューバ修行へと旅立ち、1990~2000年にはキューバ、ベネズエラ、米国を拠点に、めざましい活躍を遂げることとなる。
「向こうで歌っていたのは、オリジナルのサルサとバイラブレ=踊るための音楽。今回のレパートリーのようなボレロやフィーリンの曲は、スタンダード過ぎてほとんど取り上げませんでした。帰国後、日本でのサルサの状況があまりよくないので、試行錯誤しながら……1年半、2年前くらいから、あびる竜太さん(ピアノ)と長年ご一緒している納見義徳さん(パーカッション)、最小限のメンバーでライヴを始めたんです」
粒選りの定番曲をとびきりジャジーに、洒脱な編曲でひとひねり。20年ぶりの濃密なセカンド作……だがその間、録音に対する欲求はなかったのか?
「歌手として自信が持てず、方向性でも迷っていた。納得できる自分の音楽づくりをしたかったから、まったく焦ってはいなかった。だから、今回の作品に出合って大正解……やっと自信作でございます、っていう感じ(笑)。ライヴではもっと膨らまして、アレンジもどんどん変えていく。まず楽曲の概念を壊して、それから組み立てて……すごく楽しいんですよね。それで、“私のラテン音楽”になればいいのかな」
「まさに『恋の12の料理法』で、一曲一曲その人によって味つけが違い、いろんな料理の仕方で変わる。幾通りもある……ただね、やっぱりラテン音楽と文化に対するリスペクトは、忘れちゃ、外しちゃいけないなと思う。私たちはそこで勉強させてもらって、生きてるわけですから。あと、歌手としての力。今、やっと自信が出てきた。自信がない時点では、リスペクトを欠くような気がしますから。決して順風満帆ではなく、荒波に飛びこんで行ったほうなので(笑)、人生の積み重ねを、作品の中のどこかに感じます。荒波を乗り越えて、今やっと空気を吸えるところにきたので、これからまた、さらに上がっていかなきゃいけない」
タフなベテラン歌手が、熱い闘志をめらめら燃やす。