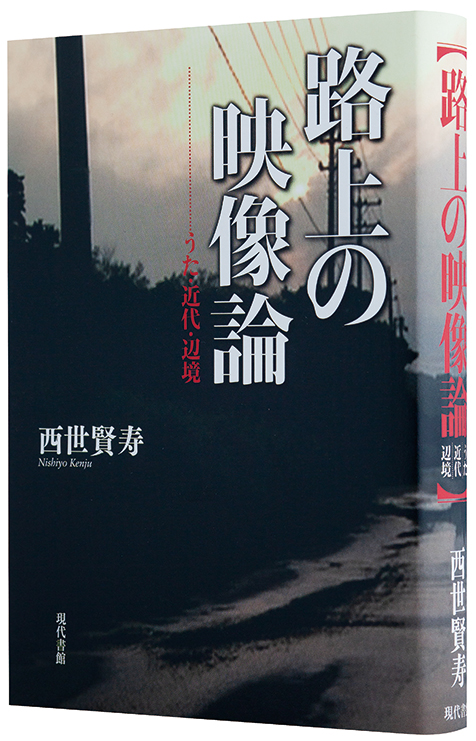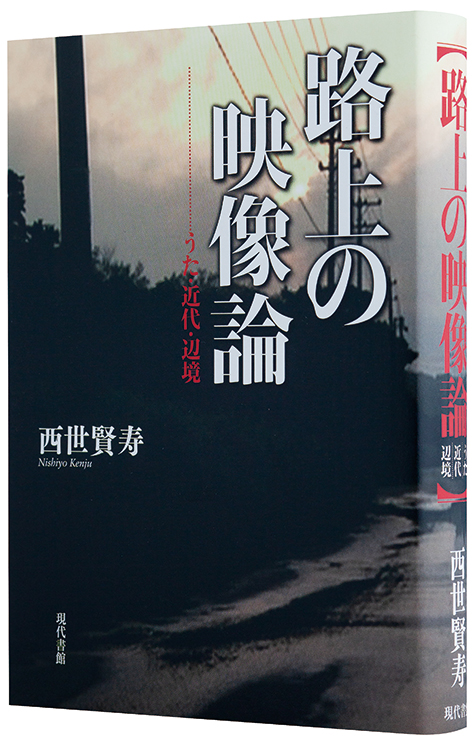人は誰しもその場その場という辺境に生きる
NHKでドキュメンタリーを制作してきた著者による初の著書。自らの映像作品を活字化した著作であるが、ずばりその内容は以下のようなものだ。著者はいう。「NHKを定年退職するまでの最後の10年間に、うたや語り物、伝承芸能の世界を入り口に、いくつかの長編ドキュメンタリーを制作してきた。中里介山の小説『大菩薩峠』の世界、福島原発事故、八重山/奄美の島唄、河内音頭、そして金時鐘と吉増剛造という戦後詩の二人の希有な詩人の旅──、何ら脈絡のないテーマだと思われるかもしれないが、それらこの本のなかで私が追い求めていったのは、とりもなおさずひとえに、辺境に生きた人々の漂う思い、言葉にならない言葉だった」(本書355~6頁)。
評者としては、まずあまりに魅力的かつある意味で「アブない」テーマ群にくらくらしてきてしまう。果たして「何ら脈絡がない」のか。私としてはまるごと一冊すべてに興味があり、また関わってきた「テーマ」でもあり、気がつくとこの本のなかでいくつかのものはNHKの映像版で見た記憶もある。テレビドキュメンタリーの書籍化というと、政治や歴史あるいは事件などの大きくハードなテーマのものをイメージしてしまう方も多いと思うが、こうしたまとめ方も非常に魅力的に思うのだ。一見 「脈絡がない」といえば、この本が迫っていくテーマ群と「テレビ」あるいは「テレビドキュメンタリー」もまた遠いもののように感じる人もいるかもしれない。事実、こうしたドキュメンタリーの秀作も少なくないのだ。
このところ、実は、私が今住んでいる広島のローカル局で「ヒロシマ」をテーマとしてテレビドキュメンタリーを評価していく作業にも関わっていることもあるのだが、誰でも見れるはずのテレビが実は見られていないことによる、損失の最大なものがドキュメンタリーだとも思う。本来、テレビはパブリックに開かれた最大のメディアであり、「人々」が他なる「人々」とつながる場所でもある。そうしてみると、本書は実は最も本源的な意味でテレビ的な作品でもあるといえるのだ。
「辺境に生きた」とはいうが、それはそれぞれの人々が、自らを中心にした場合の謂いにすぎないと考えれば、誰しもそれぞれの場所で生きている。自ら以外はみな辺境にいるが、自らもまた他者から見れば辺境にいるのだ。本書に登場する人々は、だから誰ひとりとして「私たち」ではない人もまたいないのだ。あまりに個人的に羨望の念をも持ってしまうような絢爛な内容の本書を読みつつ、そんなことも考えてしまった。関連する音源13トラック収録のCD付きも嬉しすぎる。未体験の方は、奄美の里国隆あたりにはぜひ震撼していただきたい。