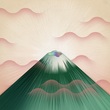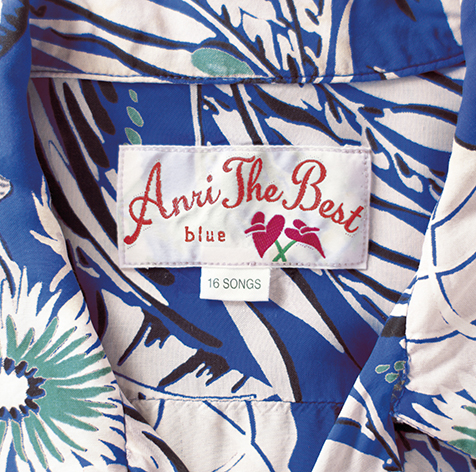グローバル社会の問題を想像力とユーモアで変える歌
折衷的なサウンドを拡大させつつもビタースウィートなフィーリングでまとめた5作目『Rings Around The World』(2001年)はSFAのキャリア最高傑作と名高い作品で、タイトルの〈世界中に繋がる電話〉が象徴するのはグローバリズムだ。
弾けるように明るいアルバム・タイトル・トラックには世界が繋がっていることの興奮が描かれているけれども、アルバムを通して見つめられるのは、グローバル社会がもたらした搾取構造、環境汚染、不平等、人権侵害などシリアスなものだ。この時期、テーマ的にもっともSFAとシンクロしたのは、『OK Computer』(97年)~『Kid A』(2000年)/『Amnesiac』(2001年)期のレディオヘッドだと言えるだろう。
そしてまた、リースは収録曲の“Presidential Suite”でビル・クリントンとボリス・エリツィン両元大統領をモチーフに政治家の退廃を描いているように、権力への怒りも隠さなかった。フォーキーな“No Sympathy”では富を搾取する権力者たちに向けて、あくまで穏やかに〈きみは死ぬべきだよ〉と歌うのである。
けれどもSFA(グリフ・リース)には、レディオヘッド(トム・ヨーク)にはないチャーミングで温かいユーモアがある。“Receptacle For The Respectable”にポール・マッカートニーがニンジンとセロリを齧る音で参加しているというのも最高だけど(ビーチ・ボーイズの“Vegetables”にポールが野菜を齧る音が入っているという逸話からの引用)、何よりもスウィートなメロディーと優しい言葉で思いやりを表すのが彼らである。
先述した“No Sympathy”の次に収録された“Juxtapozed With U”はソウルを思わせる煌びやかなアレンジとメロディーが美しいバンドきっての名曲で、そこでリースは少しおどけるように、〈堪えなくてはいけないね、嫌いな奴らのことも〉と歌っている。それは超富裕層への憎しみにも耐えねばならない人びとの気持ちに寄り添うものだそうだが、同時に自分には、立場や考えの異なる他者とそれでも共存していくことを模索する歌のようにも聞こえる。
簡単に世界が終わるわけではないと諦観混じりに告げる“It’s Not The End Of The World?”ではまた、こんなにも優しいメッセージが届けられる――〈この世の憎しみをすべて/物真似鳥に変えてしまって/遠くの空に放してしまおう〉。この世界に横たわる不平等や搾取を正面から見つめた上で、それをどうにか想像力とユーモアとともに変えていくことを歌にこめてきたのがSFAであり、グリフ・リースだった。
コンセプチュアルなグリフ・リースのソロ活動
バンドと並行しながらリースはソロとしての活動を『Yr Atal Genhedlaeth』(2005年)以降始めるが、ここでとりわけ注目したいのは、LAのビート・メイカーのブーム・ビップと結成したキッチュなエレクトロ・ポップ・ユニット、ネオン・ネオンの存在である。
ファースト・アルバム『Stainless Style』(2008年)では映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」に登場するタイムマシンのモデルとなった〈デロリアン〉を開発したジョン・デロリアンの人生を、セカンド・アルバム『Praxis Makes Perfect』(2013年)では大戦後のイタリアでソビエトの社会主義古典を蒐集し出版した共産党員ジャンジャコモ・フェルトネッリの人生をアルバムごとにテーマにしている。前者はアメリカにおける過剰な商業主義を、後者は大戦後の冷戦構造の緊張を、それぞれ数奇な人生を送った人間の視点から浮かび上がらせる。アイデアとしては突飛だが非常に知的な風刺ポップで、いま聴いてもリースのユーモアの冴え渡りぶりに驚かされる。
SFAのバンドとしての活動は2010年代以降落ち着いてしまうが、リースは代わりにソロ・アルバムをコンスタントにリリースしていく。ソロではよりコンセプチュアルなテーマを押し出しており、たとえば4作目『American Interior』(2013年)では18世紀のウェールズ出身の冒険家であるジョン・エヴァンスがモチーフとなっている。エヴァンスはアメリカ中西部にウェールズ語を話す部族が存在するという伝説を確かめるためにアメリカに渡った人物で、彼の足跡を通してリースもまたアメリカを探究する。アメリカン・フォークロアをリース流のサイケ・ポップとして調理した本作で、そして、リースは結果的にアメリカが侵略によってできた国だという事実に向き合うこととなる。リースの遠い祖先に当たるエヴァンスもまた、侵略に加担した人物であったことにも。それは、植民地主義が行った搾取によってわたしたちの現在の豊かな生活があるという事実を思い知ることであり、その負の遺産を見つめることでもある。そうしたダークな部分も隠さずに、しかしファンタジックな冒険譚として現代に向けて語り直したアルバムなのだ。
一方、キャリアでもっともエレガントなオーケストラル・ポップ・アルバムとなった『Babelsberg』(2018年)は、サウンドの穏やかなフィーリングとは裏腹にブレグジットやトランプ現象以降に漂う現代の社会不安をモチーフにした作品だ。とりわけ印象的なのはソーシャル・メディア上での孤独の描写で、とろけるようにドリーミーな“Selfies In The Sunset”には〈夕焼けのなかの自撮り/バックには燃えるような赤/死の谷では誰もが平等〉という世界の終末を連想させる言葉がある。リースはいまの世界を、ディストピアとしてここで描いている。アルバム中もっともキャッチーな“Negative Vibes”で〈きみと僕はネガティヴな空気をすべて克服しないといけないね〉と繰り返しているのも、ポジティヴであることを押しつけてくる社会のムードを皮肉っているように見える。ただそれでも、リースが歌うと本当に前向きな気持ちになってくるから不思議だ。そこにはごまかしの優しさではなく、すべての聴き手に対する慈愛のフィーリングがあるから。