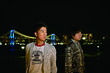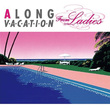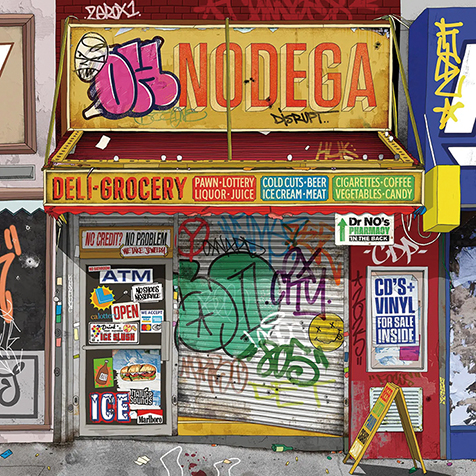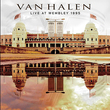みずからの歌に課した高いハードル、良質なポップスを求めてやまないリスナーの期待値――すべてを超えて稀代のシンガーはまた金字塔を作り出した! ニュー・アルバム『Horizon』に広がる美しい地平とは?
どんな曲でも自分流に引き込む
「今回は80sサウンドでいこうじゃないかと。もう10何年も〈温故知新〉を自身のスタイルとして音楽をやってきましたが、そのあたりをしっかり掘り尽くせていないという感覚があったというか、〈まだまだ絞り出せるエッセンスがあるんじゃないか〉と思い、初めて組む若手たちも交えて80s風味のシティ・サウンドを追求しようと思ったわけです」と語るジャンク フジヤマ。83年生まれの彼が最初に80年代っぽさを意識したのはいつのことだったのか?
「中高生ぐらいの頃だから90年代後半ですかね。まず聴いていたのは日本の音楽です。最初はサウンドの云々かんぬんなんてわからないですよ。〈スネアにリヴァーブがやたらとかかっているな〉とか、〈プレイヤーの手数がやたら多いな〉とか、そういうことを理解できはじめたのは大学に入ってバンドをやりはじめた頃。僕はだいたい歌に重きを置いて聴くタイプなんですが、特徴的なヴォーカルをしっかり聴かせながら、なおかつサウンドもしっかり構築された音楽を探してみたところ、さほど多くはないんだなってことに気付かされまして。特に男性シンガーではあまり見つけられなかった。そんななかで僕の耳を捉えたのは、井上陽水さん、山下達郎さん、安全地帯さんあたり。イントロからブラスがバリバリ入っているような、とにかくキラキラしたサウンド感に当時はおお~って感銘を受けました。なかでも歌謡曲の色濃い陽水さんのサウンドに惹かれたというか、素直に心地良さを感じたんです」。
そんな個人的な記憶や感情を呼び起こしながらレコーディングに臨んだというところもあるかもしれないなと、歌とサウンドの有機的な結び付きぶりがとにかく絶品な新作を前にしてそう思う。昨年のカヴァー・アルバム『憧憬都市 City Pop Covers』からあっという間に届いた感のあるジャンク フジヤマのオリジナル・フル・アルバム『Horizon』。“夏のマーメイド”“Tokyo highway disco drive”、そして名曲“あの空の向こうがわへ”の作者であるベーシスト・坂本竜太が提供した“Wonder History”など先行で配信されたシングルを受け取りながら、どうやらピーカンでゴキゲンなグルーヴィー・チューンが並ぶ痛快作になりそうだ、と予感したものだが、その読みは半分アタリで半分ハズレだったという気がしている。というのも、後味がいつになくまろやかな作品に仕上がっていて、ところどころで陽だまり感のようなものが顔を出す作りになっていたからだ。どこか初期作に漂っていたシンガー・ソングライター色を彷彿とさせる部分もあるし……などとこっちの印象をつらつら述べているとニヤリと笑いながら彼が言う。
「でも〈クレジットを見なければ、いったい誰が書いた曲かわからない〉っていうのはこれまでと変わらない。歌い手としての当たり前の個性を発揮して、全部こちら側に引っ張り込んでしまおうというね。どんなメロディーも〈こっちがいいよな〉っていうふうに譜割りなどの細かい部分を調整しながら自分なりの節回しを駆使して料理していく。もちろん同時に全体的なバランスも考えながら。まぁ、毎度やっていることですね」。
本作のクレジットには新たな顔ぶれも目立つ。“花柄の街”を提供した三味線のお師匠さんという顔も持つCHiLi GiRLこと川嶋志乃舞。彼女の既成の型に囚われないユニークな曲構成には何かと刺激を受けたとジャンク フジヤマは語る。そしてエンディングを飾る“大切なもの”を作曲した滝沢ジョーも今回が初顔合わせ。〈カーティス・メイフィールドな感じと現代的な夕暮れの雰囲気がマッチングした曲を〉とオファーをかけたそうだが、彩りも美しいゴスペル風なコーラスが映える佳曲に仕上がっている。これらのミディアム系の充実ぶりが本作のカラーを特徴づけているのは間違いないが、いろんな面々が運び込んできた多様な要素を持ち前のバランス感覚を働かせつつ独自の色合いを放つポップ・サウンドに仕立て上げてみせる彼の手管はやはりさすが。そんな本作のもっとも誇らしいポイントはどこか?と尋ねてみた。
「オープニング曲の“Horizon”のラストで、〈スパーン!〉ってファルセットをぶつけているんですけど、手前味噌ながら、〈こんなのができる人はそうそういないだろうな〉と思う(笑)。高いキーが歌えるとかそういう類いの話じゃなくってね。でも録り終えたあとで、〈俺、これライヴでやれんのかな?〉と頭を悩ませることになって(笑)。シンガーとして〈ここはいちばん美味しいとこだから外せない〉とこだわってみたものの、演奏のタイミングとちょっとでもズレたらこの歌は表現できないかもな……って。僕としては常に、アルバム以上のものをライヴで観せるべきだと思っているんで、作品を超えていくために、さてどうしようか?って悩みが尽きない」。