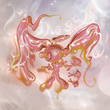リリースから早1ヶ月。2018年を代表する名盤として、中村佳穂『AINOU』の注目度は高まる一方だ。かくいう自分も何十回と聴いているが、ここまでリピートしたくなる作品と出会ったのはいつぶりだろうか。リリックの意味、歌のしなやかさ、サウンドと歌詞のシンクロ、独創的なビートとリズム解釈、演奏のニュアンスやテクスチャーの妙など、全12曲のなかに無数のサプライズが隠されており、聴くたびにハッとさせられてしまう。
そんな『AINOU』は、不思議なバランスに支えられた作品でもある。フューチャー・ソウルやトラップなど現行のトレンドとも接近しつつ、民謡や歌謡曲のようなノスタルジーも内包しているし、トラックは徹底的に作り込まれているのに、滲み出る情感はとことん人間臭い。エレクトロニックなのに血が通った、独特のサウンドはどのように生まれたのか? その謎を解き明かすべく、アルバム制作に携わった中村佳穂BANDのメンバーを取材した。
『AINOU』のキーマンとなったのは荒木正比呂。エレクトロニカの要素を持つ名古屋のバンド、レミ街の鍵盤奏者で、広告系の楽曲提供でも知られる職人気質のプロデューサーだ。深谷雄一は荒木のバンド活動に参加してきたドラマーで、シンガー/ビートメイカーのMASAHIRO KITAGAWAも荒木の旧友である。さらに、Mikikiではお馴染みのギタリスト、西田修大(吉田ヨウヘイgroup)がここにも参加。この4人に『AINOU』の制作秘話と、プロダクションへの飽くなき執念を語ってもらった。
★中村佳穂『AINOU』特集記事一覧
Pt.1「私は私、あなたはあなた、だからこそ出会える」中村佳穂――音楽を愛し、音楽に愛されし才媛の生きる道
Pt.2 中村佳穂『AINOU』はなぜ2018年を代表する名盤なのか? 柳樂光隆、佐藤文香、松永良平がクロス・レヴュー
それぞれの中村佳穂との出会い
――みなさんと中村さんが知り合ったのはいつ頃でしたか?
荒木正比呂(レミ街)「僕と深谷くんは2014年頃ですね。レミ街のリリース・イヴェントを名古屋ですることになっていたのに、最後の一組がどうしても決まらなくて。僕は新婚旅行に行くことになってたから、メンバーに見つけるよう頼んでおいたんです。それなのに、(九州の)五島列島をグルッとしたあと、長崎のホテルに戻って確認したら全然探してなかったんですよ」
深谷雄一(レミ街)「イヴェントまで残り2週間くらいでしたよね」
荒木「だから仕方なく、夜中にネットで検索してたらFacebookで女の子が演奏している動画が流れてきて。それが佳穂ちゃんだった。20秒足らずの動画なんだけど、見た瞬間に〈この子だー!〉と思って。その映像が、その日に名古屋のライヴハウスで録られたものだとわかるやいなや〈打ち上げはあそこの中華料理屋だろうから、誰か寄れる人いない?〉って、メンバーに連絡したんです」
深谷「それで僕が中華料理屋に向かうと、荒木さんの予想通り打ち上げをしていたんです。〈あのー……〉と話しかけたら佳穂ちゃんがいて。周りの共演者がレミ街を知っていて、薦めてくれたのもあって〈じゃあ出ます〉とその場でOKがもらえました」
――中村さんは以前、〈レミ街を知れたのは、サノヒトミちゃんのお陰です〉とツイートしていました。
レミ街を知れたのは、サノヒトミちゃんのお陰です。彼女の「好き」という気持ちの純粋さが私は大好きです。
— 中村佳穂 (@KIKI_526) 2015年5月5日
荒木「viridianというバンドにいたサノさんが共演者で、彼女がその動画をアップしていたんです。そこでもしニアミスしていたら、そのまま出会わなかったかもしれない」
――そう聞くと運命的な感じがしますね。中村さんとイヴェントで共演したときの印象は?
荒木「佳穂ちゃんはソロの弾き語りだったのに、バンド・サウンドより明らかに強いんですよ。〈この人のあとにライヴするの嫌だなー〉って思いました(笑)。あと、彼女はその日、“今夜はブギー・バック”を歌っていたんだけど、そのカヴァーを聴きながら、この人はいまやっている音楽とちょっと違うこともできそうだなと、なんとなく考えていましたね」
――そこから一緒にやるようになったのは、どういう経緯があったのでしょう?
荒木「tigerMos(荒木とイケダユウスケによるユニット)のアルバムを佳穂ちゃんに送ったら、彼女からメールが送られてきて。〈日本中を回りながら一緒に演奏できそうな人を集めているんですけど、名古屋で今度ライヴをやるので参加しませんか?〉と誘ってくれたんです。それで、僕と深谷くんが彼女のバンドに加わって、名古屋でライヴしたらメチャクチャ盛り上がったんですよ。出番が4バンド中3バンド目だったのにアンコールが起こったり、泣き出すお客さんもいたりして。あれは本当にヤバかった」
深谷「それが2015年の11月29日、いい肉の日で(笑)」
西田修大(吉田ヨウヘイgroup)「僕もそのころに佳穂ちゃんと知り合ったんです。YYGが3作目(2015年作『paradise lost, it begins』)のツアーをするときに、関西のイヴェンターさんが〈中村佳穂がすごいからツーマンをやったらいいんじゃないか〉と提案してくれたんです※。佳穂ちゃんはRyoTracksくんとのデュオ編成だったんですけど、歌の力もそうだし瞬発力のある音楽で、しなやかで早くてダイナミクスが半端なかった。あのときは正直、負けたと思いましたね」
※2015年12月5日、大阪・梅田Noon+Cafe
――これまた衝撃的な出会いだったと。
西田「で、ライヴを通じて仲良くなったんですよ。アンコールでも一緒にセッションしたりして。その1ヶ月後、東京で佳穂ちゃんがライヴをするときに、〈よかったらデュオをしませんか?〉と連絡をもらって。ただ俺の記憶では、あのときの自分は大していい働きをしてなかった……(苦笑)」
荒木「その時、佳穂ちゃんに〈西田くんとはどうだった?〉と聞いたら〈もう2、3回一緒にやったら良くなると思う〉と言ってたけどね」
西田「俺も同じように話して〈次こそ〉と思っていたんですけど、ふたたび共演するようになるのはだいぶ後の話で」
――KITAGAWAさんは?
MASAHIRO KITAGAWA「もともと、荒木さんとは10年以上前からの付き合いで。住まいも名古屋なので、最初の話にあったイヴェントにも遊びに行ってました。〈あのピアノの上手い子、誰?〉と驚いていたら、荒木さんに〈まだ21歳だよ〉って言われて。だから知り合ったのは早かったんですけど、僕が何をやっている人なのか、佳穂ちゃんはわりと最近までよく知らなかったと思う(笑)」
――実際、KITAGAWAさんのキャリアは謎が多いですよね。2002年にソロ活動をスタートして、トラックメイクの大会でも活躍されているそうですけど。
KITAGAWA「僕はシンガー兼ビートメイカーで、レコーディング・エンジニアもやっていたんですけど、曲を作り出すとのめり込むのがシンドくて。30代半ばまで自分の作品を発表してこなかったんですよ。そこを荒木さんが励ましてくれて、重い腰を上げて作るようになったら、結果がついてきて楽しくなって。今年の頭から自分のアルバムを制作していたんです。そんななか、荒木さんに(『AINOU』の)制作を手伝ってほしいと頼まれて」
荒木「彼は名古屋に80坪くらいあるスタジオを所有していて、機材もマニアックなのが揃っているんですよ」
KITAGAWA「そこで今年5月くらいにプリプロの録音を手伝いながら、荒木さんに言われて“get back”のトラックを作ったら、佳穂ちゃんも気に入ってくれて。そのあとライヴにも参加するようになりました。だから、一緒にやるようになったのは本当に最近ですね」
天才だけど、根性がある。中村佳穂は孫悟空みたいな音楽家
――4人から見て中村さんってどんな人ですか? ライヴのMCからは、感性豊かで朗らかなイメージも受けますけど。
深谷「普段からあんな感じですよ、いつも歌ってるし」
荒木「そうそう。寝る前とかもずーっと歌ってる」
深谷「この間も、泊まったホテルのロビーに電子ピアノがあったから、それをいきなり弾きだして。通りがかった外国人の宿泊客が拍手する、みたいな」
KITAGAWA「そういうの多いですよね。朝、早起きして一人で外に出かけて。そこでピアノを弾いてたら、おにぎりもらったとか(笑)」
荒木「ただ、天才みたいによく言われるけど、すごく根性がある人だと思います」
KITAGAWA「本当にそう、孫悟空みたい。今回のアルバムにしても、弾きながら歌うのが難しい曲ばっかりなんですよ。佳穂ちゃんも〈こんなのできないー〉って言ってるのに、次に会ったらできるようになっていて。どこでどんな練習をしたのか知らないけど、たぶん僕らの見えないところでやってるんじゃないかな」

――あと、天才肌の人は自分の〈型〉が出来上がってるケースが多い印象ですが、中村さんはそういう感じでもない気がして。
荒木「そうですね、そのなかに閉じこもらないところがある。好きな音楽と自分の音楽を分けないというか、自分が好きな音楽にストレートに向かっていくところがありますね」
――そのスタンスによって、『AINOU』も生み出せたわけですね。中村さんとレミ街では音楽性もだいぶ異なると思うんですが、どうやってお互いをシンクロさせていったのでしょう?
荒木「自分たちのそれまでの経歴は考えなかったですね。さっきも話したように、彼女のソロ・ライヴはすごかっただけに、そこに僕と深谷くんが入ったときに、ソロより弱まっている感じがしたんですよ。彼女の鍵盤はとんでもないけれど、僕はそんなに弾けないし。何をしたらいいんだろうってかなり悩みました。それで、まずは自分が活きる曲を持ち込んでみたんです。一個ずつそうやってデモを作っていって、トライ&エラーしてみて。真っさらの状態から考えていった感じですね」
――本当に地道なところから制作がスタートしたんですね。最初はなかなか形にならないまま、録っては解散を繰り返していたと中村さんも話していました。
荒木「まず何を作るべきか、どういうやり方がいいのか最初に探し出そうと。合宿をやる、朝昼を共にする、長い時間を一緒に過ごす。外を走ったり、コーヒーを買いに行ったり、呑みに行ったり。何を言ったら喜ぶのか、ストレスを感じるのか。ロジカルより前の地点から始めたんです」
――合宿をやろうと最初に言いだしたのは?
荒木「僕か佳穂ちゃんだったと思います。作曲って朝がいちばん捗るし、アルバムを一枚作るのってものすごくエネルギーを使うから、頭の効率を少しでもよくしたかったんですよ」

――合宿はいろんなところで行われたみたいですね。
荒木「最初は東京ですね。2016年の1月で、その頃に住んでいた田園調布の地下スタジオでずっと録って。1日5、6パターンくらいmp3ファイルを作って、それを4日間繰り返しました。そのあとは(愛知県)半田市にある大きいスタジオを借りたり、僕がいま住んでる三重県でやったり。佳穂ちゃんのおばあちゃんが神戸にマンションを持ってるので、そこを借りたりもしました」
――西田くんは合宿に行ってみてどうでした?
西田「僕が行くようになった頃には、合宿の雰囲気というか流れもできていたので、それを体験しているだけで超楽しかったです。みんなで同じ時間を過ごして、同じ景色を見たりするじゃないですか。そういうのがアルバムの音にも関係あるんだろうなって。それに、合宿に一回行くとメチャクチャ健康になるんですよ(笑)」
――ご飯もみんなで作るんですか?
西田「つくしを摘んで、天ぷらにしたりとか。ご飯を作るときもフォーメーションが鮮やかでしたね。俺が材料を切ってる間に、雄一さんがそれを炒めていくみたいな」
深谷「皿を配って、お箸を用意してとかね(笑)」
西田「演奏が上手くいってるようなグルーヴ感があるんですよ。そういうときに、いいバンドだなーって思いました(笑)」

――中村さんは今回のアルバムについて、フィジカルに頼りすぎず、サウンドメイクにこだわった作品にしたかったと話していました。
荒木「そこがいちばん重要だったと思いますね」
KITAGAWA「自分がビートメイクとエンジニアの両方をやっていて思うのは、ビートのうえにヴォーカルを普通に乗せても格好良くならないんですよ。日本語は響きが暗いし、リズムも作りづらいから、馴染ませるのが難しい。そこは僕が本格的に関わるようになる前から、荒木さんから相談されていて。〈英語にしたら早いんだけど〉とも言われたけど、佳穂ちゃんは日本語の力がすごいじゃないですか。あれがまた新しいんだけど、馴染ませるのに時間がかかるというか。バランスを取るための引き算が大変だったんじゃないかな」
荒木「みんなの間にモワッとした感覚だけがあって、その見えないグリッドの真ん中に少しずつ近づけていったのが今回のアルバムなんですよ。だから、佳穂ちゃんも変わらなきゃいけなかったんですよね。彼女の歌をそのまま活かして、ファンデーションするだけでは絶対作れないと思ったから」
KITAGAWA「佳穂ちゃんもずっと違和感があるって言ってましたよね、歌っていて気持ちよくないって。でも出来上がっていくにつれて、そのほうが説得力があるものになっていった」
荒木「彼女は一度出来上がった歌や歌詞を変えるのをすごく嫌がるんですよ。だから、美味しいご飯を食べてるときとかに、修正点を繰り返し伝えるようにして。でも、変えた先が正解とも限らないし、努力や我慢をしたのにいい結果にならなかったときもあったから、そういう意味でも根性があると思います。答えがまったくない作業だったから、ずっと苦しかったですね」
――それだけ産みの苦しみがあったのに、出来上がったアルバムそのものは驚くほどスムーズに聴こえるんですよね。
荒木「本当にそう(笑)。その裏には大量の没テイクがあるんですよ」