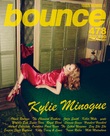ダニエル・ロパティンの音楽を聴いていると、そんなことを思う。とりとめのない記憶。思い出が生み出す思い出。来歴を失った、異質なものたちが織り成す空間。
*
引用の織物という言葉がある。その言葉の定義はもう忘れてしまったものの、その言葉が喚起するイメージは私の創作と強く結びついている。だから、私にとって自画像とは、世界の像にほかならない。
私は私の文章を、私によって書いているのではない。私によって書かれる言葉の全ては引用であって、引用の中には出典不明なものも多く含まれる。世界は書かれたものとして既にあり、私は既に書かれた世界に囲まれている。私はそれを読み、読んだ言葉を書き写しているだけだ。私にとっての創作とはつまるところ、既にある世界を異なる順序で読み替えて、それを日本語に移し替えることにほかならない。
私が生まれて初めて書いた物語は、どこにでもある大学ノートに、無数の中古の本の断片を、ただ書きつけただけのものだった。それは中学生の頃だったと思う。その頃の私は毎日家の近くのブックオフに通い、100円コーナーの棚に敷き詰められた本を片っ端からカートにつっこみ、親にねだって買ってもらっていた。私はそれらの本たち、表紙が黄ばみ、手垢にまみれてボロボロになったそれらの本たちを手に取り、気に入った文章を片っ端から書き写していった。
書き写すのが面倒なときはページを破り、そのままノートに貼り付けた。ノートに何枚もの本のページを貼り付けていくと、ノートは当初の何倍にも膨れ上がった。そうしたノートが何冊も積み重なった。ノートが無くなると、ノートの上からまた書き始め、書き始めた上から破ったページをまた貼り付け、その上からまた書き始めた。物語を書き終える頃には、盗んだ文章の元の持ち主が誰かなんて、もうわからなくなっていた。
*
そんなことが本当にあったかどうかは定かではない。今思い出されるものは今思い出されているものでしかなく、それ以上でもそれ以下でもない。全ての記憶は、事故のような偶然の中で作られ、そして思い出されるつど、ふたたび事故のような偶然を引き連れてくる。
*
ダニエル・ロパティンは2007年、セルフケアのために表現活動を開始した。当時の彼は、一日のうちの大半の時間を、やりがいのない、単純で反復的な作業に費やしていた。彼はネットワークから遮断されたコンピュータの前で、永遠のようにも思える長い時間を、ただ硬い椅子の上に座り、上司からの指示を待ち、ときどき表計算ソフトに数字を打ち込むことで過ごした。家に帰り、彼は自分自身を確認する作業として、ポップソングのメロディーをただ単に引き伸ばしたり逆再生したりしただけの断片を作り、ときどきそれをネットの片隅にアップロードするようになった。
私はその頃の彼のことは知らないが、知っていないとも断言できない。むしろ私は、現在のダニエル・ロパティンが作る音を介することで、今は存在しないその頃のダニエル・ロパティンと、あたかも友人のように出会い直し続けることができる。そんな実感を持っている。
*
私はこの原稿を2020年の10月17日に書いている。カットソーの上にカーディガンを羽織り、キーボードに向かって文章を打ち込んでいる。気温は12度で、先日までの暑さが嘘のようだった。今は朝の10時。外では雨が降っていた。私はクローゼットの中から厚手のコートを取り出して、シャツの上からそのまま羽織った。コートのポケットから、プラスチックがぶつかるような音が鳴った。
確認すると、中にはカセットプレイヤーが入っていて、開くと見たことのないカセットテープが入っていた。たぶん、一度か二度だけ聴いて、それがどんな音楽だったのかも、そもそもそんなカセットを買ったことすらも、忘れてしまっていたのだろう。
私はヘッドフォンを耳にかけて、それから再生ボタンを押した。
カセットテープからはどこかのラジオ放送の録音が流れ始めた。懐かしいような音楽が流れていた。なんの曲かはわからなかった。私はそれを、どこかで聴いたことがあるような気もしたし、そうではないような気もした。私はその音楽を聴きながら歩き始めた。家からの長い道のり。それは、家までの長い道のりでもある。私は音楽を聴き、私は小説を読み、私は忘れ、私は思い出し、そして私はまた忘れ、忘れてゆくものたちの中で、私は文章を書いている。
雨の中に音が溶けて、滲んで、それから街の中へと消えていった。そうして私もまた、街の中へと入り込んでいった。