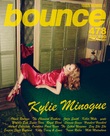ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー(以下、OPN)が約2年ぶりとなる新作『Magic Oneohtrix Point Never』をリリースした。

ONEOHTRIX POINT NEVER 『Magic Oneohtrix Point Never』 Warp/BEAT(2020)
今回Mikikiでは、本作を起点にしてOPNの3つの顔――普遍性をもった〈ポップ・アーティスト〉としての顔、〈ミレニアル世代のカルト・アイコン〉としての顔、聴き手を刺激し新たな物語を誘発する〈記憶の作家〉としての顔――にフォーカスし紐解いていくことにした。
まず、本作から聴きとれるOPNのポップな本性に迫るのは、過去にMikikiでアルカについての記事も執筆している音楽ライターの井草七海。続いて、OPNが本作制作に至るまでにカルト・アイコン化していった歩みを振り返るのは、7月に「ニューエイジ・ミュージック・ディスクガイド」を刊行した音楽ライターの門脇綱生。そして最後、本作にインスパイアされた聴き手として新たな物語を綴るのは、「構造素子」「すべて名もなき未来」などの著書で知られるSF作家の樋口恭介。
それぞれの視点から綴られる、読み応えたっぷりのテキストたちを存分に堪能してほしい。 *Mikiki編集部
【目次】
1. 井草七海が読み解く、OPNの限りなくポップな本性
2. 門脇綱生が遡る、ミレニアル世代のカルト・アイコン=OPNの歩み
3. 樋口恭介が本作を題材に綴る、新たな物語=記憶「Long Road Home」
井草七海が読み解く、OPNの限りなくポップな本性
黙々と何かに没頭する時、何を聴くでもなく、ただラジオをつける。チューニングを合わせると、ノイズ混じりに耳に入ってくる音楽、そしてそこにクロスオーバーし溶け込んでいる、人の声。それらのことをよく知りもしなくても、ラジオが作る音の空間は妙に心地よい。いや、チューニングを合わせるようなアナログなラジオなんて、最近はなかなかお目にかからないかもしれないが。
ダニエル・ロパティンによるソロ・プロジェクトである、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー。この奇妙で長いアーティスト・ネームが、ボストンのラジオ局である〈Magic 106.7〉の聞き間違えに由来するということを、不勉強ながら、筆者は今回初めて知った。彼にとって原点とも呼べるそのラジオ局の名前をもじった彼の新作『Magic Oneohtrix Point Never』は、ある意味では彼の集大成かもしれないが、根本の部分では、おそらくそうではない。これは、彼自身が〈自分はいったいどんな音楽を作りたいのか〉という初期衝動を改めてとらえ直した作品であるように、筆者には感じられる。
〈架空のラジオ〉をコンセプトとした今作は、所々にラジオのジングルのようなトラックを挟みながら展開されていく。作品を構成する楽曲は、彼の作品群の中でもこれまでになくポップだ。そのポップさの一翼を担うのが、ウィークエンド、アルカ、元チェアリフトのキャロライン・ポラチェックら、ゲスト・ヴォーカルの存在である。だが、それだけ豪華なヴォーカリストたちの声にさえも、エフェクトがたっぷりとかけられており、彼の紡ぐトラックの起伏の波に紛れこまされている。彼ら生身の人間の声と、電子音との区別は限りなく曖昧だ。
中でも特に耳をひくのが7曲目“The Whether Channnel”から8曲目“No Nightmares”への流れ。タイトルの通り、深夜に流れ出す、機械的な天気予報番組のバックでかかっているような、人間味がないのになぜか心に染み入るヒーリング・ミュージック風のサウンドに耳を傾けていると、突然ノンビートのトラックへと切り替わる。そして激しいエレドラムが高らかに鳴り始めるとともにウィークエンドのヴォーカルが混線、そのまま彼の歌が司る“No Nightmares”へとなだれ込むのだ。
“No Nightmares”では、本名のエイベル・テスファイとして今作の共同プロデューサーに名を連ねる、ウィークエンドという強力なポップ・アイコンの加工された機械的な歌が、OPNの紡ぐ、80年代のニューエイジのようでありながらチェンバー・ポップのようでもあり、けれどもそのどちらでもないようなトラックに溶け合うことで、なぜかほんのりと幸福感の漂う奇妙な感覚を聴き手に味わわせる。
“No Nightmares”は本来はウィークエンドのために作られたものをもとに、ウィークエンド自身が「よりOPNらしく」と指示しできあがったそうだが、そのエピソードに登場する〈OPNらしさ〉こそ、まさしくここで見てきたような、音と声の混線にあるように思う。
OPNが注目を浴びるようになったきっかけである4枚目のアルバム『Returnal』(2010年)や5枚目の『Replica』(2011年)でも、身元もわからない名も無き人の声を、トラックのパーツとしてささやかに忍び込ませていたわけではあるが、その後作品のリリースを重ねるにつれ、〈声〉の使用の比重は増すばかりであった。
ただ、近作である『Garden Of Delete』(2015年)、『Age Of』(2018年)において、より明確なリリックと歌唱が作品に盛り込まれるようになっていったとて、やはりそれらはノイズまみれ。パソコンの起動音やエラー音、家電の駆動するような音、子どもの頃に遊びつくしたゲームのBGM……等々、この消費社会を漂う、日常のどこかで聴いたことがある機械の音に似たサウンドと並列に扱われているのである。
若い頃には、ラジオをエアチェックしながら気に入った部分だけを録音しミックステープを作っていたという彼の耳には、ノイズにまみれてしまえば機械の音も人の声も等価に聴こえてしまうのかもしれないし、だからこそ、この原点回帰的なアルバムにおいて、ラジオを装った構成を取ったというのは、大いに納得できる話だ。
彼がそんな原点を見つめるきっかけとなったのは、やはりこのコロナ禍によるところが大きいようだ。人との接触が失われ、家に引きこもった結果か、今作後半の楽曲は、彼の諸作の中でもとりわけ内省的だ。
異様にベタでセンチメンタルなAOR~ソフト・ロック的な14曲目“Lost But Never Alone”やら、鳥の声や笛の音、チェロのような弦楽器の音などで構成された抽象的な16曲目“Wave Idea”など、エモーショナルながらも、流れで聴いていくとどこか掴み所がなくコロコロと曲調が変わっていく。そして、物憂げで美しいメロディーと歌を聴かせる17曲目“Nothing’s Special”に身を委ねると、気づけば〈放送終了〉を知らせる合図のようなサウンドとともに、フッと終わってしまうのだ。
こうして聴いていくと、今作はまるで、このコロナ禍において移ろう彼の心そのものの写し鏡のようだとも言えるだろう。それは、彼自身、〈癒し〉だとか〈頭が良くなる〉だとか、何か特定の有用性があるとされる音楽を度々否定していることからもわかるように、彼を語る上で引き合いに度々出されるニューエイジやヒーリング・ミュージックとはまるで異なるものだ。今作を聴き、彼の心の動きに触れたなら、私たちの中には何か得も言われぬ感情が沸き起こる。そしてまた、いつも全く同じような感情が機械的に起こるというものでもない。少なくとも筆者は、自分の状態に応じて、聴くたびに、少しずつ違った気持ちにさせられた。
そう、だからこそ、OPNは限りなく〈ポップ〉である、と言えるだろう。歌があるから、メロディーがあるから、という形式の話ではない。それを聴いた誰かのその時々の精神状態、そこから発生する解釈を、懐深く受け止める。OPNは「音楽が彫刻や文学のようなものになっていったとしても、音楽は誰にでも楽しめるものとして存在することができる」というブライアン・イーノの考え方に影響を受けているようだが、まさにその普遍性こそが、今作に宿っている〈ポップさ〉の源泉なのだと思わされる。
コロナ禍の自主隔離期間のOPNは、他者とのコネクションのツールとして、やはりラジオを聴いていたらしい。すなわち、今作制作時の彼にとっては、ラジオは社会へ通ずる窓であったのだ。今作は、言ってみれば、そこから聴こえてくる、機械の音も、人の声も、全部ひっくるめた、〈声〉を使った、ポップ・ミュージック作である。OPN=ダニエル・ロパティン自身のパーソナルな感情を、時代の声とクロスさせながら紡ぎ出す、という意味においては、とても奇妙な形をした、現代のある種のフォークロアでさえあるのかもしれない……というのは、ちょっと言い過ぎかもしれないが。
少なくとも今作は、ポップであるがゆえに、その受け取り方は、これまで以上に聴き手である我々に委ねられている。この普遍性こそ、一見奇天烈なクリエイターであるOPNが、その音楽制作へ向かう動機として、初めから抱えていた原点なのだということを、今作に発見したのであった。