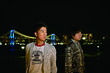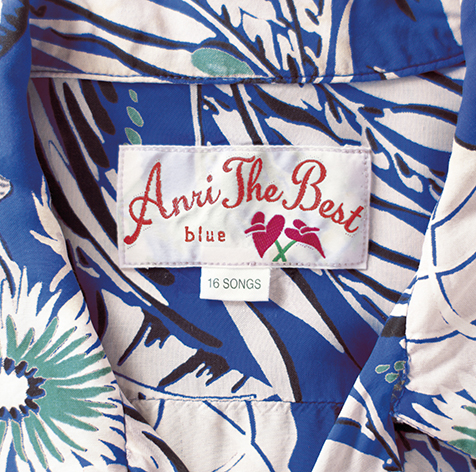自分の曲だけどそうじゃないような、大きな存在の“TOMORROW”
――聞くところによると、ライブ当日にラジオを付けたら、“TOMORROW”(95年)が流れてきて驚いた、というような出来事があったそうですが。
「そうなんですよ! 会場へと向かう車で聴いていたラジオ番組で〈ドライアイ〉についてのトークをしていたんですね。私もドライアイの持ち主なんで、へ~、ふむふむ、ってめっちゃ真剣に聞き入っていたんですよ。そしたら〈では涙ということで、岡本真夜さんの曲を〉と“TOMORROW”がかかって。こんなことあるの!?と思い、嬉しくなっちゃいました」
――まさかドライアイの話題から自分の曲へつながっていくとは、予想だにしませんよね。
「(笑)。で、そのラジオ局のお偉いさんが、ライブを観に来てくれたんですよ。なかなかない偶然ですよねぇ」
――思えば“TOMORROW”って、今回のコロナ禍や東日本大震災といった有事の際に人々を励ます役割を担ってきました。国民的応援歌となったこの曲を岡本さんはどう捉えていらっしゃるのか。
「“TOMORROW”はあまりに大きな存在になっていて、自分の手から離れてしまっている感覚があるんです。だからず~っと不思議な感じなまま捉えているというか、歌っている私も自分の曲なんだけどそうじゃないような気がして」
――その感覚は時を経るごとに大きくなっていたりします?
「いえ、もうデビュー当初からそうでした(笑)。デビューしたての頃、私はメディアに顔出ししないという形をとっていて、ま、実はそれが約束だったんですね。で、ドラマの主題歌だった“TOMORROW”がテレビから流れてくるのを聴いたり、街中で有線放送から流れてくるのを耳にしたりしながら、私の曲なんだって実感がいまいち持てないままでいたんです。
そのうちいろんな場所であの曲が歌われるようになり、知らない間にあまりに大きな存在になってしまっていて……。東日本大震災のときもいっぱいリクエストをいただいたりするんですけど、正直言ってどうにも不思議な感じが拭えなかった」
――すると岡本さんとしては“TOMORROW”を多くの人に伝えるメッセンジャーの心境だったりする?
「そうですね」
私は感覚でしか生きていけない、と言い聞かせながら
――そうかぁ。今回のライブで歌われた曲を聴いていていちばん強く感じたのは、岡本さんの音楽に備わっている日常感覚というか、誰彼関係なくごく自然に聴き手の生活に溶け込んでしまえる独特な佇まいがあるなってこと。そうやって多くの人たちの日常に寄り添ってきたんだろうなと、観客の反応を眺めながら考えていたんです。もちろん、さまざまな非常時に駆り出される“TOMORROW”も含めて。
「そう言っていただけると嬉しいです。私、歌詞を書くのがあまり得意じゃないんですけど、でもいつも心がけているのは、日記の1ページのような気持ちで書くことなんです。だから日常感覚はすごく大事なものですね」
――ひょっとしたらその感覚のベースには、岡本さんが抱いている、ポップソングとはそうあるべき、といった美意識が流れているかな?なんて思ったりしたんですけど。
「そこまでは考えていないかも(笑)。曲を作るときは自然に浮かんでくるものをただ形にしているだけで、音楽としてどこまで意識的に作っているのかと言われると心許ないところもあって。私、音楽用語とかホント知らなくて、ミュージシャンたちが自然発生的にセッションしているのを見ていて、いつも羨ましくてしょうがない(笑)。とにかくただひたすら自分のなかに浮かぶものを音にしていくことだけを続けてきたんですよ。私は感覚でしか生きていけないんだ、と言い聞かせながら」
――でもけっしてブレることなくその方法論を徹底してきたからこそ、岡本真夜的世界が育まれる結果につながったわけですから。今回のライブで僕がもっともグッと来たのはピアノの弾き語りの“ALONE”(96年)。心の震えも聴こえてくるようなステキな演奏でした。
「緊張しましたけどね。お客さんを前にしてライブするのがひさびさだったし、カメラもいっぱいあったから。弾き語りも好きなんですが、なにせ緊張しいなので。実をいうと、演奏中に本当に震えている箇所もあるんですけど、指がアップになっていなくてよかったなって(笑)」
――人前で歌を披露するはもともと好きなほうですか?
「好きですね。何がいいって、自分の歌への反応が生で味わえること。お客さんの表情や拍手や歓声に触れると、あぁ音楽を作ってきてよかったな、って素直に思える。ライブはそういう大事な場所ですね」