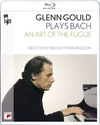生誕90年・没後40年
人はなぜグールドに魅せられるのか?
今年、生誕90周年および没後40年を迎えるグレン・グールド。クラシック音楽はまったく好みじゃないけど、このピアニストの演奏だけは聴き続けているという人は多い。そして、その音楽や存在について人々が語り、論じたくなってしまう演奏家は、そうそうみつからない。
では、人はなぜグールドに魅せられるのか。彼について語りたくなるのか。
それは、グールドのアンチ・ロマンな演奏スタイルがあまりにも新鮮だったから、というだけに留まらないように思われる。そして、時代の象徴となるべきポップなセンスがあったのは事実にしても、やはりそれだけではないような気もする。
もっと複雑な、20世紀の芸術家ならではのアンビバレンスなものを抱えた存在だったからではないか。
1932年カナダのトロントに生まれたグールド。彼の名声が一気に高まったのは、1956年に米コロムビアからリリースされたバッハの『ゴルトベルク変奏曲』のレコードだった。
若手ピアニストが『ゴルトベルク変奏曲』でメジャー・デビューというのは当時保守的だった北米では考えられぬことだった。この時代のピアニストに求められたのは、いかにロマンティックに歌い、そして煌びやかに超絶技巧を駆使するか。つまり、ショパン、シューマン、ベートーヴェンあたりを華麗に弾いてくれるほうが、レコード会社としてはありがたかったのだ。
そのあまりにも鮮烈なバッハは、レコードの歴史に残る演奏となった。これまで誰も聴いたことのないモーレツなスピード感。エッジの効いたフレーズがひたすら疾走していく。
そして、なんといっても声部の一つひとつが声高に主張し、躍動しまくる、百花繚乱のポリフォニックな音楽。主旋律と伴奏のようにヒエラルキーが整ったホモフォニーに慣れ親しんでいた耳には、お祭り騒ぎのようにも響いたろう。
そもそも『ゴルトベルク変奏曲』はチェンバロのために書かれた曲。ピアノで弾けば、どうしても表現が重くなる。響きも混濁しがちだ。
グールドは、音を繋げるためのレガートを効かせず、一音一音をソソリ立たせるスタッカートで弾き続ける。打楽器的な側面をもつピアノで、滑らかに旋律を奏でるのは演奏家の腕前の見せ所(とくに、ロマン派音楽では)。そんなものは必要ないといわんばかり、どこか挑発的な奏法に聴こえたに違いない。
今では、このような奏法は、バッハやスカルラッティをピアノで弾くときのスタンダードとなった。そして、これまで退屈な音楽と思われていた(ことが不思議なくらいだが)『ゴルトベルク変奏曲』は、ピアニストにとって重要なレパートリーにもなった。
そのグールドの弾くバッハの響きには、クラヴィコードを思わせるものがあった。彼はオリジナル楽器を弾くことはほとんどなかったが、その音楽観は、のちに音楽界を席巻する古楽復興にも少なからず影響を与えたはずだ。
グールドの新しさは、それだけではなかった。
演奏家にとって不可欠だったコンサートをやめ、メディアを通して演奏することを宣言したのだ。演奏会につきまとうバカバカしい儀式性。客席から浴びかけられる見世物小屋的な視線。ライヴという一回性への信仰。グールドはこれらを嫌った。ひたすら逃げ出したかった。
1964年以降、彼はスタジオに籠もり、そこから音楽を提供し続けた。レコードやラジオ、そしてテレビといったメディアを通して。何度もやり直しができるレコーディングは、度が過ぎた完璧主義者だった彼には都合が良かったのだ。
彼のレパートリー中心となったのはバッハ。そのほかに、シェーンベルクやヒンデミットなどの20世紀の音楽。ベートーヴェンやハイドン、リヒャルト・シュトラウスやシベリウスのピアノ曲も好んで弾いた。
どちらかといえば、カッチリとした様式があって、ドライな質感が求められる作品が多い。あからさまに情緒的なロマンティシズムを香り立たせる音楽は遠ざけられた。
だが、面白いことに、彼の弾くシェーンベルクは、ほかの誰の演奏よりも情感豊かに聴こえる。無調の作品はもちろんのこと、無機質の極みである十二音技法で書かれた曲であっても、その乾いた平原をさも嬉しそうに歩き回るグールドの姿が見えそうな音楽なのだ。バッハのときと同様、声部の一つひとつに生命力を感じ、その響きは、どこか艶めかしささえ宿しつつ。
ブラームスの後期作品集もかなり独得だ。まず、後期ロマン派的な湿っぽさをいったんパワフル除湿して、シェーンベルクを思わせる乾いた質感に変えてしまう。そうすると、今まで隠れていた音楽の組み立てが、まるで古典派作品のように浮かび上がる。そして明確になったそれぞれの声部をグールドはいつものように情感豊かに動かす。
ドライなのにエモーショナル。これこそがグールドの音楽なのではないか。いや、ドライだからこそのエモーショナルさか。彼にとっては、ロマンティシズムは自らの内側から沸き立たせるものであり、それは決して楽譜には記せないものだったのかもしれない。
ルネサンスから現代まで。グールドのレパートリーは広かった。しかし、そのなかには、ピアニストとって欠かせない作曲家とされるショパンやシューマン、リストといった名前はない。こうしたロマン派の大本命を彼はほとんど弾くことはなかった。嫌いとさえ明言していた。そこには、他人(作曲家)が道筋を作った、手垢のついたロマンティシズムを辿るのは真っ平御免といった意志も感じられる。
しかし、このような彼が好きではなかった作品に耳を傾けると、グールドという人がさらに身近に迫ってくる。
たとえば、〈モーツァルトは長生きしすぎた〉と毒舌を浴びせたにもかかわらず、この作曲家のソナタをしっかり全曲録音していたりする。
これがじつに面白い。旋律を奏でる右手と、伴奏部分の左手はまるで主導権を争うかのように拮抗、バッハのような立体的な音楽へと変貌させてしまっている。
ショパンのソナタ第3番の演奏もあった。バッハを敬愛していたショパンだが、その作品からバッハの臭いだけをかぎ分け、それを純粋培養したような音楽になっている。
呆れるほどに徹底している。すべての道はバッハに繋がっているべきだ(多少道が悪かったらなんとか通れるようにはするけど、まったく繋がらないような曲は最初から弾きません)というわけか。
そんなグールドが生前にリリースした最後のレコードもバッハだった。しかもデビューと同じ『ゴルトベルク変奏曲』。アリアで始まってアリアで終わるこの曲、まさにこのピアニストのレコーディング歴にそのまま重なってしまう。
若き日の演奏に比べると、別人と思われるほどにテンポは遅い。その遅さゆえ、各声部が自由に跳ね回り、歌い、踊る様子が手に取るようにわかる。その空間がぐっと広がった感じだ。それは、まるで何人かのグールドが集まり、一緒にアンサンブルをしているかのようにも聴こえる。やっていることは、ほとんどオーケストラ音楽である。
この頃は、指揮者としても活動し始めていた。新しいグールドが誕生しつつあった。50歳という若さで世を去ってしまったのはそんなときだった。
グレン・グールド (Glenn Gould)
1932年、トロント生まれ。14歳でピアノ部門の修了認定(アソシエイト)を最優等で取得し、ピアニストとして国内デビュー。1955年、米国デビュー公演の直後に米CBS(現ソニー・クラシカル)と専属録音契約を結ぶ。20代は世界各地に演奏旅行に赴き、カラヤン、バーンスタイン、セル、クリップスなど錚々たる指揮者たちとも共演して名声を築く。1964年4月のリサイタルを最後に演奏会活動を引退、以後は録音と放送番組の仕事と執筆に専念。1982年10月4日、脳卒中のため急逝。前年に再録音した『ゴールドベルク変奏曲』が遺作となった。
寄稿者プロフィール
鈴木淳史(すずき・あつふみ)
1970年、山形県寒河江市生まれ。たぶん音楽よりも音を聴いているほうが好きなのだけど、それだけだと単に怠け者だと思われてしまうので、音楽に関する批評やエッセイを書いている。著書に「クラシック悪魔の辞典」「背徳のクラシック・ガイド」「愛と幻想のクラシック」「占いの力」(以上、洋泉社)「チラシで楽しむクラシック」(双葉社)「クラシック異端審問」(アルファベータ)「クラシックは斜めに聴け!』(青弓社)ほか。共著に「村上春樹の100曲」(立東舎)などがある。
RELEASE INFORMATION
生誕90周年・没後40年 特別企画
GLENN GOULD 90/40
2022年9月~2023年2月
これまで未発売だった約10時間にわたる全セッション・テイクが初めて公にされる!
グレン・グールドの秘蔵音源3タイトルが正規音源からBlu-spec CD2化!
『秘蔵音源シリーズ』(3タイトル)
グレン・グールドのアルバムを、米コロンビアのオリジナルLPの発売順でBlu-spec CD2化するシリーズ
『グレン・グールドの芸術』(60タイトル)
9/21・10/26・11/23・12/21・1/25・2/22発売 各月10タイトル
世界初LP化を含む4種・6ヴァージョンのゴールドベルク変奏曲をアナログ化
『ゴールドベルク変奏曲アナログ・コレクション』(6タイトル)
1979年から1981年にかけて、グールドが精力を傾注した『バッハ・シリーズ(グレン・グールド・プレイズ・バッハ)』三部作の映像がついにまとめて初BD化
※分売あり
GLENN GOULD 90/40特集ページはこちら!