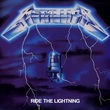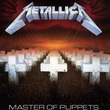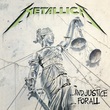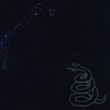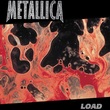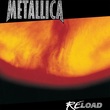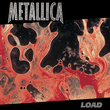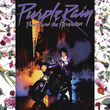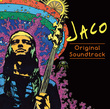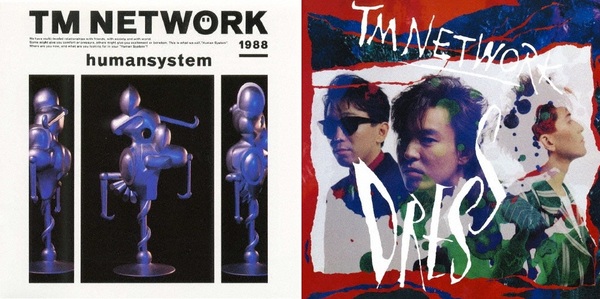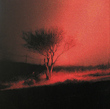『Master Of Puppets』(86年)
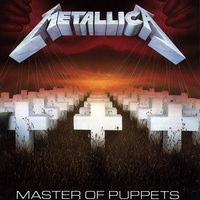
その昔、タワーレコード新宿店のマノウォーのコメントカードに〈天上天下唯我独尊 神はマノウォーの上にメタルを造らず〉という名キャッチがあった。この『Master Of Puppets』もまさに、〈天上天下唯我独尊 神は『Master Of Puppets』の上にメタルを造らず〉といえる歴史的大名盤だ。
メタル好きのバンドマンならば一度はコピーにチャレンジしたことがある曲が多く収録されているはず。Rolling Stoneによる〈歴代最高のメタルアルバム100選〉で第2位に選出されていることからもスラッシュメタルだけではなく、全てのメタルカテゴリーの中で渾然と輝く傑作だ。
”Battery”や“Master Of Puppets”、“Disposable Heroes”、“Damage, Inc.”における曲の速さ、複雑なリフに転調、曲のスピードにのったギターソロは、〈スラッシュメタルの1つの到達点〉と言っても過言ではない。また“Welcome Home (Sanitarium)”でのスローなスタートからギターソロに向けて速くなっていく展開など曲構成のバリエーションも豊富。メンバー4人での様々な試行錯誤を経て制作された本作は全8曲を通して聴いても非常に高い完成度を誇っている。失礼な言い方をすれば〈アルバムとしての完成度が高すぎること〉が逆に唯一のマイナス点と言えるほど隙のないアルバムだ。
メタリカ自身の他作品や他アーティストの作品と比べられない唯一無二の大傑作メタルアルバムと言える。 *Mikiki編集部
『...And Justice For All』(88年)
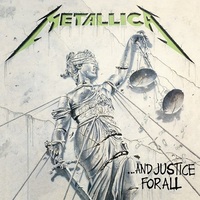
「タモリ倶楽部」の空耳アワーでタモリに〈メタリカ〉というバンド名を覚えさせた大名作〈バケツリレー 水よこせ〉でおなじみの”Blackened”が収録されたアルバムだ(他にもメタリカは空耳アワーで『Metallica』収録曲“Through The Never”の〈寿司・鶏・風呂・寝ろ〉など多くの名作を残している)。
ツアー中のバス事故でベースのクリフ・バートンが逝去し、新たにジェイソン・ニューステッドの加入初となる本作。しかし、加入直後より他メンバーから除け者にされてしまっていたことが後々明るみになるが、クリフの死によってメンバー間で連帯ができていなかった当時のバンドの状況が如実に表れたアルバムだ。
サウンドプロダクションにおいて、ベース音が小さく、非常に悪いバランスとなってしまっている点やクリフの死と向き合いながら制作されているため、前作『Master Of Puppets』での練りに練られた展開には及ばないが、ジェイムズ・ヘットフィールド、ラーズ・ウルリッヒのリフや作曲センスはより複雑にヘヴィに進化、成長や進歩を感じ取れるフレーズも多く、アルバムとしての評価は賛否両論となっている。また、小説「ジョニーは戦場へ行った」からインスパイアされた”One”では初のミュージックビデオを制作とこれまでのメタリカにない新しい試みも行われ、バンドとして新たな道を進みだしたアルバムでもある。 *Mikiki編集部
『Metallica』(91年)
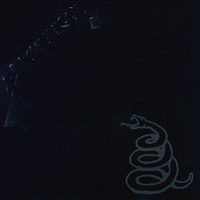
ニルヴァーナ『Nevermind』、ガンズ・アンド・ローゼズ『Use Your Illusion』と並び、時代の転換点である91年を代表する一枚。自身のバンド名を冠した通称〈ブラック・アルバム〉と呼ばれるこの作品は、彼らのキャリアにおける重要作であるだけでなく、後のロックシーンにも絶大な影響を与えた歴史的名盤だ。
鈍器を振り下ろすかのような強力なリズムが身体を震わせる“Enter Sandman”、うねるようなギターリフの“Sad Bad True”、重厚なバラード“The Unforgiven”……スピード命だった初期のスラッシュメタルスタイルから重さとグルーヴに比重を置いたサウンドへとシフトし、その後のメタリカサウンドの基本軸ともいえるヘヴィネスを本作で確立した。
ジェイムズ・ヘットフィールドの表現力を増したボーカルによってキャッチーさを増したこともあり、従来のメタルファンのみならず多くの人々を飲み込んだこのアルバムは、全世界でトータル1,500万枚以上を売り上げるモンスターアルバムとなった。そして本作の大ヒットにより、後のメタル/ヘヴィロックシーンは大きく変わっていくこととなる。このアルバムが無かったら、コーンをはじめとしたラウドロックの隆盛や、ニッケルバックらモダンロック勢の台頭は無かったと言っても過言ではないだろう。 *粟野