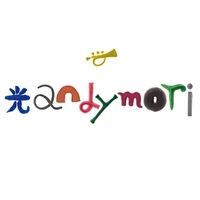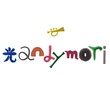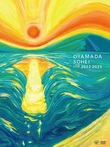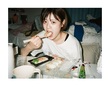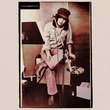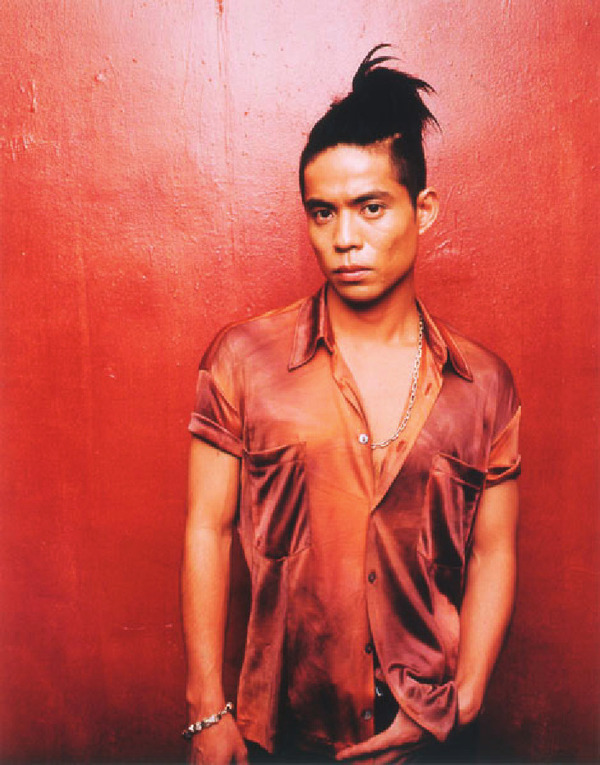〈死〉を意識しながら〈生〉をいかに輝かせるか
andymoriの代表作といえば、“すごい速さ”以外にも“everything is my guitar”や“ベンガルトラとウィスキー”のようなアッパーでエネルギッシュな曲を多く収録した『andymori』も捨て難いのだが、バンドの知名度を大きく引き上げたのはやはり2010年発表の『ファンファーレと熱狂』であり、名曲“1984”だろう。小山田の生まれた年をタイトルに冠し、勇壮なトランペットともに〈ファンファーレと熱狂 赤い太陽 5時のサイレン 6時の一番星〉と歌われるこの曲は、生命が内包する膨大なエネルギーの可能性を祝福するという、andymoriの表現の根幹が明確に表れた一曲だ。バンドの規模感が急激に広がったタイミングだったこともあって、全体的には混沌とした雰囲気も感じられるが(同年11月には後藤が脱退)、それもまたこのアルバムの魅力であり、“CITY LIGHTS”、“16”、“グロリアス軽トラ”など名曲多数の傑作だ。
その後ドラマーとして岡山健二が加入したことにより、それまで個性のぶつかり合いだった彼らが一枚岩のバンドになったことは大きな変化であり、アレンジもメッセージもよりストレートに、明確なものになっていき、それは2011年の東日本大震災を経てリリースされた『革命』(2011年)や『光』(2012年)といったアルバムのタイトルにもよく表れていたと言える。
ラテン語で〈死を記憶せよ〉という意味を持つ〈メメント・モリ〉をバンド名に含み、“The End Of The World”をSEとし、“すごい速さ”で〈きっと世界の終わりもこんな風に 味気ない感じなんだろうな〉と歌う彼らの楽曲には常に〈死〉に対する眼差しがあり、だからこそ虚無に絡め取られることなく、いかにして〈生〉を輝かせるかを希求している。コロナ禍を経てのandymoriのリバイバルというのは、彼らの表現と時代の空気がマッチした側面も少なからずあるだろう。
ラストアルバムとなった『宇宙の果てはこの目の前に』(2013年)の収録曲の中で、唯一解散を決めた後に書かれた楽曲である“夢見るバンドワゴン”は〈僕らはまだまだブルースを歌いながら〉という歌い出しで始まり、〈いつも憧れを胸に抱いて〉で締め括られる。andymoriは最後までどこまでもandymoriだった。
あいみょん、カネコアヤノら後進への多大な影響
andymoriが下の世代に与えた影響はとても大きいが、個人的に特に大きいと思うのはあいみょんとカネコアヤノという時代を代表する2人のシンガーソングライターへの影響だ。2人はともにバンド編成のライブと弾き語りのライブを交互に行っていて、そのスタイルはバンド解散後の小山田と同じ。その上で、まずあいみょんは“夢追いベンガル”で“ベンガルトラとウィスキー”を明確にオマージュ。“ベンガルトラとウィスキー”は吉田拓郎の“ペニーレーンでバーボン”が着想の元になっていて、小山田とあいみょんの共通のルーツである日本のフォークが浮かび上がる。
カネコアヤノは人脈的にもより小山田に近い場所にいて、それぞれGateballersの濱野夏耶と活動をともにしていた時期があるし、やはりフォークやカントリーに対する愛情があり、ときにサイケデリックなアレンジを施す楽曲のスタイルも似ている。完全に勝手なイメージではあるのだが、ブライト・アイズことコナー・オバーストとフィービー・ブリジャーズとの関係を、小山田とカネコに重ねている自分がいたりする。
他にもandymoriの影響を感じさせる若手の名前を挙げようとすればキリがなくて、PEOPLE 1の“高円寺にて”を聴いても、Teleの“comedy”を聴いてもandymoriが思い浮かぶが(Teleはもともと3ピースのバンドだった)、ここではomeme tentenをピックアップしたい。昨年に発表された“2020”は彼女たちなりの“1984”のようにも聴こえるのだが、面白いのはこのバンドが今年mini muffからデビューをしていること。mini muffは現在も所属しているCzecho No Republicに加え、過去には踊ってばかりの国やThe Mirrazといったandymoriと同時代のバンドたちをリリースしていたレーベルであり、彼女たちの登場はどこか時代が一周したような雰囲気を感じさせ、andymoriのリバイバルともシンクロしているように感じられた。