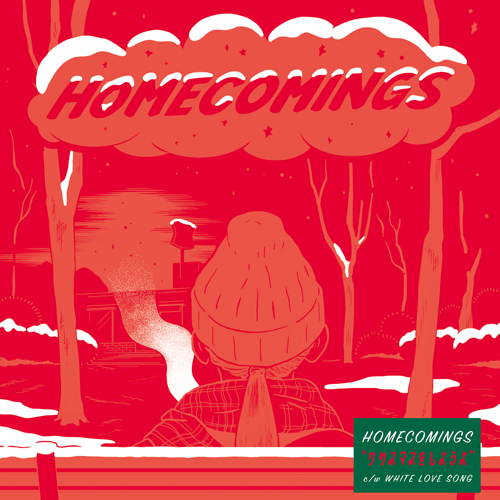2015年にMikikiに掲載されたレヴュー記事のなかで、予想外(失礼!)の高いアクセス数を獲得したのが石指拓朗のファースト・アルバム『緑町』。知る人ぞ知るシンガー・ソングライターながら圧倒的な関心が注がれ、邦楽の2015年の年間レヴュー・アクセス・ランキングでは赤西仁と松田聖子に挟まれる形で7位をマークするとは、ある意味〈事件〉だった。
そんななか、Enjoy Music Club(以下EMC)の初作『FOREVER』の詳細が発表されると、石指の同作への参加が判明。ポップでキャッチーなラップ・グループと滋味深いフォーク・シンガーとが一見結びつかず、ますます興味をそそられた。〈石指拓朗とEMCの関係とは?〉――その答えに迫るべく、Mikikiでは石指拓朗とEMCの対談を企画。MC CLUB(以下C)のみ都合がつかずに惜しくも不参加となったが、石指とEMCのMC ENJOY(以下E)、MC MUSIC(以下M)にあまり語られたことのない各々の音楽経歴からロマンティック(?)な両者の出会い、共通点も多い作り手としての哲学までを、相思相愛ムードたっぷりに語ってもらった。
EMC全員が石指拓朗の音楽を大好きになったんです
石指拓朗「EくんとCくんが小学校の同級生なんだっけ?」
MC ENJOY「そうですね。俺とCが幼馴染みで、CとMは学生のときに一緒に住んでいたんです。俺がよくその家に遊び行ってて、Mとも仲良くなった」
MC MUSIC「Eは高校を中退して高円寺で弾き語りしているというのを聞いて、会う前にはやべえ奴だなと思った」
石指「滅茶苦茶アウトロー(笑)!」
M「でも会っていくうちに普通の人だとわかって仲良くなれた」
E「そのあとMとCがラップにハマったんですよ。2人が〈ラップ最高、ヒップホップ最高〉となって、トラックを作ってくれと言われた。俺も作ったことないのに」
M「僕とCは音楽を作れないから作れる人にやってもらおうとEを頼ったんです」
――それは何年頃ですか?
M「2012年の夏くらいですね。遊び半分で集まってみて、〈まったくできないな〉となって一回諦めた(笑)。コンセプトを詰めようとして結局何もできずに」
石指「ガチガチに固めてからスタートしようとしたんだ?」
M「いまの世の中にないラップをやろうと思ったんですけど……作れなかったですね(笑)」
E「ロクでもないアイデアしか思い浮かばず、次にやったのは冬でしたね。そこで“ラップ道”を録ったんです。トラックは夏の時点ではあったんですよ」
M「そうそう、あのなんだっけ。シェルリ……」
E「シェリル・リンをサンプリングして」
M「思い出野郎AチームやY.I.Mとか、友達で音楽をやっている人が多くて、自分はその近くにいる1人だったんですけど、〈なんかできるっぽい〉みたいな空気があったんです。2012年の末に、思い出野郎が主催する〈SOUL PICNIC〉というイヴェントがあって、そこでジンやアクセサリーなど自分で作ったものをフリマで売っていいですよ、フリマの参加者は入場料が安くなります、みたいな企画があった。ちょうどそのイヴェントの日に僕らも集まってたから、安く入れるように今日売るCDを作ろうとなったんです。とにかく1曲録ろうと。その場でラップ作って録音して、CD-Rに焼いて入場料代わりに持って行って、2枚だけ売った。売り場にいなかったので誰が買ってくれたかはいまだに不明ですね」
E「それが最初にSoundCloudにあげた“EMCのラップ道”」
M「あと大江千里の“格好悪いふられ方”をリミックスした謎の音源もCD-Rに入れてました」
――フリマに出すならジンでも雑貨でもいろいろ選択肢がありそうに思うんですけど、どうして音楽を選んだんですか?
M「2011年くらいからラップをヒュッと始める人が多くなったじゃないですか? “Local Distance”や“徳利からの手紙”とか、どこの馬の骨か知らない人がネット上にアップして、ちょっと話題になっていた。それがそれまで聴いたことのあった日本語ラップよりフレッシュだなと思った。スキルとかよりアイデアで勝負してる感じがなんか大喜利っぽくて、内容の面白さで勝負できるみたいな。みんな音楽をできない人がやっていたから、じゃあ俺でもできるかもと思った。音楽でいちばん敷居の低さを感じたんです。それでCと話して、じゃあちゃんと音楽できる奴が1人いればきっとできるだろうとなったんです」
――石指さんとEMCが出会ったのはいつ頃なんですか?
石指「EMCを結成する前ですね。5、6年前じゃないかな、最初に会ったのはCくんです」
E「石指さんが弾き語りを始めた頃ですか?」
石指「まだ弾き語りじゃないね。その頃はバンドでギター弾いてました。で、バンドで出たイヴェントの打ち上げに行くと、そこにCくんもいたんですよ。その日は打ち上げがすごく中途半端な時間に終わるパターンだったんです」
E「夜の3時とか?」
石指「そうそう。あと1時間くらい待てば始発が来るくらいの時間に終わった。阿佐ヶ谷で解散になって、Cくんは確かそのときに中央線の遠いところに住んでいたんだよね。俺は吉祥寺に住んでいて、Cくんも吉祥寺まで行って漫喫で時間潰して帰ると言っていたから、〈じゃあ一緒に吉祥寺まで歩いて行こうよ〉となったんです。僕もCくんも落語がすごく好きで、打ち上げでも落語の話で盛り上がっていたから、その日が初対面だったけど、落語の話をしながら阿佐ヶ谷から吉祥寺まで歩いた。2時間半くらいかかったな。それから次に会うまではまた2年くらい空くんですけどね。でも次に会ったときもお互い覚えていたからワーワー話せたな」
――初対面のエピソード、ちょっと映画「ビフォア・サンライズ」みたいで素敵ですね。
石指「なんかね、2人で歩いて帰っても話が持ったんですよ。お互い気を遣わずに過ごせた。だって話が続かないと2時間も歩いて帰れないでしょう(笑)」
M「石指さんは誰とでも大丈夫な気がするけど」
石指「いやいや、俺だって打って響かんと話さんよ。響く人じゃないと(笑)。その次に会ったのがEくんですね。彼は僕の弾き語りライヴに来ていたんですよ」
E「三鷹おんがくのじかんですね。僕は石指さんを観に行っていたんですよ」
石指「そこでEくんが話しかけてくれたんですね。そのあとも池袋のオルグとかで何回か会った。そのくらいのときに、彼が銭湯で企画ライヴをして、僕を誘ってくれたんですよ。僕と大森靖子さんとスカートさんと彼という面々でね」
M「豪華だな」
E「でも人は全然入らなくて、ヤバかったすよ」
石指「そんときにCくんとも再会したんだよね。思い返すといろんなことが繋がっているように感じる。その銭湯ライヴから2年が経って『緑町』の発売に至るんですよ、緑町』の ジャケットのイラストを描いてくれた花原(史樹)くんとEMCが一緒に使っている作業場があって、花原くんとの打ち合わせや『緑町』のジャケット制作はほとんどそこでやっていたんです。僕がそこに行くとEMCのメンバーも大体いるんですよね。初めてMくんと会ったのもその作業場だったね」
M「そうですね。でも不思議な縁があったんですよ。高校のときに失恋したことがあって、そのときに先輩が〈音楽を聴いたほうが良い、音楽が失恋の痛みを和らげてくれる〉と50枚くらいCD-Rをくれたんです。スペシャルズとかオシリペンペンズとか入ってましたね。その先輩とはいまも仲良いんですけど、彼が大学のときにバンドを始めて、実はそれが石指さんも在籍してたバンドなんですね」
石指「へー! 作業場でみんなで遊んでいるときに、EくんからEMCの『FOREVER』と『緑町』のリリース日が近いという話もされたんだよね。僕は自分の作業がなくてもその場にいるのが楽しいから、よく自転車で作業場に行ってたんです(笑)」
E「よく来てましたね(笑)」
石指「花原くんとお酒呑んでるうちに、EMCが来てみんなで話をするんだよね。その時間が楽しくて無駄に行っていたんです。そこでEくんから〈こういう曲をやりたいんですけど手伝ってくれないですか?〉という相談が来たんです。僕も〈良いよー〉と即答した。『緑町』の発売前後にはいろいろなところにツアーに行っていて、その日は東北方面のツアーに出る3日前だったんですけど(笑)」
E「その曲が『FOREVER』の1曲目の“ENJOY OPENING”ですね」
石指「もう明日レコーディングすると言うから、僕は家からギター、マンドリン、バンジョー……なにからなにまで家から作業場に運んだ。鈴とか小物もね。ツアーの3日前に相談されて2日前に録音した」
E「無茶なスケジュールでやってくれましたよね」
石指「でも、相談くれたとき〈これはやっとこう〉と思ったんだよね。部室ノリというか楽しいからやる、みたいな。アレンジも聴かせてもらった瞬間に思いついたし、レコーディング自体はさくさく進んだ」
――Eさんが石指さんにお願いしたのはミュージシャンとしての信頼があったからですか?
E「そうですね。30秒くらいのオープニングをこういう曲にしようとなったとき、もうイメージがパッと出てきました。これは石指さんだなと」
M「花原くんが作業場でひたすら石指さんのCDをかけてたんだよね(笑)。それでみんなが大好きになった」
E「石指さんのことはバンド時代から知っていたし、ギターが滅茶苦茶上手いとはずっと思ってました」
石指「昔、EMCの裏設定みたいなこと話してくれたよね?」
E「え? それなんすか」
石指「その時代その時代にEMCは存在した、みたいな」
E「あー、ありましたね(笑)」
石指「〈Enjoy Music Club〉という概念だけあって、第1期EMCは60年代にいて、それはカントリーという形を取っていた。で、僕はEMCの第1期メンバーという設定なんだよね(笑)。第2期はパンクで、そいつらはあんまり人気なかったとか、そういう時代を跨いでミュージックをエンジョイするという概念だけが受け継がれて、現代がラップだったという」
M「サイケ期がどう、みたいなことも言ってましたよね(笑)」
――その設定、最高ですね。
E「俺はずっと疑問だったんですけど、石指さんはバンドではギタリストだったのにどうして弾き語りを始めたんですか?」
石指「俺の音楽原体験はブルーハーツなんです。地元の中古CD屋で〈これ“リンダリンダ”歌ってる人のCDだ〉と思ってファースト・アルバムを買って聴いてみて、〈めっちゃカッコイイ!〉となった」
E「地元はどこなんですか?」
石指「鳥取。最初はベーシストがすごくカッコイイと思って、ベースを買ってもらってブルーハーツをコピーしまくってた。でも親父が昔使っていたギターが家の押入れに2本あったんですよ。それもあって14歳の頃になんとなくギターを始めたんです。でも本格的に音楽活動を始めたわけじゃなくて、ずっと部屋で1人で弾いてました。演奏活動は実家を出るまではずっと同じですね。家でひたすらギターを弾いているだけという」
M「オリジナルも作ってたんですか?」
石指「いや、俺がオリジナルを作ったのは20歳過ぎてからだね。だから耳コピしてた。ただ好きな曲を弾けて楽しいなと思っていた」
E「歌いたいという気持ちもなかったんですか?」
石指「部屋でギターを弾きながら歌ってたけど、古いフォークばっかり歌ってた。フォークのギターは難しいけど楽しいなーとかほんとそんな感じ」
E「東京に出てくるのは何歳のときですか?」
石指「21歳のとき」
M「高校でバンドやったりは?」
石指「全然やってない。部活ばかりしてた」
E「何部ですか?」
石指「バレー。俺キャプテンよ」
EとM「キャプテン!」
M「じゃあ、文化祭で演奏したりは?」
石指「俺はね、高校で軽音部に入ったりバンドやったりしている奴をダサイと思ってたのよ。友達にもギター弾けることを言わんかったしね。〈こいつギター弾けるんだぜ〉〈まあ弾けるけど〉みたいなノリがすごく嫌で。」
M「そのセリフ聞いたことある(笑)」
石指「あるでしょ? 家で遊んでで誰かがギターを弾き出したら、その演奏をみんなが聴かないといけないみたいなのが嫌だったのよ。そんなことよりみんなでワイワイ楽しく話したかったし、そこにギターとか挿みたくなかったんだよね。だから高校3年間は頑として表に出さなかった。ただの明るいスポーツ少年」
M「でも家帰ったらずっと弾いてたんですよね?」
石指「家に帰るとね。めちゃくちゃ田舎だからアンプがフルテン(アンプのツマミをすべて最大値の10にすること)でも全然問題ないんだけど、お婆ちゃんが畑から戻ってくるときに〈1個目の曲がり角で音が聴こえてきたから流石にデカイじゃないか〉と注意された(笑)」
――表と裏の顔を持つ少年だったんですね。
石指「親父のギターが押入れにあったということは、親父も音楽が好きだったということじゃないですか。親父はフォーク・ブーム真っ只中の人だったんですよ。で、親父の手書きの大学ノートが家にあって、それを見たらニューミュージック期の松山千春の曲や伊勢正三の“風”とかのコード進行を手書きでいっぱい書いていたんですね。で、それをコピーすると親父が喜んでくれるんですよね」
M「良いっすねえ。じゃあお父さんには見せてたんですか?」
石指「見せてたというよりは、俺が2階で弾いてるのを親父が1階で聴いている、俺が1階に降りると親父が〈お前ギター上手くなったな〉と言う。そういうやりとり。でも、それが嬉しくてね」
E「良い話だなぁ」
石指「だからフォークの入り口は親父の手書きのノート。そこから掘り下げていって岡林信康や高田渡、泉谷しげるなどに辿り着いた。聴いてて笑えるコミック・フォークもすごく好きでしたね」
――その当時はネットで音楽を聴く機会もまだなかったように思うんですけど、どうやってフォークを掘っていったんですか?
石指「うちはパソコンもなかったし、いまみたいにスマホもないですしね。ネットができるところで、フォークを紹介しているブログや記事をひたすら読んで、歌手名をメモしてました。ガッツリ探し出したのは、実家を出てからです。当時流行ってたものも聴いてましたよ。GOING STEADYやMONGOL800、Hi-STANDARDやSNAIL LAMPとか。でもバンドは一切やってなかった。音楽活動をスタートしたのは上京してからですね」
M「どういう心境で上京されたんですか?」
石指「東京に行くきっかけは、友達が上京するって言うから〈じゃあ俺も〉と付いていっただけ。でも、そこで〈音楽やろうかなー〉と思って弾き語りを始めてみたんです。すぐ挫折したんですけど。人前で歌う、緊張する、持ち時間30分あるけどまだ5分しか経ってない……みたいなね。もう心が持たないし向いてねえなと思って、自分で歌うのは辞めたんです。それで弾き語りからバンドに移りました。九龍ジョーさんとその頃初めて会ったんですけど、すげえショックなこと言われたな。いま思うとそんなに気にする必要なかったけど、まだ若かったし、信頼する大人に言われたことは100%正解に思えたから」
E「なんて言われたんですか?」
石指「〈歌った瞬間に空気が変わらない〉と言われた」
EとM「キツイっすね(笑)」
石指「当時はね。プレイヤーに専念したほうが良いのかなと思って、いろいろなバンドに入ってました。20代半ば頃、4年前くらいにもう1回弾き語りでやってみてやっぱりダメだと思ったら音楽辞めようと思い直して、弾き語りでの活動を再スタートしたんです。才能の有無じゃなくて、自分の心がめげたら辞めようと決めた。すでに1回めげてるくせにね。最初は修行のようでしたけど、やっていたら楽しくなってきたんです。いまでも〈心が折れるまではやろう〉というスタンスは変わってないですね。別に覚悟を決めて音楽をやろうというわけではなく、折れない限りはやるし折れたら辞める、という」