〈傑作〉というのは間違いない
2011年7月23日、27歳で亡くなったイギリスのシンガー、エイミー・ワインハウス。その早すぎる死から間もなく5年を迎える7月16日より、波乱に満ちた彼女の生涯とその素顔を炙り出したドキュメンタリー映画「AMY エイミー」が日本全国で順次公開される。デビュー前からのプライヴェート映像に加え、サラーム・レミやマーク・ロンソン、トニー・ベネットといったエイミーと縁の深いミュージシャン/関係者の証言などで構成される同作は、昨年本国で公開されて本年度の米アカデミー賞・長編ドキュメンタリー賞を受賞した話題の作品だ。
同作の日本公開に先駆けて、去る4月15日にタワーレコード渋谷店で公開記念キックオフ・トークショーが開催された。登壇したのは、「〈傑作〉というのは間違いない」と太鼓判を押す、「AMY エイミー」の字幕監修を担当したピーター・バラカン氏と、エイミーが家族と暮らしていた北ロンドンのエリアに住んでいた経験もあるというラジオ・パーソナリティーのレイチェル・チャン氏。この2人がひと足早く、この作品の見どころを解説してくれた。

放っておいてあげればたくさん良い音楽を作ったはずなのに、誰も放っておけなかったことがエイミーの悲劇の始まりで、まるでシェイクスピアの悲劇のようにさまざまな要素が見事に揃ってしまったと、バラカン氏は「AMY エイミー」を振り返って語る。本作の監督を務めたのは、「アイルトン・セナ~音速の彼方へ」(2010年)を手掛け、現在はオアシスのドキュメンタリー映画に着手しているというアシフ・カパディア。彼が製作に取り掛かるにあたってエイミーの情報を集めるため、彼女ともっとも親しかった幼馴染みの女性2人と、最初のマネージャーであるニック・シマンスキーらにコンタクトを取ったが、エイミーと親しければ親しい人ほど彼女について話したがらなかったという。しかし、かなりの時間をかけて少しずつ信頼を得ていき、ついに彼らが話しはじめると、背負っていた重荷を降ろすかのようにどんどん話が溢れていったのだそう。
その甲斐あって、エイミーの関係者でさえも知らなかったという彼女のデビュー前の姿がこの映画であきらかになっている。これこそが本作の肝で、レイチェル氏が「このドキュメンタリーのために撮っていたのかなと思うくらい細かく、デビュー前のエイミーの普段の自然な姿を収めた映像が大半というのが凄い」と語っている通り、先述した初代マネージャーのニックが所有していた多くのプライヴェート映像で浮かび上がるエイミーの素顔は、歌うことが好きな本当に普通の女の子。しかし本人は当初、歌手になりたかったわけではなかったという。「表舞台に立ちたいと思っていなかった人が、こういう形でスターダムにのし上がっていくというのは、ある意味、悲劇的な運命だったのかもしれない」(レイチェル氏)――自身の音楽で人々に大いなる感動を与えたぶんだけ自分の人生を犠牲にしてしまった、そんなふうにも映る哀しい現実だ。

作詞家としての独自の才能
エイミーの人生において、恋人や親との関係も大きなポイント。本編ではもちろんそういった点にも注目したい。ご存知の人も多いかと思うが、彼女が酒やハード・ドラッグに溺れるきっかけとなったのが、ブレイク・フィールダー・シヴィルという男との交際。一度破局を迎えたものの、エイミーの世界的なブレイクののちに復縁して夫となる(が、程なく離婚)彼にのめり込んだことが破滅への入り口だった。レイチェル氏がエイミーの印象的な1曲として挙げた“Back To Black”(2006年作『Back To Black』収録)は、ブレイクと最初の別れを経験し、どん底のなかで書かれたナンバー。「特定の人(ブレイク)との別れを痛々しいほどに書かれている。〈涙が乾ききるくらい泣いた〉という歌詞を踏まえて映画での彼女の眼を見ると、この方は何度涙を流さず心の中で泣いてきたんだろうというくらい深い。日本でここまでの詩を書く人はそういないと思う」と言う。
バラカン氏も同調して、「作詞家として独特というか、独自の才能がありますね。彼女のような歌詞を書く人はそういない。自分の感情をストレートに表現していることもあれば、詩的な表現もある」と絶賛する。そんなバラカン氏は、エイミーの1曲として“Rehab”(同『Back To Black』収録)をピックアップ。初めて彼女の音楽に触れたのがこの曲だったそうで、「1回聴いただけで吹っ飛んだ。いまの時代に僕が吹っ飛ぶような音楽はそうないけど(笑)、これはとんでもないと思った」という。往年のジャズ・シンガーの面影をエイミーに見たと彼が語るその感性は、ジャズ好きである父、ミッチ・ワインハウスの影響だと思われる。
エイミーの父親・ミッチ(娘の七光りで2010年にジャズ・シンガーとしてデビューまでしている)は、映画「AMY エイミー」に最初から否定的で、いっさい協力しないという姿勢を取っていたそう。ただ、その理由は本編を観ればよくわかるはず――悪く描かれているわけではないけれど、観ていて決して良くは思わないはず、と登壇した2人は声を揃える。しかし、エイミーは最期まで父を慕い続けた。それは“Rehab”の〈みんなが私にリハブに入れっていうけど、私の返事はノー/だってパパも大丈夫だって言うから〉という歌詞からも窺える。エイミーの歌とも密接に関わる恋人や近親者との関係性を知ることで、彼女の楽曲に対する解釈もまた変わってくるかもしれない。

悲劇的な人生以上に、音楽への強い想いを感じてほしい
また、バラカン氏からは興味深い指摘も。この映画ではエイミーが子供の頃に好きだったダイナ・ワシントンやビリー・ホリデイ、サラ・ヴォーンといったジャズ・シンガーについて語っているのだが、なかでもダイナ・ワシントン(1940年代中盤~50年代に活躍)はジャズとリズム&ブルースを股に掛けたシンガーで、エイミーのフェイヴェリットだったのもよくわかる、と。さらに、ダイナは言葉のキツい女性だったそうで、エイミーもまたライヴのMCやインタヴューなどではかなりバッド・ランゲージが飛び交っていた……そんな知られざる共通点もおもしろい。
イヴェントの最後には、「AMY エイミー」のなかでも注目してほしいシーンについて紹介された。レイチェル氏は本編終盤に登場する、エイミーが亡くなる直前の心身共にボロボロの状況のなかでプロデューサーのサラーム・レミと電話で話しているシーンを挙げ、「(エイミーが)次から次へと言葉が湧いてきてどうしようもないから早く一緒に(アルバムを)作りたいとサラームに訴えているんです。命の糸が切れそうな状況でも音楽のことをずっと語っている。最後の最後まで彼女は〈歌いたい〉という気持ちが滲み出ているので、彼女の悲劇的な人生以上に、音楽への強い想いを感じてほしい」という。
一方、字幕監修のためにすでに4回ほど同作を観ているというバラカン氏は、印象に残ったシーンをひとつだけ選ぶのは難しいとのことで、「観るたびに発見がある映画。回を重ねるごとに細かいところに気付くんですよね」と語る。ただ、この映画を通していっそう悔やむ気持ちを強くするのは、何よりエイミーの不在だ。バラカン氏いわく「若い歌手が俄かに売れてしまうことが必ずしも良いことではないということがよくわかる映画です。成功するということがどういうことかを考えさせられる映画だと思います」――図らずも突然名声を得たことで生まれてしまった深い闇がそこにある。
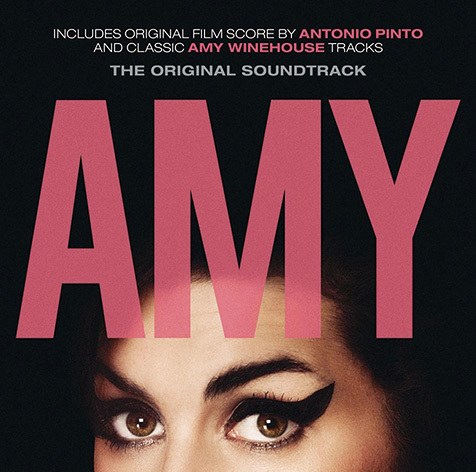
この2人のトークで浮かび上がったのは、映画「AMY エイミー」はこれまでわれわれが見聞きしていたエイミー・ワインハウスの姿だけでない、素の彼女がしっかり掘り下げられているということ。打算なく純粋に愛を求めた一人の女性の真実に触れることで、彼女が歌った楽曲の深さを新たに知ることになるだろう。






























