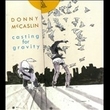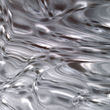サックス奏者のダニー・マッキャスリンがリーダーとなって、デヴィッド・ボウイの遺作『★』で中核を担ったメンバーたち――マーク・ジュリアナ(ドラムス)、ジェイソン・リンドナー(キーボード)、ティム・ルフェーヴル(ベース)の4人が集結し、2月1日(水)~2日(木)にブルーノート東京で来日公演を行う。ダニーが昨年9月に発表したリーダー作『Beyond Now』には“Warszawa”などボウイ関連のカヴァーも収録されており、生前の彼を魅了したハイブリッドなサウンドはますます深化。最期のレコーディングを彩った実力派グループの演奏が、いよいよ日本で初披露される。
では、一周忌を迎えたこのタイミングで改めて問いたい。ボウイはなぜ、人生最後の作品に新世代ジャズ・ミュージシャンを選んだのか? ロック史を塗り替えたNYの精鋭ジャズメンは、いったい何がスペシャルなのか? その答えを確かめるべく、敬愛するマーク・ジュリアナをゲストに迎えて、1月30日(月)にブルーノート東京での初ライヴを開催するYasei Collectiveを直撃した。ダニー・マッキャスリン・グループの面々に早くから多大なる影響を受けてきた彼らは、映像やライヴなどを通じてプレイを長年研究しながら、自分たちのパフォーマンスに採り入れてきたという。そこで今回は、ヤセイの松下マサナオ、中西道彦、斎藤拓郎、別所和洋がそれぞれ厳選した同グループのライヴ動画を鑑賞しながら、各メンバーの魅力を掘り下げていきたい。
ちなみに、冨田ラボ×柳樂光隆両氏がボウイと現代ジャズの関係性を語った記事や、ダニー・マッキャスリンが『Beyond Now』の制作背景やボウイとの記憶を振り返ったインタヴュー、今回共演するきっかけになったというマーク・ジュリアナ×松下マサナオのドラマー対談のほか、上述した両公演にまつわる関連記事のリンクも記事中に用意したので、併せてチェックしてほしい。
★ダニー・マッキャスリン・グループ公演詳細はこちら
★Yasei Collective with マーク・ジュリアナ公演詳細はこちら

――ダニー・マッキャスリン・グループの話をする前に、まずはYasei Collectiveの2016年を振り返ってみましょうか。最新作『Lights』のリリースもあり、飛躍の1年だったのではないかと。
斎藤拓郎(ヴォーカル/ギター/シンセサイザー)「フェスにもたくさん出演させてもらったり、いい年だったよね」
松下マサナオ(ドラムス)「レコーディングしながらフェスを回ったり、イヴェントに誘われる一方でコンピレーションに参加したり、以前よりも忙しくなった感じがしますね。それに各自がサポート・メンバーで呼ばれたり、曲を提供したりするときに〈ヤセイのときみたいな感じで〉というオファーがすごく増えたんですよ。そうやってバンドを軸にしつつ、個人活動も活発になった1年だったと思います」
――ヤセイが渋谷慶一郎さんの主宰イヴェントに招かれ、松下さんがSeihoさんのライヴに呼ばれたかと思えば、中西さんは村上”ポンタ”秀一さん率いるNEW PONTA BOXに参加して、最近もKID FRESINOによるTV番組「モヤモヤさまぁ~ず2」のエンディング曲“Salve”に斎藤さんが参加したりと、ジャンル/世代を越えて広く求められるようになった印象です。
松下「あとは海外の実力派ミュージシャンにとって、〈日本に来るならヤセイに訊け〉みたいなルートの一つになりつつある手応えも感じました。デヴィッド・ビニーやルイス・コール、ベン・ウェンデルが僕のところに直接連絡を送ってくるんですけど、そういうケースがどんどん増えている。嬉しいですよね、普通のバンドマンではなかなかないことだろうし」

――さらに9月には、〈Blue Note JAZZ FESTIVAL in JAPAN 2016〉への出演もありました。
斎藤「かなり響いた手応えがありましたね。メイン・ステージにはかなりの大物が出演していたのに、僕らのことを観に来てくれる人がたくさんいて」
中西道彦(ベース/シンセサイザー)「ジョージ・ベンソンのサポート(・メンバー)で来ていたデヴィッド・ガーフィールドという有名なキーボード奏者が、物販スペースに座りながら僕らのライヴを観ていたんですよ。しかも終演後に、〈あの演奏はどうやってるんだ!?〉といきなり話しかけられて(笑)。あれはビックリしました」
――2016年の初めにはマーク・ジュリアナと松下さんの対談も実現しましたが、そこから1年後にヤセイとマークの共演が開催されるようになるとは思わなかったです。〈Blue Note JAZZ FESTIVAL〉での好演も大きかったんでしょうね。
松下「間違いないです。〈ダニー・マッキャスリンの来日に合わせて、マーク・ジュリアナと一緒に出演するのはどうですか?〉とオファーをいただいたときは、もちろん即決しました(笑)」
――その共演については後ほど伺うとして、みなさんがダニー・マッキャスリンを意識するようになったのはいつ頃でしたか?
別所和洋(キーボード)「3~4年くらい前ですね」
松下「マーク・ジュリアナやティム・ルフェーヴル、ジェイソン・リンドナーのことはもっと昔から追いかけていたんですけど、そんな僕らにとってのアイドル的なミュージシャンが、あるときからダニーを中心にして集まるようになったんですよ。そこから注目するようになりましたね」
――エレクトロニック・ミュージックとジャズの即興演奏を組み合わせた現在の音楽性が、マークとティム、ジェイソンが揃った2012年の『Casting For Gravity』から本格化していったんですよね。ダニーのリーダー作についてはどんな印象を抱いてます?
別所「そういったコンセプトをキープしつつ、作品を重ねるごとにクォリティーを高めている感じがしますよね。最新作の『Beyond Now』は近作のエレクトロニックなアプローチを維持しつつ、アコースティックな要素も柔軟に採り入れていますし」
松下「あとは、録り方も変わった気がしますよね。前の作品ではリズム・セクションをセパレートして録音しているような感じで、リズム面のおもしろさが伝わってくる反面、主役のダニーが少し浮いているようにも聴こえましたけど、最新作はダニーのサックスが率先してバンドを操っている感じがして、すごく一体感が生まれている。僕はやっぱり、最新作と前作の『Fast Future』(2015年)を聴く回数が断然多いです」

マーク・ジュリアナ
――ここからは、ヤセイのみなさんに選んでもらったダニー・マッキャスリン・グループのライヴ動画を一緒に観ながら、各プレイヤーの魅力を掘り下げていきましょう。まずはマーク・ジュリアナ。現代ジャズを代表する人気ドラマーですが、同じドラマーの松下さんから見て、どんなところがすごいと思いますか?
松下「とてつもないソロを叩いている動画があるので(再生開始から1分後~)、まずはそれを観てほしいです」
松下「ハットで8分音符をずっと刻みながら、キックとスネアだけでインプロしているんですけど、これがメチャクチャ難しいんですよ。上半身も下半身も動きが異常ですよね。さらにマークがすごいのは、何をやっても軸がブレないところで」
――恐ろしいスピードで叩きまくっているけど、破綻するどころか、むしろ安定しているように感じるというか。驚異的な精度ですね。
松下「そうそう。(5分過ぎ~の)リズム・チェンジも最高にカッコイイ」
――あまりにすごすぎて、客席から呆気にとられたような笑い声が聞こえてきましたね(笑)。
松下「これが2012年のライヴだから、いまはもっとすごいわけですよ。この動画を選んだのはもう一つ理由があって、最近のマークはここまで無邪気に入り込んでいる演奏が少し減ってきているんですよね。ジャズ・クァルテットを率いたりしているのもあって、大人の演奏が求められるケースが以前より増えているので」
――なるほど。マークとティム、ジェイソンの3人はダニーと組む以前から何度も共演してきただけあって、演奏にも一体感があるような気がします。
松下「初期のビート・ミュージック(マークが率いるエレクトロニック・ユニット)はその3人で活動していたんですよね。LAのブルー・ホエールというライヴハウスでビート・ミュージックが演奏している動画があるんですけど、それもいいんですよ。〈左手でそんなフレーズ叩くの?〉みたいな感じで、マークがどんな演奏をしているのかすごくわかりやすい。ドラマーなら絶対に観たほうがいいと思います」
――このドラムを生で観れるだけでも、ダニーのライヴに足を運ぶ理由として十分すぎる気がしますね。
松下「今回の3人が集まったときのダニー・マッキャスリン・グループは、完全にロックだと思うんですよ。マークも相当楽しそうに叩いているじゃないですか」
――彼は決してエゴを押し出すタイプではないんですよね。松下さんとの対談で〈今後の人生で一度もドラム・ソロを叩かなくてもいい〉と語っているし、『★』でもボウイが用意したデモに忠実な演奏を心掛けたそうなので。その一方で、ダニー・マッキャスリンと演奏するのは〈自分らしい演奏を期待される機会〉だとも語っているので、今回はリミッターを解除したパフォーマンスを観ることができるかもしれない。
松下「そうなったら最高ですね! 以前、僕らのブログ〈ヤセイの洋楽ハンティング〉でマークが現在のスタイルに辿り着くまでの動画をセレクトしているので、それも改めてチェックしてもらえたら嬉しいです」

ティム・ルフェーヴル
――同じベーシストの中西さんにとって、ティム・ルフェーヴルはヒーローなんですよね。
中西「そうです。これも2012年のライヴ動画で、ティムが中心に映っている珍しいアングルなんですよ」
――中西さんから見て、ティムの魅力はどんなところにあると思いますか?
中西「マークとティムの姿勢が対照的ですよね。ひたすら前のめりに打ち込むマークに対して、ティムは直立不動でどっしり構えている。見た目でどうこうってわけではないけど、こういう姿勢の人がバンドにいたら安心すると思います」
――この動画でも、首を揺らしながらとんでもないプレイを披露していますけど、表情は〈余裕だぜ!〉って感じですよね。周りのメンバーがどんな演奏をしても、彼のベースがしっかり支えてくれそう。
中西「それに繊細なところもあって、〈そこだよね〉というところにジャストで音を入れられるんですよ。だからこそ、いろんな仕事を経験しているんだと思います。彼の経歴は幅広くて、テデスキ・トラックス・バンドや(USの人気番組)『Saturday Night Live』のハウス・バンドにも参加したことがあるんですけど、それはアメリカで一番安心できるミュージシャンである証だろうし」
――ドナルド・フェイゲンのバックを務めたこともあるくらいですからね。
松下「ちなみに、ダニー・マッキャスリン・グループではネイト・ウッドがドラムを叩いたり、ときにはベースを弾くこともあるけど、ネイトが参加すると演奏がグッとタイトになるんですよ。バンドっぽさよりもセッション感が増える感じ。ティムはその逆で、もっと独創的なタイプの人ですね」
中西「ネイトはすごくプレイが精密だけど、ティムはそういうアカデミックな感じではないんですよ。ただティムがすごいのは、勘に頼った演奏でグイッと引き戻す瞬間があって。そういう瞬間に野性味というか、人間らしいドロっとしたものが溢れ出るのがすごくいい。上手くてタイトなベーシストは山ほどいるけど、こんなふうに空間がグニョンと捻じ曲がるような演奏する人はそういないと思います」
――それを聞くと、既存のロックを回避するために、ジャズ・ミュージシャンにロックを演奏させるという『★』のコンセプトにもうってつけだったのでしょうね。
松下「音一つとっても、ティムの強烈さは違いますもん。エレクトロニックだし、ドラマーの立場からすると引っ張ってくれる感じがする。なにせ彼は、キース・カーロックとマーク・ジュリアナという、2000年代中盤に出てきた2大ドラマーとがっぷり四つでやってきたベーシストですから。キース・カーロックはいまやスタジオ/ツアー・ミュージシャンの頂点だし、マークはインプロの最高峰ですけど、その両方からファースト・コールで迎えられるだけの実力がティムにはあるんですよ」