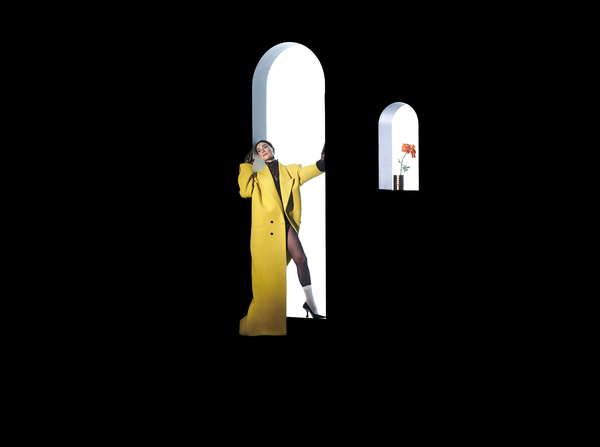◎&△$♪¥○?×%#!!! 言葉にできない叫びに託された生きることの真理とは? ペルソナを脱ぎ捨て、〈自分自身〉になった彼女の歌、ギター、ビート――そこには強烈な衝動とパワフルな鼓動が刻まれている!!!
生身の姿で向き合った生と死と愛
USインディーを代表するギター・クイーンにして、テイラー・スウィフトの大ヒット“Cruel Summer”の共作者、そしてオリヴィア・ロドリゴとは音楽家として相思相愛の仲(オリヴィアの“obsessed”も共作)。ジャンルや世代を超えて畏敬の念を集めるセイント・ヴィンセントことアニー・クラークによる最新作『All Born Screaming』の日本盤が、新年の〈rockin’on sonic〉での来日を記念してリリースされる。第67回グラミー賞では4部門にノミネート、批評筋からも評価が高い本作を改めて紐解く。
ここ10年ほどのセイント・ヴィンセントは敬愛するデヴィッド・ボウイさながら、作品ごとに新しいペルソナを纏い、音楽性やヴィジュアルを刷新してきた。『St. Vincent』(2014年)では〈近未来の新興宗教の教祖〉として銀髪姿でダンサブルなギター・ロックを提示し、ボンデージ姿でインダストリアルなエレクトロ・ファンクを鳴らした『MASSEDUCTION』(2017年)では〈精神病棟のSM女王〉を標榜、そして父親が好きだったという70年代ソウル/シンガー・ソングライター的なサウンドに転身した前作『Daddy’s Home』(2021年)では俳優のジーナ・ローランズやキャンディ・ダーリンをイメージした金髪のウィッグ姿で人々の前に登場した。しかし今回のアルバムで彼女は、特定のペルソナを演じることを辞めたという。理由は、プライヴェートで身近な人を亡くし、その悲しみを表現することを本作では念頭に置いていたから。つまり今回の彼女はアニー・クラークという生身の姿で、本人いわく〈生と死と愛〉という人間の根源的かつ普遍的なテーマと向き合うことに決めたのだ。
これまでのアルバムごとにペルソナを変えるという発想は極めてスリリングであったものの、ときにテーマに縛られすぎることによって彼女本来の良さが発揮しきれないこともあった。セイント・ヴィンセントといえば何よりもまず才気溢れるギタリストだが、例えば『Daddy’s Home』はピアノやギターのコード・ストロークが多く、得意のギター・リフがかなり抑制されていたため、やや物足りなさを感じた人もいただろう。だが本作は久しぶりにペルソナという制約を脱ぎ捨てたことによって、これまで以上に幅広い音楽性が自由闊達に表現されている。
まず耳を引くのは、リード曲でもあった“Broken Man”と“Flea”だ。激しいギター・ノイズ(とシンセのホワイト・ノイズを重ねたもの)が暴れ回るこれらの曲は、いわばセイント・ヴィンセント流のグランジ・ソング。彼女は9歳のときにニルヴァーナの『Nevermind』を聴き、〈これこそが自分の音楽だ!〉と衝撃を受けたという。〈生と死と愛〉という主題に向き合うにあたって、自分の人生にとって重要な瞬間に立ち返るのは筋が通っている。しかも、この“Flea”でパワフルなドラミングを聴かせるのは、元ニルヴァーナ/現フー・ファイターズのデイヴ・グロール。そして“Broken Man”の強烈なドラムは、グロール、現行ジャズ界屈指のドラマーであるマーク・ジュリアナ、そして本作のミキシングも担当するキアン・ライオダンの3人体制だ。これ以上に完璧な布陣はない。
他の収録曲も目を見張るものがある。コクトー・ツインズを意識したという耽美な“Hell Is Near”、『MASSEDUCTION』の進化系とも言えるファンキーな“Big Time Nothing”、マーク・ジュリアナのグルーヴィーなドラムが映画サントラ風のサウンドに映える“Violent Times”、どこかデヴィッド・ボウイ“Five Years”を彷彿とさせる美しいバラード“The Power’s Out”、亡きソフィーに捧げられたトロピカルな“Sweetest Fruit”、スカ/ダブのスパイスが効いた“So Many Planets”、そしてウォーペイントのステラ・モグザワがドラムを叩き、ケイト・ル・ボンをフィーチャーしたアフリカ音楽~テクノ的な“All Born Screaming”。まったく異なるアイデアを持った曲が並ぶが、アナログ・シンセの生々しいサウンドがほぼ全曲で通奏低音となっており、個性豊かな楽曲群を1枚のアルバムへと見事に繋いでいる。