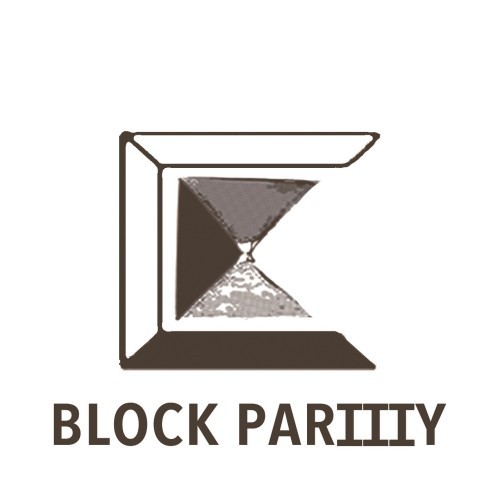東京を拠点に活動する5人組ロック・バンド、The ManRayがファーストEP『You will be mine』をリリースした。DYGLやGi Gi Giraffeらとも共振する、2000年代以降のガレージ・ロック勢からの影響を感じさせつつも、古のソウルやR&Bから受け継いだ黒いグルーヴ感、ダルなヴォーカルが醸すレイドバックしたムードは、若いインディー・リスナーにもフレッシュに響くことだろう。今回はギターのTenshiroを除くメンバー4人に、DJ/音楽ライターのTAISHI IWAMIがインタヴューした。 *Mikiki編集部
渋いメロディーが沁みた。しなやかなグルーヴに体が揺れた。力強いフレーズに魂が震えた。そして気持ちが晴れた。それを人はブルーズやファンク、ロックンロールと呼ぶ。つまり作り手がさまざまな音楽を折衷することは、日々の心情を映し出そうとすることだ。自らに素直であればあるほど〈リアル〉であり、それが誰かの心に響いた瞬間〈ポップ〉となる。
承認欲求を満たしたいがゆえにちょっと格好つけてみたり、無理して何かに合わせてみたりする。しかし本来持っている遊び心は忘れたくない。〈狙う〉ことと〈楽しむ〉ことは結び付く場合もあればかけ離れて行くときもある。そして気持ちの葛藤が生まれる。The ManRayのデビューEP『You will be mine』はそんな人間らしさそのものが人間による〈バンド〉の音で鳴っている。だからこそスマートにもいびつにもなる。美しくも泥臭くもある。まさにポップの原石のような作品は、目まぐるしいスピードで、世界に向けてさまざまな音楽がうごめく、群雄割拠の東京シーンのどこを転がって誰のもとに届き、どんな風に磨かれ輝くのだろうか? The ManRayとあなたのロックンロール物語が今ここに幕を開ける。
ルー・リードがNYのことを歌うようなイメージで、自分から見た東京を歌う
――Takuroさん、Ryujiさん、Morrisさんは沖縄出身の同い年だそうですね。地元にいた頃からの仲間ですか?
Ryuji Ooshiro(ドラムス)「そうです」
――当時からバンドをやられていたんですか?
Ryuji「この3人を中心にして、GOING STEADYやHi-STANDARDのコピー・バンドをやっていました」
Takuro Asato(ヴォーカル/ギター)「ちょっと恥ずかしいんですけどね。コピーしていたバンドがどうとか、そういう失礼な話ではなくて、当時の自分たちを思い出すとむず痒いというか」
――青春時代を掘り起こすとそういうことはよくありますよね。上京のタイミングは同じ?
Morris(シンセサイザー)「僕とTakuroは同じです。大学に進学するタイミングで」
Ryuji「僕は2人より後に、音楽の専門学校に通うために上京しました。それからしばらくして〈またバンドやろうよ〉という話になって結成されたのがThe ManRayですね」
――Koさんはどのタイミングでメンバーの皆さんと出会ったんですか?
Ko Koga(ベース)「僕はTakuroとMorrisと同じ大学で、卒業してからも仲が良くて。その流れでThe ManRayに入ることになりました」
――それが2014年ですね。現在は主にどういった場所で活動しているんでしょう?
Ryuji「渋谷、下北沢、新宿のライヴハウスが中心ですね」
――The ManRayも参加されたコンピ『Block Party at shimokitazawaTHREE』をKiliKiliVillaと共同でリリースした下北沢のライヴハウス、THREE周辺など、最近は東京のインディペンデントなバンドのコミュニティーが新たなざわつきを見せている印象もありますが、仲の良いバンドなどはいますか?
Ko「今日ここには来られなかったTenshiro(ギター)が所属しているJappersとは僕らも仲良くしています」
――今回『You will be mine』をリリースするレーベル〈MM〉のオーナーともライヴハウスで知り合ったんですか?
Ko「当時YouTubeにアップしていた音源を聴いて、ライヴに来てくれたのがきっかけです」
――『You will be mine』は一本筋の通ったポップとしても響く作品ではありますが、ロックにポップス、ブルーズやジャズ、ファンク、さまざまな音楽を組み合わせるセンスがかなり独特だと感じました。〈変わった人がやってるなこれ〉って。
Takuro「自分でも聴いててわけわかんねえなって思いますよ(笑)。でも、ミニマル・ミュージックやエレクトロとかあまりフレーズを動かさずに反復する音楽の気持ち良さと、バンドの生々しさがごった煮になっている感じは、狙ったというより〈出ちゃった〉という感覚なんです。それを良いと思ってもらえたら嬉しいんですけど、もっとちゃんとコントロールしてわかりやすくやれたらとも思っています」
――〈わかりやすさ〉とはどういうことですか?
Takuro「もうちょっと客観的に抜き差しができて、ストーリー性を持たせられたらおもしろいんじゃないかと」
――そうなんですね。でも、作曲に関しては研究を重ねたうえでやられているイメージでした。
Takuro「(作曲は)僕がDTMで作ったデモをバンドに持って行って再構築していく形ですね。だから同じパターンを何回も聴きますし、どの曲にも教科書的なものがあるので、そう感じられたんだと思います」
――例えば“Life Goes On”は3拍子が入ってきますよね。曲の質感も合わせてビートルズや60年代のソフト・ロックなどを突き詰めたのだと思いました。
Takuro「あれはまさにビートルズですね。ベース・ラインもポール・マッカートニーが弾くフレーズをいろいろ聴いて作ったんですが、そのポップなリズムにシンプルなコードを乗せて、でもちょっと変なこともやりたいと思って出来た曲です」
――なるほど。Takuroさんの音楽的なルーツも遡って訊かせてもらえますか?
Takuro「初めて買ったCDはBoAの“VALENTI”なんです。〈タイトなジーンズにねじ込む〉ってやつ(笑)。当時は中学生でとにかく新しい音楽を探すことが好きで、それがなぜBoAだったのかは謎なんですけど。高校生になるとグリーン・デイやブリンク182とかメロディック・パンク以降のポップ・パンクと言われる音楽を聴くようになりました。リズムにおもしろさを感じるようになったきっかけはレッド・ホット・チリ・ペッパーズでしたね」
――そこから10年ほど経って、今はどんな音楽が制作の影響源になっていますか?
Takuro「最近はデヴィッド・ボウイやエコー&ザ・バニーメンとか、ジャカジャカ鳴らすというよりは、静かな余韻が楽しめてメロディーの世界観がしっかりした音楽が好きですね」
――なんとなくわかる気がします。Takuroさんが書く歌詞やメロディーってロマンティックですし、詩人的な雰囲気もあって。
Takuro「本は大好きなんです。フランスのロマンティックな文学だったり、片やアメリカ文学だとぶっ飛んでいるのが好きだったり。そういう部分は作品に表れていると思います」

――タイトル曲の“You Will Be Mine”はそうしたTakuroさんっぽさが出てますよね。頭からブルージーなリフ主体で持っていく軸と、ロマンティックな歌&コード感が同時に進行していて。ちゃんと成立してるんだけど、それを組み合わせようとしたプロセスを考えると〈この人の頭の中はどうなってるんだろう?〉と思いました。
Takuro「自分でもちょっとまずいなって思いました(笑)。ミックスの時にデカいスピーカーで集中して聴いていると、ポリリズムじゃないですけど、違う線上で各々が繰り返しやっていることが並行して進みつつ、サビにくるとファンキーでメロディアスにまとまってくる感じに、〈俺は何をやっているんだろう〉って」
Ryuji「ちょっと精神面が心配に」
Takuro「でも精神が侵されているような状態というのはこの曲のテーマではあったので、ピースがはまった感覚もあったんですよね」
――この曲の歌詞はさまざまな受け取り方ができると思いますが、どういうイメージなんですか?
Takuro「ルー・リードがNYのことを歌うようなイメージで、僕から見た東京のことを歌っています。街の凶暴性というか、(人と人との間には)いろいろあるけど結局そんなこと気にもしないで街は動いていくじゃないですか。人が多く集まるとそういう機械的な動きがより大きく見えちゃう」
――私は最近東京に引っ越してきたんですが、今まさにそれを目の当たりにしています。多くの人々が何かを求めてうごめいていることに良い刺激を感じることあれば、落ち込んだときにはよくドラマなどで観たような〈顔のない人たちとすれ違っている〉感覚になることもあって。自分も誰かからはそう見えてるんだろうなと思うと、いたたまれない気持ちになったりします。
Morris「ありますよね」

――キーボードのMorrisさんが聴いてきた音楽についても訊かせてもらえますか?
Morris「意識して音楽を聴くようになったのは遅いんです。高校時代はなんとなく有名な曲を聴く程度で、ボブ・マーリーの“One Love”や2000年代のクラブで鳴っていたようなチャラいR&Bとか、バラバラでしたね。20歳くらいで周りにいろんな音楽を教えてもらって聴くようになって、やっと自分が本当にどんなサウンドが好きなのかわかってきた感じです。マーヴィン・ゲイやカーティス・メイフィールド、レイ・チャールズとか、オールドなソウルやR&Bをよく聴いていますが、最近いちばんぐっときたのはキューバのシンガー、ダイメ・アロセナ。ライヴを観て、〈命〉と言うべきエネルギーを感じました」
――そういったR&Bやソウル、ラテン・ジャズの生命力や開放感から感じたことが、ご自身の弾く鍵盤に活かされている部分はありますか?
Morris「そうですね。聴き手にもそういった繋がりを感じてもらえるようになりたいです」