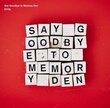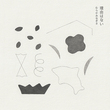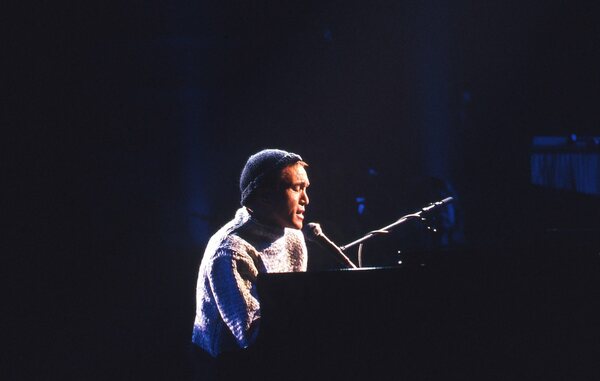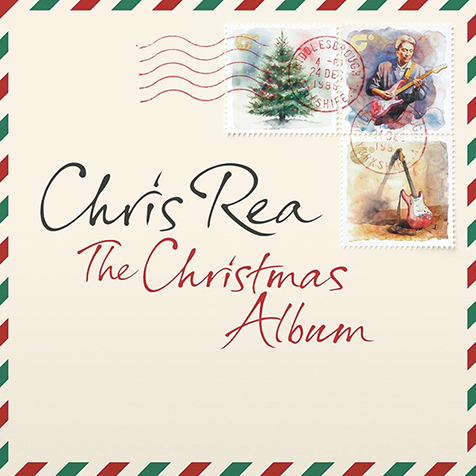悲しみと喜びを併せ持つ二面性がウィリアム・ブレイクの詩集と結びついた
――『Songs of Innocence & Experience』は、ウィリアム・ブレイクの1794年の詩集「無垢と経験の歌(Songs Of Innocence And Of Experience)」に影響を受けていると聞きました。
秋山「僕は大学でイギリスの詩を専攻していて、その時期に『無垢と経験の歌』を知り、綺麗なタイトルだなと感じたのを覚えています。その頃は、いまほど自分にとって重要な存在になるとは思っておらず、今作のレコーディング中もこの詩集のことは特に考えていませんでした。前作のタイトルは収録曲の歌詞から引用したので、今回は違う形でタイトルをつけたいと思い、すべての作業が完了するまでタイトルを決めなかったんです。『無垢と経験の歌』を思い出したのは、制作が落ちつきタイトルを考えているときでした。そのときあらためて読み直してみて、今作との関連性が多いことに気づいたんです。
前作ではいろんなタイプの感情をあえてポジティヴに落とし込んだ気がしますが、今回は自分のなかで感じている矛盾や怒り、悲しみなどをよりそのままの形で表現したいと考えていました。とはいえ今作のなかにも悲しみや怒りなどのネガティヴとされる感情だけでなく、もちろん喜びや愛などのポジティヴな感情もある。そうした二面性と、ブレイクが二つの作品を一つにまとめて出版した『無垢と経験の歌』にある多義性との間に、繋がりを感じたんです。今作のタイトルは、僕なりにブレイクのオリジナルに対するリスペクトを込め、2回目の〈of〉を抜いて『Songs of Innocence & Experience』に決めました」

――ブレイクはイギリスのバンドにも影響を与えています。リバティーンズのピート・ドハーティーが愛読していたのは有名ですし、ブロック・パーティーのケリー・オケレケは“The Love Within”の影響源にブレイクの「Songs Of Innocence」を挙げています。もしかして、これらのバンドがブレイクに触れるきっかけでもありますか?
秋山「それは知りませんでした! どちらも好きなバンドなので、そのことを知れて嬉しいです。どちらかといえば、今回はU2の『Songs Of Innocence』(2014年)からの影響かと訊かれることが多いです(笑)。ブレイクを知ったのは大学での講義がきっかけで、特にその講師だったポール・ハラー先生の存在は僕にとっては大きいですね。もともと僕は詩そのものに興味はなかったんですが、彼の講義を通して詩の魅力や、詩人としての生き方に惹かれていくようになりました。ハラー先生は(スコットランドの)エディンバラ出身で、80年代には現地の音楽シーンでも活動していたそうです。その後はNMEで働くなど、音楽と関わりあいながら生きてきた人なので、今作用に書いた詩にも意見をもらいました。音楽的にも言葉的にも、信頼できる数少ない僕の友人であり先生です」
今回はスタジオでいろいろな実験をできた
――『Songs of Innocence & Experience』のプロデュースは、テスト・アイシクルズのメンバーだったローリー・アットウェルですよね。彼とはどのようにして出会ったのでしょうか?
秋山「プロデューサーやエンジニアを考えるときは、まず自分たちの好きな作品を録っている人たちをリストアップします。そのうえで、リストに入れた人の他作品や活動場所など諸々を考慮しながら、声をかけていくというやり方です。〈ローリー・アットウェルはどうかな?〉と言いはじめたのは、確か加地くんでしたね」
加地「シングルの『Bad Kicks/Hard To Love」(2018年)をレコーディングするとき、僕らから声をかける形で会いました。ギターを格好良く録ってくれる人がいいなと思っていて、一時期聴いていたキッド・ウェイヴというバンドのギターの音を思い出し、そのバンドをプロデュースしたことがあるローリーはどうかな?と提案しました。そこから彼が関わった作品を遡って、ヴェロニカ・フォールズやチャイルドフッドなど、自分たちが聴いてきたバンドと仕事をしていることにもシンパシーを感じて、お願いしました」
――前作のプロデュースはストロークスのメンバーとしても知られるアルバート・ハモンドJr.でした。プロデューサーとしてのアルバートは、シンプルさを大事にする人だと思いますが、ローリーはどのようなタイプですか?
下中「アルバートは曲のコンポジションにフォーカスし、曲の構成自体に仕掛けを作ることに重きを置いていたように思います。ヴァース、プレ・コーラス、コーラスなど曲のパートを並び替え、その曲のそれぞれのパートが機能するようにしてから、シンプルな古き良き音像をいまの技術で作っていく作業を一緒にしたのが印象的でした。
ローリーとの仕事は、もっとプロダクションに目を向けるやり方だったと思います。前回のレコーディングは9日間で10曲以上を録ったので、実験的要素はあまりなかった。でも、今回のレコーディングでは、ローリーと一緒にシンセサイザーをいじったり、ギターのノイズを出したりと、〈とりあえずやってみよう〉という試みが多かったのが非常に楽しかったです。ローリーが選んだスタジオは、パーカッションから鍵盤、エコー、エフェクト・ペダルなどの機材も豊富だったので、とてもワクワクしながら作業ができました。そこの部分の満足度は高かったですね。
そういえば一度、ローリーが体調を崩したときに、ステレオラブでドラムを叩いているアンディ・ラムセイが代打でエンジニアをしてくれたんです。レコーディングをしていたスタジオのオーナーがアンディだったので。彼はビートの違和感のあるところや、それぞれの楽器のアンサンブルを直してくれました。ローリーとはまた違ったアプローチだったので、それもいい経験になりました」