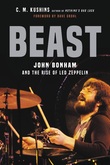全国公開中のドキュメンタリー映画「レッド・ツェッペリン:ビカミング」。公開7日間で興行収入が1億円を突破、洋画ランキング1位に輝き、売り切れ続出のパンフレットは増刷が決定するなど大きな成功を収めている。そんな同作が焦点を絞っているのが、バンドの前史と1stアルバム『Led Zeppelin』(1969年)および2ndアルバム『Led Zeppelin II』の時代だ。そこで今回はバンド初期のアルバム2枚をレビュー。まずは初作の記事をお届けしよう。 *Mikiki編集部
ジミー・ペイジが貫いた音楽・芸術至上主義
「レッド・ツェッペリン:ビカミング」はもう見ただろうか? 映画では、タイトルどおりレッド・ツェッペリンに〈なっていく〉過程が丁寧に描かれている。そしてあの4人が集まった時点で〈勝ち確〉だったことは、顔合わせ代わりの初セッションでの手応えを語った言葉からもわかるとおりだ。
ビートルズのように地元の仲間たちで集まったわけではない。ジミー・ペイジの青い野心や自身の人生を切り拓いていこうという若い意志を軸にして、彼らは引き寄せられた。そして、その〈最強の4人〉が揃った充実感や剥き出しの野望と冒険心が荒々しく、そして生々しく刻まれているのが、この1stアルバム『Led Zeppelin』である。
映画にあったようにジミー・ペイジはアメリカのアトランティックとの契約を勝ち取り、レコード会社に介入させない、有無を言わせない作品至上主義を貫いた。アトランティックのスタッフをスタジオから締め出し、音楽的・芸術的追求を第一義にしたのだ。さらにコマーシャリズムへの迎合を拒否し、シングルカットを禁じたものの、本作はそもそもシングルに不向きな曲が多すぎる(“Babe I’m Gonna Leave You”“You Shook Me”“Dazed And Confused”は6分超え、クローザーの“How Many More Times”に至っては8分27秒もある)。そういった態度は現代的な感覚でもかなり異例で、新人にしてはあまりに不遜かつ挑戦的だが、そのようなジミー・ペイジの頑なさがあったからこそレッド・ツェッペリンは純粋さを保ったままデビューできたと言える。
アルバムへのこだわりが一貫しているからこそ、本作は構成が見事だ。“Good Times Bad Times”は2分台の短い曲で、作品のオープナーとして、そしてバンドが名乗りを上げる口上として完璧に機能している。〈ジャッジャッ〉というシンプルなギターリフの反復と隙間を活かしたイントロの演奏は、ジョン・ボーナムの力強いフィルインとロバート・プラントの代替不可能な歌のための余白を用意しているかのよう。両者が入ってくる瞬間は、まるで〈主役登場〉といった様子だ。ボンゾのバスドラムの連打、ジミー・ペイジのリフや激しいソロ、ジョン・ポール・ジョーンズの饒舌にうねるベース……。ZEPの魅力、アクが強い4人の個性がこれでもかと詰まっている。ロックにおける〈疾走感〉を定義したと言ってもいい“Communication Breakdown”はもはやスタンダードナンバーになっているが、これも“Good Times Bad Times”のような名刺代わりの曲になっており、パンクやメタルの原型としての先駆性すら備えている。