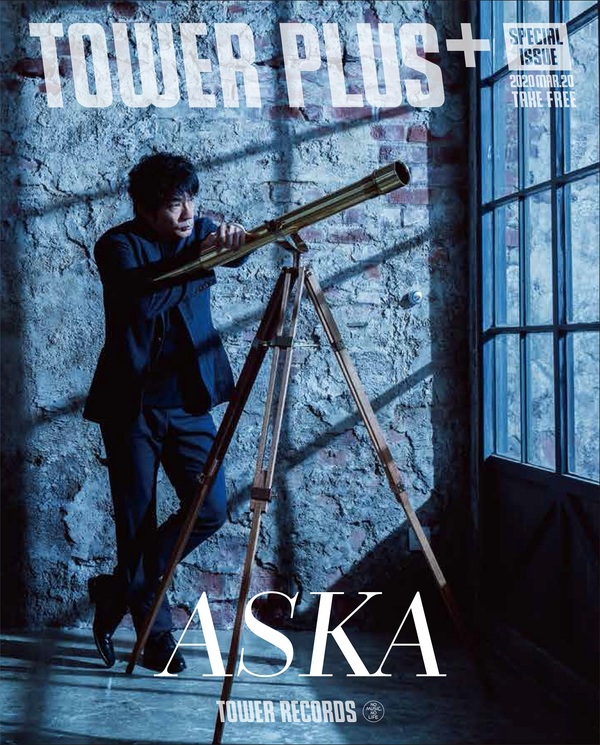作ったものはちゃんと聞いてもらいたい。だから、それに値する楽曲をしっかり作っていく
西寺「自分の理想は、CHAGE and ASKAのように純粋に自分の音楽を追求しながら、光GENJIのようなアイドルをプロデュースして老若男女に届けるというか、その二つの動きをパラレルに進めることで」
ASKA「1989年の終わりにイギリスのロンドンに生活の拠点を移してね。戻ってきてから、もう一度向こうで生活したので、合計1年間ノースセントラルのフィンチェリーに住んでいたんだけど、向こうのミュージシャンに対しては日本の業界も含めて、外タレっていう表現の中で委縮するんだよ。僕もそうだった。外タレが日本に来れば武道館だし、来ればライブ会場は満杯だし、やっぱり特別感があるよね。自分たちとはクラスが違う人だと、階級が違う人だと、そんな意識間の中で僕らは育ってきた。それはコンプレックスだよね。でもあるときからロンドンに住むことになって向こうで生活しているうちに、どんどん環境になじむわけでしょ? 向こうのレコーディングスタジオに入るわけでしょ? 隣ではジョージ・マイケルがレコーディングしていたりして……」
西寺「ジョージ・マイケルの大ファンなんですよ(笑)! 時期的に言えば、ジョージ・マイケルはそのとき、『リッスン・ ウィズアウト・プレジュディス』(90)というアルバムを作っていたはずですね。ASKAさんがイギリスに行かれたのは1989年、日本は平成になり、中国では6月に天安門事件があったり、直前の秋にはベルリンの壁崩壊もあったり、一番激動ですよね。イギリスで経験したことは、その後のアルバムにも絶対影響は出ていますよね?」
ASKA「洋楽とか邦楽とかの間仕切りがまったくなくなったよね。だから最近、自分のキャリアとか色々なことを認められるようになってやっと言葉に出せるようになったんだけど、〈やっぱり音楽はワールドワイドでないといけない〉と思っていて。日本という島国の中で、日本は人口が多いからミュージシャンとして成り立っていける人も多かっただろうけど、芸術性なんていう言葉は堅苦しいから使わないけど、でも音楽はやっぱり〈作った作品〉だから、この作品をなぜ日本国内だけのものに、さっきの殻の話と一緒だよね、なぜ殻の中に入れてしまうんだと。自分が作る楽曲は日本以外の国のことも気にしながら作っているよね」
西寺「CHAGE and ASKAの作品は中国でもめちゃくちゃ人気ありますもんね。”万里の河”などもいまの視点で聴くと、オリエンタルでワールドワイドな魅力を持っていて。”ひとり咲き”(79)もイーグルスの”ホテル・カリフォルニア”(76)をアジア人、日本人として再解釈している気もしますし。デビュー時から、ASKAさんが狭い基準で作品を作ってないってことは伝わってきます」
ASKA「音楽は無国籍でありたいと思っているから、そこはすごく考えているよね。でもいまは、若い人たちの音楽も一つの文化が出来上がっていて、聴いてみるとなるほどなというメロディをみんな持っているよね。でもその中で、なるほどなとは思うし、テクニックもあり歌詞もすごくいいんだけど、やっぱり日本なんだよね。作品を作るときに自分たちで知らないうちに枠を作っているのかなと感じていて。これは何度かメディアで話しているんだけど、映画「未知との遭遇」のラストで、結局宇宙人とのコンタクト方法は音階だったりして。それを意識すると、音楽は最大のコンタクト手段。その音楽で言葉の通じない人とコンタクトを取ることを考えたら、音楽はなんでもできるんだよね。人の心を繋ぐこともできるし、動かすこともできる。でも、音楽によって敵対はしない。音楽は繋がり合えて分かり合えるものだから、そういう意味では、音楽をやれたことでいまの自分がいる。それは幸せなことだなと感じているよね」
西寺「『Breath of Bless』の中に“We Love Music”という曲もありますもんね」
ASKA「これは別に音楽に特化した話じゃないんだけど、すべてにおいて〈気を込める〉ってすごく大事なことだと感じていて。ここ数年、いや、数年というと浅いな、もう少し前から気付いているんだけど、言葉であったり音であったり声であったりというのは、ひとつの伝達手段であって、もっとそれを超えるものは〈気〉で、その〈気〉を歌に込められて、まさに込めたものがステージ上でどれだけ再現できるかどうかで、残る人残らない人の振り分けができるよね。これはね、ステージングがうまいどうこうのレベルではなくて、いま自分がどれだけのことを感じて分かっていて、それを分かっている自分にステージで到達できるか、それ以上のものができるか、それって〈気〉だから。それこそテクニックだったら、誰が叩いても誰が弾いても一緒、上手な人はいっぱいいるからね。だからここにきての決めの一発の〈気〉が大事。そこで伝わるものは大きいはずだと思っているんだ」
西寺「僕は今回のアルバムを聴いて、先ほどASKAさんが仰られた数学という部分を感じて。〈気〉と、さっき仰っていた〈数学〉的な計算、相反するように思えるその両面から答えを探す冷静さが、すごいなと」
ASKA「そうだね。〈込めるもの〉がしっかりできていないと、作品が作品として届いていかないから。さっきの話で、どちらかというと音にこだわると言ったけど、でもやっぱり最後には詞だよね。歌詞って何気に聞いている中で聞き逃すことがほとんどでしょ。車に乗っていても何するにしても、聞こえてくるのはメロディだよ。歌詞は大きくないからさ。でも、そこに自分で言葉を繋げて、これくらいでいいだろうと思ったものはこれくらいしか届かない。だからしっかり書いて自分の中で満足できたものは、どこかで何かに触れるから。そこは大切にしようと思っている」
西寺「詞の書き直しはされるんですか?」
ASKA「もちろんするよ。でも昔は1週間、10日、長いときは1か月かかっていた詞が、ここ4~5年は4時間以上を超えてないよね」
西寺「集中されているんですね」
ASKA「自分の中で色々なことがあったから、どこかを一周して原点に帰ってきたような気持ちにもなるんだけど、すごく言葉を選ぶスピードが早くなったかな」
西寺「僕は『Breath of Bless』 を聴かせていただいて、すごく自然というかナチュラルに聴こえたんです。今回の曲数の多さもそうですけど、ここ5~6年のディスコグラフィーを見ても、ベストがあるにしてもめちゃくちゃリリースされているじゃないですか。ASKAさんは、いまちょうど整ってきたというか、やりたいことがすーっと素直にできる状況なのかな、とも思ったりして。技術の進歩もあると思うんですけど、ASKAさんのやりたいことと、世の中がようやくこう……。もちろん合っているときもあったと思うんですけど、めちゃくちゃ合っていたからあれだけヒット曲が出たんだと思うんですけど、またそれとは違う意味で、ASKAさんの作りたい作品が素直に届いているということを、このアルバムを聴いてすごく感じました」
ASKA「僕たちはプロだからね。ポップスであろうが、ファンクであろうがロックであろうが、ブルースであろうが、カントリーでもいいけど、作っておいていくら自分が満足して語ったところで、相手が受け付けられなかったら聴き流してしまうだけでしょ。それは寂しいよね。やっぱり作ったものはちゃんと聴いてもらいたい。だから、それに値する楽曲をしっかり作っていかなきゃ。プロなんだから」
西寺「そう言えば、色々まだ聞きたいこともありました。昔テレビで見たんですけど、ASKAさんはポール・マッカートニーと対談されていましたよね」
ASKA「実はポールと会う前、89年にロンドンに行ったときに、娘のステラ・マッカートニーと先に知り合っているんだよ。そしてポールが日本に来たときにホテルのファミリーパーティーに呼ばれて、そこでポールに家族を紹介されて、そこでステラが出てきてね。初めましてみたいな会話から、いや実は前に会ったことがあるんだよ、ロンドンで会った日本人だよって言ったら、ステラが思い出してくれて。そうしたらポールが、なんだ知り合いだったのかって、そんなやり取りがあってね。そして、そこで会ったポールのバンドメンバーが、僕が後に実験アルバムのレコーディングでロンドンに行ったときに、偶然にもスタジオに呼んだメンバーだらけで。また彼らに、あのときの日本人だよって言ったりして。ポール・マッカートニーほど、ポップやロックの中にあれほどのアカデミックさを持ち込んだ人はいないよね。ジョン・レノンは、存在感と、カリスマ性、声のよさ、もちろんメロディもいい、ジョンはロック寄りのかっこよさだよね。ポールのかっこよさはロック寄りなところもありながらもメロディアスでクラシカルなところ」
西寺「そうかも知れないですね」
ASKA「楽典的にはポール・マッカートニーなんだけど、やっぱり、ポールとジョンの二人が合わさったときのビートルズの魅力は素晴らしいものがあるよね」
西寺「いやー、でも僕が好きなアーティストたちの〈第一次情報〉と言いますか、直接のエピソードがどんどん出てくることに本当に感動しています。ただ、確かにアメリカやイギリスのスーパースターだからと言って萎縮することはなくて。当時の音楽市場の規模でいっても、日本というマーケットは大きかったですから」
ASKA「世界第2位だよね」
西寺「そうですよね。プリンスやマイケル・ジャクソン、ポールもそうですけど、そういうアーティストと実際にCHAGE and ASKAが肩を並べていたというのは、ピリッとするだろうし、負けてはいけないと思うだろうし。ASKAさんがイギリスから日本に戻って、普通の気持ちでいられるわけありませんよね。彼らと戦わなきゃいけない、というか……」
ASKA「負けてはいけないというよりも、戦うというよりも、楽曲に関しては作るうえではなんの遜色もないよ」
西寺「今回、ASKAさんとお話しできたことで、大きな刺激をいただきました」
ASKA「時代が自己発信できる時代だからね、色々なところで使われちゃいけない気持ちが大きくて、色々なものを使わなければ、使う側にならなければ、まずはそれを考えるよね。使われるときには自分から愛情をもって使われたい、使われにいきたいと思う。それ以外の部分は、自分が使っていかないと。これから日本の音楽はますますインディペンデントしていくだろうね」