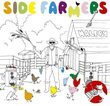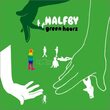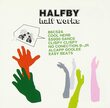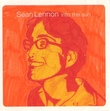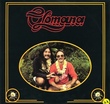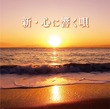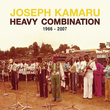メン・アイ・トラストを経た〈ネオアコ〉再発見
――『Loco』のサウンド面での方向性を定めていくうえで、何かリファレンスはあったんですか?
「僕の家は八幡という京都の南のほうの田舎なんですが、生活するうえで車での移動が欠かせないので、車中でよく音楽を聴いているんですよ。僕の場合、家で聴いたレコードより、車のなかで聴いた音楽のほうが印象深く残っている。運転と音楽を聴くことは相性がいいんですよね。
このアルバムに取り掛かった頃は、ちょうどメン・アイ・トラストの『Oncle Jazz』(2019年)――フランス語で〈叔父さんのジャズ〉というタイトルのアルバムをずーっと聴いていて。あのアルバムは、メロウな曲や暗い曲が中心で、かつ24曲も収録されているんですが、いわゆるジングルっぽいものや、タイトルコールなんかも上手く構成に組み込んであって、めちゃくちゃバランスがいいんです。何周もリピートして聴けるんですよ。
それがすごく快適だったから、〈歌もののアルバムを作りたい〉という単純な気持ちが芽生えてきた。『INNN HAWAII』と『LAST ALOHA』は情報量を削ってインスト中心にすることで、リスニング向けに徹したつもりだったんですが、メン・アイ・トラストの『Oncle Jazz』は歌ものが中心にもかかわらず、それをやってのけた作品だと感じたんです」
――メン・アイ・トラストが『Loco』に影響を与えたとは思いもしませんでした。
「彼らのライブを観に行ったんですけど、シンプルな演奏のなかにドリームポップと形容されるようなインディーの要素がありつつ、ジャズをベースに持っていることも見え隠れして。それがメロウにまとまっていることも、すごく好みでした。
それからCDやレコード、カセットテープにTシャツまで買い揃えて、すっかりファンの気持ちで盛り上がったことが、新作の制作に影響したのかもしれません。ちなみにメン・アイ・トラストを知ったのも、小山田くんが〈息子に教えてもらって〉と雑誌のインタビューか何かで紹介していたのがきっかけです」
――ここでも小山田圭吾の影響が。
「メン・アイ・トラストは、アレンジの面ではエレピが入っていたりスラップベースが多用されていたり、そこはかとなくファンクマナーではあるんだけど、佇まいやアートワークを含めて絶妙にインディーポップしているんですよね。もともとインストのダンスミュージックを作る男性デュオだったのが、女性ボーカルのエマニュエル(・プル―)が加入したことでスタイルが少し変わり、ポップミュージック面での引き出しが輝きはじめた。その過程も含めて好感度が高かったし、彼らの音楽的なバランスも、ひとつアイデアのもとにはなったかな。〈こういう音楽がやっぱり自分は好きなんだな〉と再確認できたし。そこから〈ネオアコ〉というキーワードもより強くなってきました」
〈間〉って感覚がHALFBYの強み
――なるほど、ネオアコですか。アルバムのなかでもマニラ出身のボーカリスト、Ruruをフィーチャーした“Calm As Day”、“I’ll Remember you”はネオアコ~ラウンジ感が強いですよね。
「Ruruは、NaohirockさんのDJミックスに収録されていて知ったんです。〈この人の声、ちょうどいいな〉と思って、Bandcampを経由して連絡してみたら、すぐ返信がきて。〈私はプロだから、ちゃんとお金いるよ〉なんて書いてあって、より歌ってもらいたくなりました(笑)」
――かっこいいですね(笑)。
「そのあと、歌メロを入れたデモを送ったら、すぐに歌を入れて返してくれたんですが、僕の入れていたメロディーとはまったく違うメロディーで(笑)」
――(笑)。
「そこが外国人的というか、ワクワクさせるなーと思いました。でも、彼女が入れてくれた歌メロも歌詞も良かったから、もちろんそのまま採用して。
彼女はマニラに住んでたんですが、この間〈サンプルCDを送るから住所を教えて〉と連絡したら、住所がカナダになっていました。ついこの間引っ越したみたいです。メン・アイ・トラストもカナダ出身ということで、その点でもシンパシーを感じたし、北米でもぜひ人気が出てほしいですね」
――高橋さんはRuruのどんなところに歌い手として魅力を感じていますか?
「うーん……単純にコケティッシュさ(笑)? 例えばアフリカ系アメリカ人のファンキーな声質とは違う魅力があって。そういうのも自分のインディー感においてはすごく重要なんです。僕、ただ歌が上手い人ってずっとは聴いていられないんですよ。あと日本人だとこのムードは絶対に出せないですよね。
Ruruに歌ってもらった”Calm As Day”の配信シングル用のジャケットはサラ(Sarah) の7インチのアートワークへのオマージュなんですけど、曲自体もサラに在籍したオーストラリアのバンド、イーヴン・アズ・ウィー・スピークにメン・アイ・トラスト、それからノーネームの〈間〉を意識したんです。この〈間〉って感覚がHALFBYの強みだと思っていて、それを作るためにRuruのボーカルが必要だった。
それから、これは後付けだけど、ソサイエティ・オブ・セヴンっていうフィリピン出身の大御所グループがいて、60年代にハワイに渡ったあと、ホテルのショーなんかを通して大成功したんです。彼らの存在もあって、フィリピン出身のRuruにハワイの曲を歌ってもらうのはいいなって」
ハワイのミックスカルチャーはコンピレーションにこそ反映されている
――ちなみにインディーポップ/ネオアコ的な音楽はハワイでも盛んなんですか?
「70年代のハワイでは、カラパナ以降という感じで、オーセンティックなハワイアンやフォーク/カントリーミュージックに、欧米のロックやソウル、ジャズなどからの影響がクロスオーバーしたような新世代のグループがたくさん登場したんです。それが80~90年代になると、ネイティブハワイアンへの原点回帰が始まったり、プリAORというかマッキー・フェアリーの後期のようにコンテンポラリー色を高めていったりして、透明感のある洗練された雰囲気の音楽が増えてきた。
それらは、ネオアコをはじめとするヨーロッパの80年代の音楽と通じる部分を持っているんです。単純にミキシングのトレンドも大きいとは思うんですが、煌めいたピアノの音色だったり、ギターアルペジオのアレンジだったり、ボサノバっぽいリズム感だったり、自分的なネオアコのフィルターに引っかかる要素が入った曲もちょこちょこあって」
――そうなんですね。
「その頃の作品でも、フリーソウルで人気のテンダー・リーフみたいに、アルバム全曲があの方向を向いているのは珍しいんです。本土への憧れを持った作品には、カントリーやフォーク、ネイティブなハワイアンソング、レゲエやボサノバ、それにコンテンポラリーでネオアコ風のロックなどが織り交ざった、一本調子ではないバリエーションに富んでいるものが多い。
僕は、そういう作品にこそハワイのミックスカルチャーを象徴するような雰囲気を感じていて好きなんですけど、日本だとレアグルーヴ的な観点からしか評価されていなくて、そういうのは本当につまらないなと思います。なので、『Loco』の販促用に作った〈Loco ZINE〉では、レアグルーヴっぽいのをあえて外して、大衆的なハワイワンレコードをいろいろと紹介したんです。そちらもぜひ手に取ってほしいと思います。
あと、オアフ島のラジオ局のDJたちが76年にスタートした、日本でも人気のある『Home Grown』というコンピレーションがあるんですけど、それは〈プロアマ関係なく、ハワイのローカルアーティストを紹介する〉というコンセプトを貫いているシリーズなんです。そのハワイならではの〈ホームグロウン〉で〈ミックスカルチャー〉という視点もアルバムのヒントになりました。そこで、僕がDJしたり作曲したり選曲したりする感覚を反映した、コンピ的な要素をアルバムに入れてもいいなと思ったんです」
――なるほど。
「自分のなかでコンピレーションといえば……と連想したときに、elのシリーズ『London Pavilion』(87~89年)が思い浮かんだ。そこで、さらにネオアコという裏テーマに熱が入ったんです。自分のなかでのこじつけではあるんですけど(笑)」