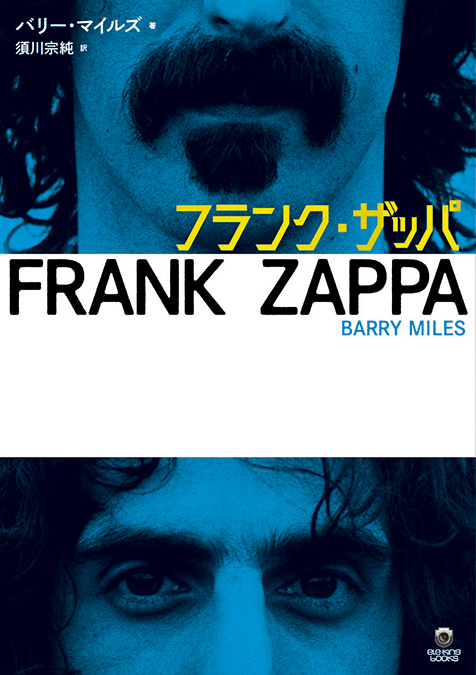これはほんとうのリアル・フランク・ザッパ本だ
2020年に制作された初の遺族公認のドキュメンタリー映画「ZAPPA」(アレックス・ウインター監督)がついに日本公開されたフランク・ザッパ。1966年に『フリーク・アウト!』でデビューして以来、いわゆるポピュラー音楽という業界では異例とされるようなやり方や、ある意味では反時代的でもあるような、自身の信念にもとづく言動、振る舞いによって、これまで一種〈キワモノ〉的な印象を持たれていた(一方で、それゆえの支持者も多くいる)、いわば聴く人を選ぶ、近づきがたい、通好みなミュージシャンでもあった。しかし、本書でも触れられているように、ザッパと仕事をすることは、〈ミュージシャンにとっては花嫁学校に入るようなもの〉と称されるようなミュージシャンであり、ザッパの下で仕事を共にしたことが、ある種の箔付きともなるような、優れたバンドリーダーでもあった。しかし、演奏家の技能の限界が、作曲の可能性を制限してしまう、バンドという共同体の宿命にあきたらず、シンクラヴィアという当時最新のシンセサイザーを導入、あげく、ふつうの演奏家では演奏が極めて困難な楽曲を自動演奏するような楽曲も生み出した。
本書は、数多くのミュージシャンの評伝を手がけたバリー・マイルズによる、フランク・ザッパの本格的な評伝である。これまでのザッパ本は、どちらかといえば、ロック界の変わり者としてのザッパを(たとえそれがさまざまな誤解にもとづいて作り上げられた人物像だとしても)印象付けるものが多かったと思う。しかし、本書に描かれているのは、それが一般的なものと少し考え方が異なるにせよ、あくまでもあらゆる物事を真摯に考えぬく、ある意味、生真面目なミュージシャンの姿である。もちろん、それはミュージシャンという枠にとどまらない、社会にコミットするものでもあった。
自身の音楽が「その音楽が新しいように目的も新しい」と端的にのべているように、ザッパが目指していたものは、たんに奇を衒うようなことではまったくなかった。本書は、ザッパが一体なにを考えていたのかを、ほんとうのザッパを知る好著と言えるだろう。