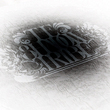ブリアル以降のUKガラージとベーシック・チャンネル以降のダブ・テクノのミックス。一時はベルリンを拠点に活動し、日本内外でリリースを重ねてきたSATOLの作風は、これまでならそんなふうに形容できたかもしれない。しかし、2013年の『harmonize the differing interests』、2014年の『Enhance Cell Survival』を経て完成したフル・アルバム『Shadows』において音のスタイルはガラリと変貌を遂げた。ディープかつストイックな佇まいには前作と相通じるものが見い出せるが、野太いビートはさらに多種に及び、ミュージック・コンクレートのような実験的な音響と叙情的なメロディーが流れ込んだ、非クラブ・ミュージックと言っても差し支えない作品に仕上がっている。今回は、このアルバムに至った経緯を解きほぐす意味でも、音楽活動の出発点からじっくり話を訊いた。

ハードコアが出自ながら、自分だけで黙々と音作りすることに魅力を感じた
――SATOLさんは今回、新作『Shadows』を発表されたわけですが、これまでにもかなりのリリース作品がありますよね。そもそもどういう形で音楽を始めたんですか?
「もともとはバンドをやっていたんですよ。18歳の時にデス・メタルから入って。で、〈これテンポ速すぎるんちゃうか〉ってことでハードコアに移行しました(笑)」
――より速くなった(笑)。
「ストイックにハードコアを追求していましたね。その後にレゲエも好きになってジャマイカへ行ったり。それで(日本に)戻ってきてから少し経ってたので、大阪でクラブ経営を代表者含め4人で始めたんです」
――いま作られているようなエレクトロニック・ミュージックに興味を持ったきっかけは?
「ハードコアやレゲエにどっぷりだった時期に、ハイパーダブが出てきたんですが、そのなかでも特にブリアルに衝撃を受けたんです。こういう抽象的なサウンドがあるんや、これはいけると思って」
――ハイパーダブが展開していたダブステップ以降のクラブ・ミュージックの重低音は、レゲエにも通じるところがありますよね。そのへんが響いたんですか?
「そういうところもあったかもしれないですけど、この音なら一人でできるなと思えたのがいちばんデカかったんです。やっぱりバンドって大変じゃないですか」
――バンドは集団による物作りですもんね。そこが醍醐味でもあり大変でもあり。
「自分だけで黙々と音作りをすればいい、というのがめちゃくちゃ魅力的に感じたんですよね。本当は自分の顔を表に出したり、人前にも出たくない。できるなら音源だけポッと置いて消えちゃいたいと思っている節もあったりして」
――そういう理由から打ち込みの活動に入ったんですね。そこからSATOLさんはベルリンに移住されたと。
「ドイツのキルミニマル――いまはイオアン・ガンボアという名前で活動していて、今回の新作にも参加してもらったアーティストなんですけど、クラブをやっている時に彼をブッキングしたら意気投合して、〈良かったらうちのレーベルから出さないか〉という話をもらったんです。なら、ベルリンで活動しようと」
――でも、移住というと結構な決断じゃないですか?
「当時一緒に暮らしていたドイツ人の友達が、アーティスト・ビザが取れるんちゃうかといろいろ取り計らってくれたんです。そのおかげもあって、上手いこと移住できたんですよね。で、キルミニマルが所属していたレーベル=マッドベルリンにも関わるようになって」
――マッドベルリンからのリリースでSATOLの名が知られるようになります。当時はどういう音をめざしていたんですか?
「最初の『madberlin.com』(2010年)はブリアルやコード9からの影響が強くて、ダブステップと2ステップが混ざったような音をやっていました。ダークステップというかUKガラージというか」
――そういう音楽がどんどん広がりを見せていく時期ですよね。
「そうですね。でも、自分はそこからコロッと変わっちゃったんです。一緒に活動していたキルミニマルにすごい影響を受けてしまって、次の『Radically Nu Breed's Cre8』(2010年)から4つ打ちのテクノのほうに進んでいった」
――ドイツはテクノががっちり根付いている国という印象ですけど、その土地から受けた影響はありました?
「インスパイアされたところはすごくありますね。ただ、それはあまり良くないということにちょっとずつ気付くんですけど」
――というのは?
「ベルリンで活動していることがステイタスになっていたというのは、正直なところあったんです。でも自分はその土地の人間じゃないし、影響を受けすぎるというのは、要は真似になっちゃうじゃないですか。海外の文脈に乗っかっているだけというか。それは個性がないよなと」
――そういう思いがもたげてきたと。
「そうですね。そこから、どう自分らしさを出すかということを深く考えるようになりました」
THA BLUE HERBをリスペクトしつつも聴かないようにしていた
――そして『Superhuman Fortitude』(2011年)を発表された後に日本に戻られます。このタイミングで帰国したのは?
「これはだいぶリアルな話なんですけど、当時、大阪でクラブの摘発が続いたんですよね。自分はもともと大阪のシーンで育ってきたわけだし、地元がそんな状況のなかベルリンにはいられないと思ったんです」
――大阪のシーンはどういう感じなんですか?
「メジャーなオーヴァーグラウンド箱と、音にストイックなアンダーグランド箱、その2つがごちゃごちゃに混ざっていますね。まあ、大概はオーヴァーグラウンドな箱ですけど(笑)、EDMのようなメジャーすぎるものがかかっていることに、逆にプライドを感じるところもあります。そこまでメジャー路線ならすごいわ、みたいな(笑)。自分は出す音こそこんな感じですけど、そういう奴らとも仲良くしてもいました。ヘンな話、ガチなイヴェントより、チャラいイヴェントのほうが物販でCDが売れたりもするんです。そういうことは勉強になったし、大阪らしいなって思いますね」
――そんな大阪に戻ってきて、2013年にアルバム『harmonize the differing interests』をリリースします。
「日本でのファースト・アルバムという位置付けですかね。そこで仕切り直しという気持ちもありつつ、ベルリン時代からの流れで出来た作品でもあります」
――このアルバムは当時、UKガラージ的な紹介をされていましたが、もっと広くいろんな要素を採り込んだエレクトロニック・ミュージックという印象を受けました。
「アンディ・ストットを引き合いに出されたりもしましたけど、自分ではそんな意識もなかったんです。なんなら言われた後にアンディ・ストットについて調べたりしましたし(笑)」
――ビートのない展開があったりするところでアンディ・ストットが想起されたのかもしれないですね。その時はダンス・ミュージックを作ろうという意識はありましたか?
「ないっすね。〈ビーツ〉とか言うじゃないですか、音楽をそういうふうに捉えるのが嫌で。ドラムがあって、ベースがあって、ウワモノ、SE……みたいなダンス・ミュージックのフォーマットがワンパターンに思えた。それで、ビートがないような曲を作りはじめたんです」
――先回りすると、新作『Shadows』はまさに脱ダンス・ミュージック的な作品ですよね。ここに至る変化が当時から表れはじめたわけですね。
「そうですね。海外の音に影響を受けるんじゃなくて、自分なりの音を出そうと考えた結果、とりあえずいまはこうなりました」
――『harmonize the differing interests』から『Enhance Cell Survival』のリリースを経て、THA BLUE HERBのO.N.Oさんが立ち上げたレーベル、STRUCTからアナログを発表します。
「O.N.Oさんはイヴェントで一緒になった時に〈いいね〉と言ってくれて、意気投合したんです。彼がレーベルを作る時に、〈お前は俺から逃げられないから〉って声をかけてくれて(笑)。〈いやいや、逃げる気ないすよ〉と」
――ソウルメイト感のあるお話ですね。もともとTHA BLUE HERBが好きだったそうですけど、そういう意味ではグッとくるものがあったんじゃないですか?
「THA BLUE HERBはアブストラクト的な音が衝撃的でしたし、リリックにもすごい惹かれるものがありましたね。ただ自分も薄情というか……実はライヴも観たことなければCDも買ったことないんです。〈(TBHに)影響受けすぎやん〉みたいな人も多かったじゃないですか。それは違うなと。だからリスペクトしつつも聴かないようにしていました」
――SATOLさんはリスナーとしてガツガツ聴き漁るタイプではない?
「10代の頃は、ひたすらハードコアを買いまくってましたけど、その後はそういうことはなくなりましたね。あくまで個人的な意見ですが、例えば俗に言うアンダーグラウンド・シーンやストリート生まれのジャンルほど、いまの若手に限っては、ほぼそのまま90年代スタイルのバンドが多いと思いました。そうやってグルグル回ってる印象を受けましたね」
――リヴァイヴァルというかリサイクルというか。
「僕はそうだと思いました。細かいところは変わってるけど、基本は同じものが回ってる。そういうシーンの流れに身を任せても、新しいものは作れないんじゃないかと思ってしまって」
――じゃあむしろ、意識的に外の音を遮断していると。
「遮断してますね。自分の曲作りに没頭したいし、自分が持っているイメージに向けて純粋にやっていくだけです」

ダンス・ミュージックの約束事を壊すことしか考えていない
――その後にミニ・アルバム『Enhance Cell Survival』(2014年)があり、そして今回、3年ぶりのフル・アルバム『Shadows』が完成しました。まず本作はPROGRESSIVE FOrMからのリリースになりましたね。
「これは言っていいんかな、と思うような話なんですけど、PROGRESSIVE FOrMに話をするつもりではいましたけど、メールの件名を他のレーベル宛の件名で送信してしまったんです。〈終わった……〉と思ったんですけど、PROGRESSIVE FOrMが音源を好意的に受け留めてくださって、リリースに至ったという」
――なんだかすごい話ですけど(笑)、そんな経緯があったとはとても思えないです。というのも、実験的で現代音楽っぽい要素も感じられる作品で、PROGRESSIVE FOrMのレーベル・カラーに見合ってるなあと感じたので。
「間違えた件名と内容でメール送信した時点でアルバムは概ね出来上がっていたし、そんな(メールを誤送信する)感じですから、特にレーベルを意識して作ったアルバムではないんです。だからこそミラクルだなあと自分でも驚きましたね」
――これまでよりも、ずっとアブストラクトでフリーフォームなサウンドが展開されています。特に前半の曲では明快なビートがほとんど鳴っていないし、ダンス・ミュージック的な縛りがない。
「そこはなくしたかったし、もっとなくしたいです」
――もっとですか。
「もっと、もっと……ですね。そういう考えから始まったアルバムだし、ここからさらに自由になるんやろうなと」
――以前からフィールド・レコーディングの要素はありましたけど、今回はそういった環境音のコラージュというか、ミュージック・コンクレート的な要素が強いですよね。
「最近はライヴでも、サンプリングで蜂がブーンって塊で飛んでる音やハエの飛ぶ音とかをよく使うんです」
――例えば“voyeurism”は女性の声とスクラッチ・ノイズで幕を開けて、そこにドアを開け閉めし続けるような音が入ってくる。
「その曲は特に〈自分(っぽい曲)やな〉と思ってしまいますね。ビートがないんですけど、ビートの部分をベースが埋めてしまった。結果、こういう音になったんです」
――聴いていると、その凄まじい音像と展開に否応なく持っていかれるんですけど、一方で〈これは何なんだ!?〉とも思うわけですよ。こういった実験的なサウンドの後ろには、具体的なストーリーやテーマがあるんですか?
「うーん……ストーリーということで言えば、今回は後半に叙情的な音が入ってくる曲が多いんです。そこに持っていければいいのかなって」
――超シュルレアリスム的なサウンドが突然切り替わって、クラシカルでエレガントなピアノのメロディーが入ってきたりする。その叙情性もアルバムの大きな特色ですよね。
「メロディーとメロディーを重ねていくのが得意なので、そういう部分を押し殺す必要もないなと。抽象的なところから急にメロディアスになるという音楽も他にないし、だったらやってしまおうと思ったんです、さらにBPMも曲中に変わるので」
――それから、繰り返しの構成を拒否している曲が多いですよね。どんどん展開していく。そこもダンス・ミュージック的ではないなあと。
「おっしゃる通りで、もうダンス・ミュージックの約束事を壊すことしか考えていない。さっきから言おうか迷っていたんですけど、本当は雅楽もやりたいくらいなんですよ」
――雅楽ですか!
「自分で笛を吹くんちゃいますよ(笑)。雅楽の音を採り入れたいという、そういうノリです」
――そうやって選び取られる音に基準はあるんでしょうか。
「とにかく攻撃的な音が好きなんです。かつ、ジャンルに回収されないようなもの。例えば〈ギャー〉っていうノイズもアリやと思いますよ。そういうのも好きやし。セミの鳴き声にエフェクト掛けただけでもいいかな、とか」
――実際、ノイズの要素も入ってますよね。それから、SATOLさんの出自であるハードコアの感覚も見い出せるように思いました。サウンドがハードコアというわけではないんですが。
「ハードコアの影響を隠す必要はないなと思いはじめたんですよね。これまではちょっと無理して隠してたんちゃうかなと。ハードコアは自分の精神にずっと残っているし、自分にとってデカイものです」
――テクノのシーンではここ何年かでインダストリアルなサウンドが浮上してきましたけど、そういう潮流に通じるところもあると思ったんです。あるいは、先ほどお話に出てきたアンディ・ストットの近作に繋がるものも見い出せなくはない。そういう外の動きは意識してないですか?
「まったく気にしてないですね。さっきも話しましたけど、とにかく外の音を遮断して、何かを真似しないってことが作品を作る原動力になっているんです。気にしているのは、出会って意気投合した奴らだけ。そういう周りの奴らがイケてると思っているんで」
――身近なコミュニティーだけを信じていると。
「もちろんカッコイイものはカッコイイと認めます。ただ、それは会った時に、と思ってるんです。地方でライヴをやる機会も多いんですけど、そこで出会った人たちとか。どういうわけか、ハードコアの人たちやオリジナリティーのある、ある意味孤立した歌い手と仲良くなっちゃうんですけど」
――SATOLさんのなかでは〈出会い〉が大きなファクターなんですね。
「そこっすね。そもそも人間味のある人が好きなんですよ。サウンド云々よりも会って話さないとわからない。音源だけで〈こいつヤバいな〉と思うのはごく少数で」
海外のモデリングをしない奴らと一緒にシーンを変えていきたい
――アルバムの後半は、楽曲ごとにいろんなアーティストが参加してますが、そういう意味で、彼らはSATOLさんが〈出会った〉面々ということですか。
「まさにそうですね。お世話になっている人ばっかですわ。それぞれに同じトラック(“period of alertness”)を渡して、そこに手を入れてもらいました。だから、いろんなヴァージョンが並んでいるんです。お願いするにあたっても特に注文はせずに、自由にやっていただきました。仕上げてもらったものに、さらに自分が音を加えたりはしてなくて」
――なぜ今回は他のアーティストが参加する形になったんでしょう。
「これまで自分の作品に別のアーティストが参加したり、リミックスしてもらったりというのをほとんどしたことがなくて。やってこなかったからこそ、今回はいろんな人に参加してもらおうかと」
――まず登場するのはO.N.Oさんです。やっぱり、こういう企画であれば参加してもらわないわけにはいかない人ですか。
「そうですね。O.N.Oさんは日本ではすごく有名ですけど、海外ではまだそこまで知られていないのかなというのもあり、これをきっかけに(海外でも)知ってもらえたらという気持ちもありました。僕がこんなことを言うのもおこがましいかもしれないですけど」
――音的に相通じるところもありますか?
「いや、それは思ったことがないですね。彼は本当にテクノだし、ビート職人なので。ただ、一緒にやるのはおもしろいですね。〈BPM145で!〉とお願いすれば、〈速すぎない?〉と言いながらも作ってくれる。そうやってこっちに合わせてくれるんです」
――TAKAAKI ITOHさんはテクノ・シーンのヴェテランですね。
「最初はイヴェントで出会ったんですけど、とても気さくで、やっぱり人間的に好きな人です。上がってきたトラックもシンプルでITOHさんらしくて、すごい良かったですね。テクノが好きな人にはむっちゃ響くと思います。この曲をSoundCloudにアップしたら海外からのリアクションもむっちゃありました」
――ハルプ(HALP)はオランダのプロデューサーなんですね。ロウでざらついたベースが印象的な曲です。
「彼は実際には会ったことがなくて、ネット上で交流しているんですが、アルカに影響を受けてる奴なんですよ。だからか曲が短い(笑)」
――そしてイオアン・ガンボア。最初に名前が出てきた元キルミニマル氏ですね。このアルバムのなかではちょっと毛色の違う、柔らかな音色が印象的なハウスっぽい仕上がりです。
「僕のキャリアにおける分岐点を作ってくれた存在で、曲作りの師匠でもあって、いまだに週に2回はSkypeで喋る間柄ですけど、自分とはスタイルが全然違いますね。〈ザ・テクノ〉って感じで、それでいてミニマルが大嫌い。だから以前は〈キルミニマル〉と名乗っていたんですけど(笑)。そんなやからベルリンでも威風堂々としてるんでしょうね」
――今回のアルバムはSATOLさんにとってどういう作品になりましたか?
「自分らしい、良いものが出来たと思います。聴いてみてどうでした?」
――〈何これ!〉っていう訳のわからなさと、2016年に響くいまっぽさと両方が合ってるんですよね。そこがすごくおもしろい。
「そう言ってもらえるのはありがたいですね」
――なんらかのフォーマットに縛られない、独自のスタイルをめざした作品ですよね。これまでの作品とはがらりとスタイルが変わりましたけど、この方向性がSATOLさんのベースになるのかなと。
「そうですね。O.N.Oさんとか尊敬できる先輩方は、何かの模倣じゃないオリジナルな音を追求してきたはずだし、自分もそうありたい。僕だけでなく、周りにいる海外のモデリングをしない奴らと一緒にシーンを変えていきたいと思ってます。ツアーも12月まで続くので、現場でいろんな人に会いたいですね!」