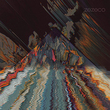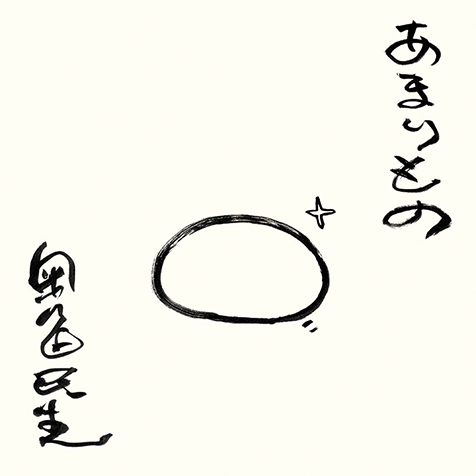変拍子を駆使しながら 〈静〉と〈動〉を行き来するバンド・アンサンブル、ミニマルかつサイケデリックなサウンド・プロダクション、ライヴにおけるアブストラクトな映像や歌詞の持つ独特な世界観によって、日本のポスト・ロック・シーンを牽引しながらも常に孤高の存在であり続けるdownyが、約3年ぶりの新作となる第六作品集『無題』をリリースした。2004年の活動休止から実に9年という長い空白期間を経て発表した2013年の前作〈第五作品集〉は、青木ロビンのヴォーカルをフィーチャーし、エレクトロニクスを大々的に採り入れるなど、それ以前の作品と比べるとかなり趣の異なるものだった。ところが今回の新作は、歌モノとしての楽曲構造やサウンド・テクスチャーは前作の延長線上にありながらも、初期の彼らが持っていた肉食動物のように獰猛なグルーヴや、研ぎ澄まされた刃物のように鋭利なサウンドを取り戻している。
これまでdownyはあえて自分たちに厳しいルールを設け、そのなかで表現を追求することで〈downyらしさ〉をストイックに守り続けてきた。活動再開以降、そうしたルールを取っ払いながら作品を作り続けてきた彼らが、それでも失うことのなかった〈downyらしさ〉とは、いったい何だったのだろうか。活動休止と同時に、家族を連れて沖縄へ移動し、東京との間を行き来しながらふたたび音楽を奏でることを決意した青木ロビンに話を訊いた。
マグマの如きエモーションを氷で閉じ込めたような音楽を作りたかった
――前作がリリースされてからの3年間は、どんなふうに過ごしていました?
「わりとやることが多かったんですよね。ライヴはもちろんありましたし、曲作りも1年ちょっと前から始まっていたので。とはいえ沖縄での生活は結構のんびりしていますし、オンとオフの切り替えができていると思います。あと、自分の所属しているコミュニティーが沖縄と東京ではまったく違うんですよ。東京にいるときは、やっぱりミュージシャンの仲間と会っていることが多いんですけど、沖縄の人たちはみんな、僕のことをミュージシャンとして認識していないんじゃないかな。家にギターが置いてある人くらいにしか思っていない気がします(笑)」
――青木さんのお子さんは、いまおいくつなんでしたっけ。
「中1と小4です。育児にもそんなに手間がかからなくなって、それも音楽を始めるタイミングとしては良かったのかもしれない。2人とも楽器を始めたんですよ。娘はギターとピアノ、息子はドラムをやっていて、レッチリの新作を聴いて3人で演奏したりしています。downyはあまり好きじゃないみたいですけどね(笑)」

――ハハハ(笑)。沖縄では飲食店を営みつつ、さらにデザイナーの仕事もされているそうですね。downyを再始動してからは、やることも増えて大変じゃないですか?
「まあ、東京に出てきたときにはついでに(音楽以外の)仕事もしていますし、沖縄は沖縄で、周囲のスタッフががんばってくれています。そのあたりのチームは出来上がっていたので、そんなに大変でもないですね」
――メンバーは東京に住んでいるということで、曲作りはメールのやり取りを通して行われるのでしょうか。
「はい。ドラムとベースだけはスタジオに入って録るんですけど、裕さん(青木裕/ギター)と僕に関しては、基本的に各々が自宅で録って、それをメールで送り合いながら仕上げています。最終的には僕のところで作業するという感じで。前作の〈第五作品集〉(2013年)からそういうやり方になりました」
――前作のどんなところを踏まえて、今作のレコーディングに取り掛かったんですか?
「前作は復帰後の第1作目ということで、ライヴをしないままスタジオに入ったんです。なので、結果的にライヴのことを一旦頭から外してレコーディングしていたんですね。そのぶん僕ら自身のパーソナルな部分が、直接的にサウンドに表れたような気がします。これまでのdownyのなかで、もっとも人間味が溢れる作品というか」
――ライヴで演奏するために〈武装〉した音楽というよりは、もっと〈素〉に近い感じ?
「そうなんです。人肌な感じがするというか。それはそれで僕はすごく好きだったし、良い作品だと思っていますけど、その後またライヴを重ねながら〈downyってどんなバンドだったっけ?〉ということに向き合っていくと、より一層余計な肉を削ぎ落とした、冷たい音を作りたいんだなと気付いたんです」
――冷たい音楽?
「冷たくて、人が触れることのできない場所にある音楽を作りたい。マグマの如きエモーションはあるんだけど、それを氷で閉じ込めたような音楽。燃え盛る炎を見ることはできるけど、触れることはできないというね。今回は、自分たちの音楽に対してかなりエモーショナルに向き合いつつも、いままででいちばんクールな作品になりました。ライヴを再開し、自分たちにふたたび向き合ったという意味では、原点に立ち返った作品とも言えますね」
――ものすごくクールで、鋭利な刃物のように研ぎ澄まされたサウンドなのですが、一方で以前のような殺伐した感じは後退しましたよね。もっと美しくてカラフルなイメージさえあります。
「流石にもう当時みたいな殺伐とした性格ではなくなっているので(笑)。〈第一作品集〉(2001年)あたりはめちゃめちゃ殺伐としていましたよね。どうしてあそこまで殺伐としていたのか……(笑)」
素晴らしいミュージシャンがメンバーにいるのは本当に強い
――ロビンさんのヴォーカルを大きくフィーチャーしている点は、前作を引き継いでいますよね。
「そうですね。もともとメンバーたちは、もっと僕の歌を入れたいと思っていたんですよ(笑)。前作でそれに挑戦して、自分でもちょっと自信を持てたのも大きい。エンジニアさんからは、今後これより歌のヴォリュームを下げることは絶対にないよ、と言われてました……。ただ、相変わらず自分の声はあまり好きじゃないんです。自分の声を聴かなきゃいけないのはすごくストレスで」
――それでもやはり歌を入れていこうと。
「はい。それはこの3年間、弾き語りをやらせてもらう機会が少なからずあったのが大きいですね。downyの曲を分解して、リアレンジして歌だけ残っている状態にして演奏したのが、自分は歌い手なんだと見直すキッカケになった」
――今回の作品は、歌モノを前提としてアレンジが構築されているように思いました。
「そうなんですよ。これまでのdownyは、ヴォーカルよりも楽器が主役というか、ヴォーカルは他の楽器のアンサンブルに組み込まれるような形で存在していたんですが、今回は最初からヴォーカルをどのセクションに入れるかを決めて、そこにスペースを用意しながらアレンジを構築していくという作り方だったんです。そのぶんミックスは難しかったですね。歌をこれだけ全面的に打ち出したことがなかったので、セクションごとに他の楽器とバトンタッチし合いながらダイナミクスを作っていく作業に相当時間をかけました」
――それは、単にヴォリュームの問題だけでなく、歌も含めた各楽器の周波数帯域のバランスまでアレンジの段階で考えているからですよね?
「そうです。もともと僕は打ち込みの人間なので、曲の作り方がテクノのそれなんですよね。曲作りの段階で、この楽器はこの周波数をカットして、その代わりにこの楽器の周波数を足して……みたいなことを、downyの初期からメンバーと一緒にやってきた。それこそ昔は〈VS〉※を使って作り込んでいましたよ(笑)」
※90年代後半にRolandが製造していたハードディスク・レコーダーのシリーズ名

――懐かしの〈VS〉シリーズ! デジタル圧縮された独特の音質が、特定のミュージシャンの間でとても人気がありましたよね。
「そうなんですよ。僕も大好きでしたね。〈第三作品集〉(2003年)を作った頃は、わざわざ一度〈VS〉で録った素材をプロトゥールスに流し込んでいました。搭載されているエフェクト機能も優秀なんですよね。〈第三作品集〉の世界観は、〈VS〉じゃないと再現できないんじゃないかとさえ思ってます」
――曲を作るとき、最初の取っ掛かりはどんなところから生まれるんですか?
「いろんな形があるんですけど、まずはリズム・セクションを作り込むことが多いですね。ある程度のパターンが出来たら、ドラムスの秋山(タカヒコ)くんがスタジオに入って実際に叩きながら録っていくんですけど、僕は沖縄から電話やメールをしつつ、秋山くんから〈このハットの置き方だとちょっと古いから、こんな感じにしてみない?〉と連絡が来たり、相互で〈欲しいアクセントはここかも〉〈じゃあ、代わりにキックを入れてみようか?〉みたいな意見交換をしたり、リアルタイムでやり取りしながら進めていきました」
――へえ!
「打ち込みで作ったリズム・パターンを生で叩いてみると、プレイ・バランスのなかでハット(の音)が小さくなったり、キックが出すぎたりするので、フィジカルで微調整していくんですよね。そのへんを、いま言ったような方法でディスカッションしつつ詰めていき、ベーシックのリズム・トラックが完成した段階でプリプロ(プリプロダクション/レコーディング前に行うデモ制作)が始まります。ベースと仮歌、裕さんのギターが入ると曲としての全体像が出来上がるので、さらにマッチョ(仲俣和宏/ベース)が展開しつつ、裕さんに〈エンディングのアイデアあります?〉と投げる。で、さらに格好良いギターを入れて、歌を練り直す。他にもいろんな曲作りのプロセスがあるんですけど、不思議なことに、どんなアプローチで作っても最終的には〈downyの音〉になるんですよね。仮に僕が弾き語りで作っても、間違いなくそうなる。素晴らしいミュージシャンがメンバーにいるというのは本当に強いですね」