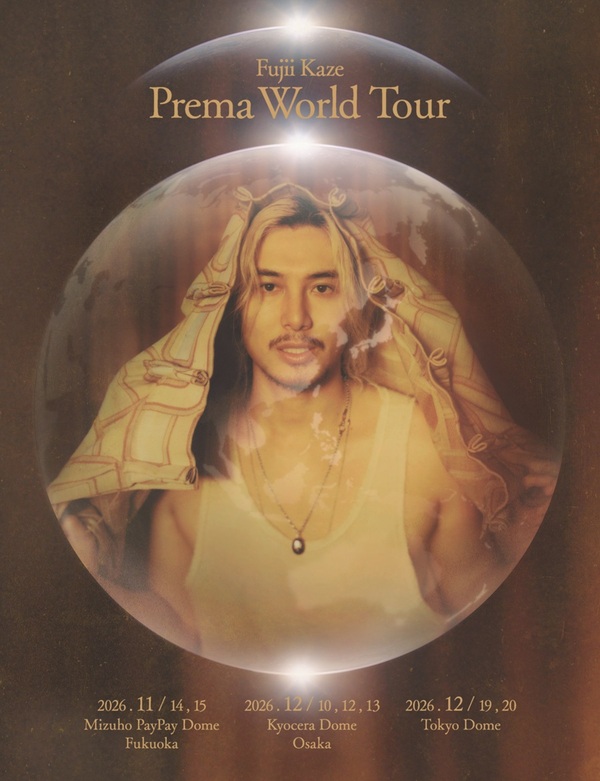〈ジャズのキャリアの終わりを告げる作品〉の真意
――WONKの2人はホセさんの新作を聴いて、いかがでした?
江﨑「すごく雰囲気が変わっていたので驚きました。これまでのアルバムでもロック的なアプローチを試みたりと、多岐に渡る方向性をお持ちでしたけど、それまでとはまったく違う作風だったので」
長塚「ジャケットにも驚いたしね」
江﨑「そうそう。これ、本当にホセ・ジェイムズのアルバム?っていう(笑)。でも、1曲目の“Always There”からみんなで〈これ、スゲエいいね!〉と話していました。なかでも、地名が続くリリックがすごく耳に残るんですよ」
長塚「Tokyo, New York, LA~♪」
ホセ「嬉しいね(笑)。この曲では自分の生き様を歌っているんだ。東京、NY、LAと常に世界中を移動していて、2か月も同じ街に留まることがない。最初のうちはそういう生活にエキサイトしていたけれど、いまはそれが日常になっている。どの街にいても落ち着けるようになるんだ。アーティストも外交官みたいに特別なパスポートを発行してほしいよね(笑)」
――新作の資料のなかで、ホセさんは〈僕のジャズのキャリアの終わりを告げる作品だ〉と言っていますよね。この言葉に僕はびっくりしたんですけど、その真意を教えてください。
ホセ「もちろんいまもトラディショナルなジャズは大好きだし、グレゴリー・ポーターのようにそういうものを歌い続けている人のことも好きだけど、トラディショナルなジャズでやるべきことを、僕はある意味やり尽くしてしまったんだ。ビリー・ホリデイのトリビュート・アルバム(2015年作『Yesterday I Had The Blues』)を作ったとき、あれ以上のジャズ・アルバムを作れないような気がしてね。バンド・メンバーもワールド・クラスだったし。だからまた新しいゴールを見つけるしかないと思ったんだよ。とはいえジャズにはこだわりを持ってやってきたので、そんなジャズに別れを告げるにあたってはほろ苦い感覚もあって。そんなビタースウィートな感覚がこのアルバムには出ていると思う」
江﨑「僕らも似たような話をよくしてるんですよ。ジャズも100年以上の歴史のなかで古典化してきていると思うんですね。クラシックにおいてベートーベンやバッハが素晴らしいものとされるように、ジャズにおいてもチャーリー・パーカーが古典になっている。日本のジャズ・シーンのなかではいまもバップ全盛期のスタイルが主流になってますけど、僕らの世代はそういう古典化した文脈から外れたところを切り拓いていかなきゃと思っていて。ジャズを起点にしながら、世界的な潮流の方向へと進んでいきたいんです」
ホセ「重要な視点だと思うよ。新しいことをやるのはいつもリスクが伴うけど、すごく意味があることだ。NYでは新しいことをやらないと誰も聴いてくれないけど、日本でやることに意味がある」
――ホセさんは〈ジャズのキャリアの終わりを告げる作品〉と言いましたけど、長年どっぷりジャズに取り組んできただけあって、どの曲にも気配としてのジャズは残っているように感じました。
ホセ「その通り。このアルバムもブルーノートからリリースされているわけだしね(笑)」
――そういえばそうでした(笑)。
ホセ「今回参加してくれたプロデューサーたちは、みんなミュージシャンの心を持っているんだ。スコット・ジャコビーやタリオ、ライクマインズもみんなマルチな人たちで、ここ10年で彼らのようなプロデューサー兼ミュージシャンはすごく増えたと思うよ。優れた技術と素晴らしい機材があれば、何でもできるようになった」

――ホセさんは、これまでもさまざまな音楽からインスピレーションを得て作品を作ってきましたよね。2014年の『While You Were Sleeping』はニルヴァーナやレディオヘッド、ステレオラブからの影響を反映していましたが、今回はどのようなものが元になっているんでしょうか。
ホセ「ドレイク、アンダーソン・パック、ビヨンセ、グライムス、ジ・インターネット……R&Bにまつわる新しいムーヴメントには常に刺激を受けているよ。FKAツイッグスも大好きだし。僕が若い頃、R&Bもヒップホップもニュー・ソウルも全部一緒になったような、クロスオーヴァーした作品がたくさんあったけど、いつからかコマーシャルな音楽が主流になってしまった。そういう流れがようやく終わりつつあって、フレッシュな音楽がたくさん出てきている。すごくおもしろいと思うよ」
江﨑「アンダーソン・パックやジ・インターネットみたいな最近のアーティストもチェックしているんですね」
ホセ「まあ、基本的にただの音楽好きなんだよ(笑)」
江﨑「いまは世界中どこでもほぼ同じタイミング・同じ環境で新しい作品が聴ける環境になっていますよね。それと同様に、どんどん国境やジャンルの壁がなくなりつつある」
ホセ「その通りだね」
――今回のアルバムにはトラップの曲までありますよね。びっくりしました。
ホセ「そこが聴き手の分かれ目だと思うんだよね。それを喜んでくれる人もいるけど、なかには〈ホセ・ジェイムズがトラップ?〉と思う人もいるから」
――一方で、トラップの曲が入ったアルバムをブルーノートがリリースしているというのもすごい話ですよね。
ホセ「クールだろ(笑)? まあ、(ブルーノートの現社長)ドン・ウォズがイケてるんだよ」
江﨑「ブルーノートもドン・ウォズがトップになってから作品の幅が相当広がりましたよね」
ホセ「そうなんだ。歴史のあるブランドだって、新しいものを常にクリエイトしていかなくちゃいけない。ブランドを守っていくだけじゃダメなんだ。ドン・ウォズにトラップの曲を聴かせたときのことは忘れられないよ。〈この曲どう?〉って訊いたら、無言で胸に付けたバッジを指差しているんだ。よく見たら〈Fxxx yeah!〉と書いてあった(笑)」
一同「(爆笑)」

――WONKの2人もこの機会に何かホセさんに質問があれば……。
江﨑「そうですね……僕らは同世代感に対する憧れがあるんです。ホセさんとグラスパーは同じニュースクールの卒業生ですけど、凄腕のプレイヤー同士が同じ学校の卒業生というだけじゃ、ここまで世界的なムーヴメントは起きなかったと思うんです。同じ世代同士で繋がり、新しいものを生み出していこうという明確な意識があったのかどうか知りたくて」
ホセ「ザ・ルーツが大きいと思うんだ。クエストラヴはソウルクエリアンズとしてもディアンジェロやエリカ・バドゥ、コモンの作品を支えたわけだし、ルーツが起点になった部分は大きい。あと、ソウルクエリアンズにも参加していたビラルがニュースクールの出身で、彼がグラスパーとさまざまなプレイヤーを繋げたんだ。当時はそうやっていろんなミュージシャンがナチュラルに繋がっていったんだよ。グラスパーがムーヴメントの最初のリーダーになったわけだけど、それ以前のルーツの存在も重要だったんじゃないかな」
――WONKはこれからヨーロッパ・ツアーを行うんですが、彼らのような日本人ミュージシャンが海外で活動することについてはどう思います?
ホセ「そうだな……インスタントの味噌汁は持っていったほうがいいね(笑)」
江﨑・長塚「ハハハハハ(笑)」
ホセ「いや、マジな話。ウチのバンドには日本人のメンバー(大林武司、黒田卓也)がいるときもあるんだけど、彼らは1週間もすると日本食が恋しくなっている。ツアー中に何を食べるかはすごく重要なことだからね。海外でライヴをやるのは初めて?」
江﨑「初めてです」
ホセ「そうか。どこでやるの?」
長塚「ベルリン、パリ、ロンドンです」
ホセ「ヨーロッパのリスナーはハードコアだよ(笑)。ただ、自分も最初のヨーロッパ・ツアーのときに友人になったDJとはいまだに付き合いがあるし、そのとき渡したデモテープがなぜかサンパウロのラジオ局でかかり、それをきっかけにブラジルに呼ばれたこともある。SNSを利用しながら友達をたくさん作ったほうがいいね。世界は小さいんだから!」