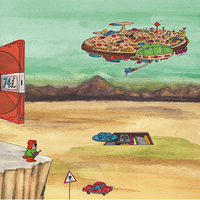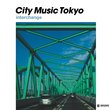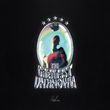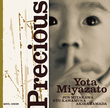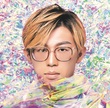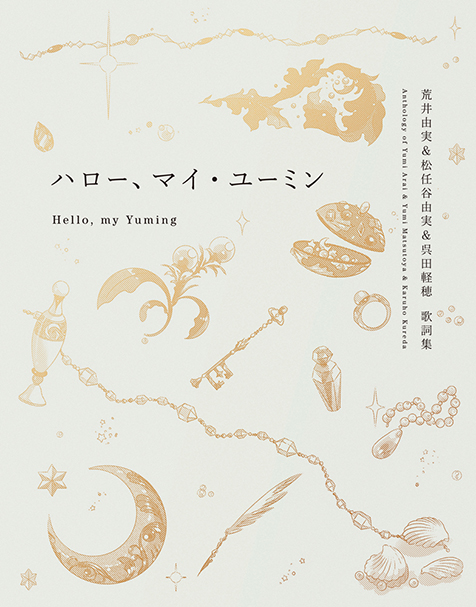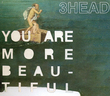小川翔(ギター)、山本連(ベース)、宮川純(キーボード)、伊吹文裕(ドラムス)の4人が集まったバンド、LAGHEADS。彼ら一人一人の名前は聴いたことがなくても、メンバーのプレイしている音楽をまったく聴いたことがないという人はいない。アニメの主題歌で、「紅白歌合戦」で、ドラマのサウンドトラックで、きっとどこかで耳にしている。そう言い切れるのは、彼らがみな今の日本の音楽シーンで〈ファーストコール〉(ミュージシャンが必要な場面で一番最初に声を掛けること)のミュージシャンたちだからだ。
そんなプレイヤーが集まったLAGHEADSの音楽は、70年代から現在まで、ジャズ、ソウル、ロックなど多様な参照点を、あくまでしなやかでポップなサウンドにまとめあげる。
KIRINJI、長塚健斗(WONK)、HIMI、吉田沙良(モノンクル)というゲストボーカリストも迎えた3枚目のアルバム『Who is “LAGHEADS”?』をリリースした彼らに話を聞いた。
普通のバンドと違う、凄腕4人ならではの制作
――LAGHEADSはほぼリモートで制作をされているとインタビューで読んで驚いたのですが、今作もリモートですか?
小川翔「今回も変わらずで、なんなら以前よりリモートになりました」
山本連「〈せーの〉で録るって、このバンドではやったことないですね」
小川「バンドが始まった頃は誰かの家で録ったりしましたが、今はほぼデータのやりとりで終わってます」
伊吹文裕「ドラムの録音は誰かしら立ち会ってくれますね。そもそもバンドを始めたのはコロナ禍で、みんな仕事が無くなったタイミングで、〈仕事も無いし何かやろっか〉というところから始まっているので、時間があったんです」
小川「単純にみんなが忙しすぎてリモートになっているのもあります」
――時間や場所の制限が無いと何度もリテイク(録り直し)したくなってしまいそうです。
小川「意外と無いですね。たいてい僕と連でデモを作って、それぞれが録ったデータが僕のところに集約されるんですけど、絶対デモより良くなってるので」
宮川純「前の方が〈ここにオブリ(ガート)がほしいから弾き直して〉とか、アレンジや音色のレンジに対する注文が出てきて録り直すことがありました。だんだんお互いのことがわかってきて、欲しいものや求められていることがわかるようになった感触があります」
山本「今思うと、1枚目(『What is “LAGHEADS”?』)はプレイ的にも音質的にも荒削りなところがあった気がして、そこより精度は上がったと思います。だんだんクリアになってきたというか」
小川「効率は上がってますね。リモートで作業しているからこそ、ミックスのエンジニアさんを含めてイメージの共有ができるようになったと思います」
――デモが出来て、最初に伊吹さんがドラムを生に差し替える段階では、アレンジにどのぐらい余白があるんですか?
山本「デモでは基本パターンを提示するぐらいで、シンプルなドラムしか入ってないですね。そのパターンすら録る時に変わったりして」
伊吹「余白はありますね。デモの段階でジャンルとかイメージはわかるんです。〈これはアース・ウィンド&ファイアーっぽい〉とかは、デモを聴いたらわかるので」
――そのイメージって言葉でも共有されるんですか?
伊吹「いや、そこまで具体的には無いですね」
小川「あんまりしないね。ドラムを録る時に準備しながら雑談するぐらいで」
伊吹「僕としては、ドラムを録る時に翔さんか連が立ち会ってくれてるのが大きいですね。曲におけるドラムの占める割合って大きくて、ドラムの音色とパターンが決まると全体のディティールも決まるので。そこが立ち会いで決まることで、自然と自分がやることの道筋が見えてくる感覚があります」
――お話を聞いていると、それぞれの音楽への理解度が高いことで成り立っている気がします。
山本「それぞれが毎日いろんなジャンルの音楽をやっているから、消化する力は高いと思います」
宮川「自分のバンドだけど、サウンドに関しては俯瞰して見られる部分があると思います。メンバーみんな〈俺はこれしかやらない、できない〉というプレイヤーではないので。そこは普通のバンドと違うところかも」
伊吹「どんな音楽が来ても面白いと思って演奏できるメンバーですね」