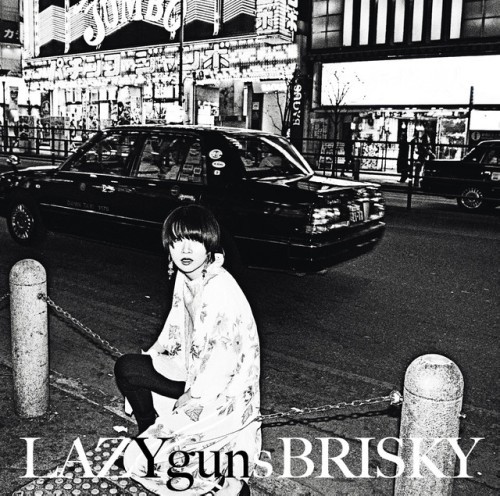2012年の解散後、メンバーそれぞれに活動していた3年間を経て2015年に再始動した4人組ガールズ・バンド、LAZYgunsBRISKYが初の全国流通盤となるニュー・アルバム『NO BUTS』をついにリリースした。今作のテーマは〈変化〉だったという。
浅井健一がプロデュースを手掛けた2008年作『“Catching!”』でメジャー・デビューを飾った彼女たちは、これまでロックンロール・バンドと捉えられることが多かったが、その頃からバンドを知っているリスナーは、今回プロデューサーに中尾憲太郎(Crypt City、元・ナンバーガール)を迎えたことを意外に思うに違いない。バンドのメンバーとして、ベース・プレイヤーとして、そしてプロデューサーとして、これまで中尾が主にオルタナティヴ・シーンで活躍してきたことを考えれば、それは当然だろう。しかし、その意外な顔合わせが新境地と言える全7曲に結実。〈変わりたい〉〈新しいことに挑戦したい〉という彼女達の想いがいかに強いものだったかを見事に代弁している。
取っ掛かりは90年代のオルタナやライオット・ガールだったそうだが、ダークかつクールなポスト・パンク・ナンバーの“Dress to kill”をはじめ、多彩な7曲を聴けば、それは単にきっかけに過ぎなかったことがわかるはず。ダンサブルな“Headache”“Axis”に、ハード・ロッキンとも言えるダイナミックなリフに語り風のヴォーカルが乗る“Suitable suicide”、バラードの“The Sea”、ファンキーでキュートな魅力がはじける“ADDICTION”。そこにデイジー・チェインソー“Love Your Money”のカヴァーを加えた7曲を聴く限り、現在の彼女たちは何にも囚われていないようだ。
今回Mikikiでは、メンバーと中尾との座談会をセッティング。両者の出会いまで遡って、中尾と共にバンドが今回どのような場所へ辿りついたのか、その道のりと共に掘り下げた。
最初は僕じゃないほうがいいと思った
――まず、みなさんと中尾さんのそもそもの出会いを教えていただけますか?
azu(ベース)「再結成後、初めての作品でもあるし、昨年10月にYukoが正式加入して新しい体制にもなったので、サウンド面を変えていきたいということになったんです。それでアレンジまで見てもらえるプロデューサーを探していたら、憲太郎さんがいいんじゃないかとお話をいただいてお願いしました。でもライヴを観てもらったあと、速攻で断られましたけど(笑)」
中尾憲太郎「いや、僕じゃないほうがいいと思ったんですよ。やっていることは同じで、僕もバンドだし彼女たちもバンドなんですけど、ライヴを観たらものすごくロックンロール然としたバンドだったから、やってきた環境の違いみたいなものをすごく感じて。もっとスムーズにできる人がほかにいるんじゃないかなと思ったんです。僕が参加しても、恐らく話をこじらせたりとか、意見のぶつかり合いになったりしそうで、全員がもやっとしたまま作品を作っても達成感もないし、いい作品になるわけもないのでお断りしたんですよ」
――でも、バンドとしてはサウンド面を変えていきたいというところで中尾さんだったわけですよね?
azu「そうです」
中尾「僕は最初その話を聞いてなくて」

Lucy(ヴォーカル)「全然違うところにいる方がいいと思ってお願いしたんですけど、それが伝わってなかったんですよね」
中尾「だから〈あ、そうなんだ〉って。その後、バンドともミーティングして……何でしたっけ、モーツァルトでしたっけ?」
Lucy「バッハです(笑)」
中尾「そう。〈バッハ〉っていう名前の居酒屋で打ち合わせをしたとき、変わりたいという意思を受けて、〈わかりました。そこまで思っているんでしたら、僕も覚悟を決めてがっつりやらせていただきます〉と」
azu「そのとき、YouTubeでいろんなバンドの動画を観ながら、こういうのをやりたいって話をして」
中尾「そういった話はすごく合ったんですよ。いろいろなバンドや音楽ジャンルの話をしたら共通項がたくさんあったので、それなら何か共通のゴールをめざして作れるんじゃないかって」
――例えば、どんなバンドが挙がったんですか?
Lucy「L7とか、あの時代のライオット・ガール的なものとか」
中尾「今回カヴァーしたデイジー・チェインソーとか、プライマル・スクリームも出たもんね」
Lucy「ゴシップも。ただ、ゴールは必ずしもそこではなかった」
――ここでちょっと遡って、バンドが変わりたいと思ったきっかけを教えてもらってもいいですか?
Moe(ドラムス)「曲は基本的にazuが作っていたんですけど、Yukoが加入する半年ぐらい前から、私はazuが苦しんでいる姿を見ていたんですよ。曲を作っていくうちに曲作りのテンプレートみたいなものが出来てしまって、私たちに合った曲は作れていたけど、はたしてそのままやり続けることが最善なんだろうかと。そういうところで、誰かにプロデュースをお願いしたいというのは、azuが一番思っていたことだったのかなという気がします」
Lucy「正解もわからないしNGもわからないっていう状況の中で、自分たちで指針を決めて時間をかけてやっていっても良かったんですけど、Yukoを迎えるときに誰かもう1人加わってもらったらいいんじゃないかと」
azu「これまでギター・ロックをずっとやってきて、その軸となるギターの音が変わるんだから絶好のタイミングだったんですよ」
Lucy「それに、Yukoがロックだけじゃなくていろいろなジャンルに興味があるのを知っていたから、彼女が入ったことでサウンドの幅が広がるって確実にわかっていましたし」

azu「Yukoは性格もいいし。人柄に惚れました(笑)」
Yuko(ギター)「ありがとうございます(笑)」
――逆にYukoさんは、バンドのどんなところに魅力を感じたんですか?
Yuko「音楽性は昔から対バンもしてたから知っていたんですけど、結局、人柄ですね」
azu「パクんなよ(笑)」
Yuko「硬派なイメージでやっていたところも含め共感できると言うか、活動しながら悩んでいるポイントも〈わかる。そうだよね〉みたいなところがめっちゃあったんですよ。自主制作でがんばってることに対して自分が助けになれれば、という気持ちもサポートをしながら芽生えてきて、(正式なメンバーとして)一緒にがんばりたいって思えたんです」
――その後、中尾さんと作りますとなってから、作業はどんなところから始めていったんですか?
azu「私が軽く作ったデモをバンドで合わせるんですけど、憲太郎さんにも一緒にスタジオに入って演奏を聴いてもらいながら、〈アレンジをもっとこうしたほうがいいんじゃないか〉と、最初はワンコーラスぐらいしかなかったものを一緒にフル尺にしていく感じでした」
中尾「スタジオの隅っこでひたすら聴いて、気付いたところを言って、それにチャレンジしてもらって……みたいなことをずっと繰り返していました(笑)。もちろん、僕の意見を絶対聞け!ということではなく、その都度意見をすり合わせながら良くなればいいかな、というスタンスではあったんですけど」
azu「憲太郎さんは思いついたことを何でも、〈とりあえずやってみよう〉って言ってくださるんですよ。そこからまたいろいろなアイデアが生まれるので、それがおもしろかったです」
――中尾さんのサジェスチョンで劇的に変わった曲はあったんですか?
Moe「“ADDICTION”という最後の曲ですね」
azu「本当は入れない予定だったんですけど、レコーディング中に1曲足りないってなって。紙に書きながら曲の構成を考えました」
中尾「書いたっけ?」
azu「書きましたよ、パズルみたいに。曲の部品というか素材は一応あったので、それをどう組み立てたらおもしろい曲になるかと考えながら、深夜2時ぐらいまで付き合っていただいて、それを一気にレコーディングしたんです」

中尾「作業時間内にちゃんと収まるかどうかハラハラしながらも〈やっちゃおう、やっちゃおう〉って(笑)」
Lucy「バンドの意思を汲みながら進めてくださるんですけど、結構時間はきっちり決めていましたよね?」
中尾「きっちりってほどではないんだけど、〈今日はここまでやらないと〉みたいなものはあって、その中でざっくりとね」
Lucy「感覚や感情、空気感とかを大事にしながら、その日の時間配分をちゃんと計算をしているんだと気付いたときに、憲太郎さんって一体どんな人なんだろうって不思議になりました。謎だ! 掴めない!って(笑)」
中尾「計算とまでは行かないけど、時間なのか音なのか、その時の優先順位をやっぱり考えないと。例えば深夜~翌朝とかまで作業しても次の日のポテンシャルが下がるだけなので、ある程度は区切ってやっていかないと効率は良くないですからね」
――そういった作業の結果、最初に言っていた〈ライオット・ガール〉だけじゃない作品になりましたね。
中尾「え、ライオット・ガールなの? 僕は全然意識してなかった」
Lucy「いや、それは例えばです」
azu「フェミニストじゃないですし(笑)」
Lucy「何か(特定のもの)を意識してはやっていないですね。だから型にはまったものにはなっていないと思います。私たちは〈変わりたい〉という想いで、憲太郎さんと1曲1曲時間をかけて大事に作りましたけど、こうでなきゃっていうものは、ホントになかったんですよ。逆に、どう聴こえました?」
中尾「そこは突っ込んだほうがいいよ(笑)」
――資料には〈ライオット・ガール・ムーヴメントの姿勢を彷彿とさせる〉とありましたけど、それだけに留まらない新しいサウンドに挑戦しながら、LAZYgunsBRISKYらしい作品になっていると思いましたよ。今回の制作を通して、メンバー自身はどういった変化がありましたか?
Lucy「あんまり変わってないかもしれない」
azu「私は性格が明るくなりました(笑)。暗かったわけではないんですが、制作前は〈やばい、曲を書かなきゃ〉ってプレッシャーもあって。アルバムが出来て、なんかホッとしました(笑)。そういえば、1曲目の“Dress to kill”を書いていたときは悲しい気持ちだったんですけど、作りながらどんどん悲しい気持ちになっていっちゃったんだった」
中尾「あ、そうだったんだ。そんな話はしなかったけど、そういうのは伝わるね」
Lucy「暗い曲だなと思いました?」
中尾「いや、暗いというのとはちょっと違うけど。でも、歌もいちばん大変だったもんね」
Lucy「ホント大変でした。あれトラウマですから、私(笑)。いちばん時間をかけましたよね」
中尾「いちばん早く終わるんじゃないかと思って始めたら、結局歌入れの日に録り終われなかった」
Lucy「別日に録り直したんですよね。もう1回、もう1回ってテイクを重ねるうちに私もこれじゃない、これじゃないって正解がわからなくなってきちゃって」
中尾「スケジュールでは、本当はその日のうちに歌を2、3曲録らなきゃいけなかったんですけど、その1曲で終わった」
Lucy「夜中までかかったんですよね」
中尾「楽器はまだ、それぞれがやってきたバックグラウンドが違ってもある程度は音やノリを説明できるんですけど、歌はやっぱり難しいんです。身体的なこともそうだし、精神的な部分もあるから、そこで僕とLucyのOKラインもだいぶ違っていたんですよ。でも最初に“Dress to kill”を録音して良かったのは、それが一番如実に出る曲だったんです。僕とLucyを含めたバンドとの溝を埋めるという意味で、ここでとことんやっておいたら後が楽だろうなと思ったんですけど、僕もエンジニアも途中で辛くなっちゃって。Lucyの辛さがわかるから。でもいくら時間がかかっても、ここでしっかりぶつかり合うことが最終的にいい結果になるだろうと判断しました。途中まではコンソール・ルームとヴォーカル・ブースを行ったり来たりしていたんですが、面倒なので〈コンソール・ルームで歌って〉と言って来てもらって、ヘッドフォンなしで爆音でオケを流しながら歌ってもらったり。いろいろなやり方を試して、丸1日使って仕上げました」