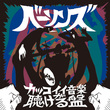GOING UNDER GROUND(以下、GUG)がニュー・シングル『超新星/よそもの』をリリースした。2015年にドラマー・河野丈洋が脱退し、3人編成になってからは、昨年発表の3作――シングル“the band”、アルバム『Out Of Blue』、ドキュメンタリーDVD「the band 記録と記憶」と、よりプリミティヴなロック・バンドへと立ち戻るべく活動を続けてきたGUG。自主企画〈全方位全肯定〉では、先輩格にあたるザ・コレクターズや同世代の銀杏BOYZ、さらにHomecomingsやスカートといった後続のバンドを招くなど、自らの音楽愛を自由に開花させたラインナップも痛快な印象を残した。だが、2016年の12月8日、そんな彼らを悲劇が襲う。それは、ここ数年に渡りサポート・キーボーディストを務めてきた橋口靖正の急逝。今回の“超新星”には、橋口への追悼の想いと供に、どんなことがあってもバンドは止まらないという決意が託されているという。GUGの現在地について、ライターの北沢夏音がフロントマン・松本素生にインタヴューした。 *Mikiki編集部
GOING UNDER GROUNDというバンド名を初めて目にしたとき、当然のようにジャムの名曲を想起した。彼らをルックスだけで判断する限り、どこから見てもモッズには見えない。だが、GUGのフロントマンである松本素生が、僕の前にクラブDJとして現れたとき、そのエクレクティックかつ小粋な選曲はモッド以外の何ものでもなかった。事実、彼は90年代にハードコアなモッズ・チーム〈ブルー・ドレス〉が主催するパーティー〈ウィスキー・ア・ゴー・ゴー〉に足繁く通った時期もあったという。
その夜、彼と少し会話してみて、僕らにはいくつかの見過ごせない接点があることがわかった。そして、しばらく会わないでいる間に、GUGに大きな転換期が訪れたことを知った。そんなとき、友人のウェディング・パーティーで久々に再会したYouth Recordsの庄司信也に、GUGを取材したいという希望を伝えることができた。昨年のシングル”the band”に心を掴まれたというのもある。しかし、松本素生とじっくり話してみたいと思った一番のきっかけは、シャムキャッツやHomecomingsといった、現在のインディー・ポップを代表するバンドの中心メンバーが松本に寄せる熱い想いに触れたことだ。松本を囲む座談会での夏目知幸と福富優樹の発言は、ジャムのこんなエピソードを僕に思い起こさせた――ロンドンの通りを歩くふたりの少年が着ているTシャツの片方には、“俺はポール・ウェラーを知っている”と書いてあり、もう一方には“俺もだ”と書いてあった――。
松本素生がブルーハーツから受け継いだもの
――素生くんのことは前から知っているけれど、インタヴューは初めてなので今日はニュー・シングルのこと以外にも、いろんな話が訊けたら嬉しいです。
「こちらこそ。初めてお話ししたのは庄ちゃん(庄司信也)のイヴェントでご一緒したときですよね」
――そう。僕もDJに呼んでもらって、そのとき素生くんのDJを初めて聴いて、選曲もプレイのスタイルも最高だなと思った。でもGUGの音楽と、DJでかけている音楽の印象がかなり違っていて、まずそのことに驚いた。
「そうですね」
――そのとき、正直な感想として、好きな音楽と実際にやっている音楽が、そんなにくっきりと分かれていてバランスが取れるのか、葛藤があるんじゃないかと思ったんです。
「いや、だから葛藤はありましたよ。ずーっとあって、それがなくなってきたのが最近ですね。去年『Out Of Blue』というアルバムを出したんですけど、自分たちが以前所属していた事務所を抜けて、庄ちゃんと一緒にやるようになり、〈またゼロから始めるか〉となった2016年あたりから、聴いているレコードと実際にやっている音楽があまり違わなくなってきた感じがありますね」
――GUGはメジャーのレコード会社と契約していて、ヒット曲も出して、いわゆるJ-Popのフィールドで活動していましたよね。
「そうですね」
――今も昔もJ-Popのフィールドには、いったん確立した音楽性を劇的に変えるバンドはあまりいない気がするんです。レコード会社からもファンからも安定を求められる部分があるだろうし、変化したい気持ちとのバランスを取るのが難しいんじゃないかと。
「それはあるかもしれないですね。俺らも最初はそんなこと考えなかったし、そんなにすごく売れたわけじゃないけど、2006~2007年ぐらいから何か〈商品〉を作るような感覚が自分のなかに生まれてきた。とはいえ、自分の好きなミュージシャンを見てると、もっと何て言うか……自分の魂に忠実に作っているようなイメージがあって、(自分たちもそうしたいのになかなか振り切れないという)葛藤は、正直言ってありました。庄ちゃんとよく遊ぶようになったり、北沢さんと三宿WEBでDJやったりしたのは、ちょうどそんなときです。あの頃は本当に過渡期で、友達からも〈それでバランスが取れるのか〉って、よく言われてました」
――2006年というと、サンボマスターや銀杏BOYZの盛り上がりが熱かった頃。
「そうですね。俺たちは、どちらかというとだんだん普通っぽくなってきたときかな、分析すると。何かつまらなくなってきたなぁ、という頃ではありました」
――活動がルーティン化してきたということ?
「ルーティンというより、バンド内に〈もっと自分の心に忠実に音楽を作りたい〉という奴もいれば、〈いや、バンドの形を保って進んでいこうよ〉という奴もいて、今思えば、そのバランスを取ろうとする状態をかなり長い間続けてきちゃったな、というのがありました。ただ、ここ数年は、聴いている音楽や自分の心のなかに流れているものをそのまま楽曲にして、出来上がったときに〈これだよね!〉と思える感覚が戻ってきましたね」

――庄司くんのイヴェントで素生くんがかけていたレコードは、60年代のR&Bやニューオーリンズ産のアーシーなファンク、カリブ海産のスカ、ロックステディ、カリプソといったモッドな音楽で、基本的にはシンプルなギター・サウンドを旨とするGUGに、個人としての素生くんが好む音楽はなかなか反映しづらいだろうな、と思った記憶があるんです。
「うんうん。でも、俺が〈音楽しかやりたくない!〉と思ったきっかけがブルーハーツだったから。俺が中学生の時、Nack5※で〈ブルーハーツのしおり〉っていうラジオ番組をやっていて、そのなかで(甲本)ヒロトが〈自分たちはブルースだからね〉って言ったんです。俺はそのとき〈えっ、ブルースってこういう感じ(の音楽)ではないんじゃない?〉って思ったんだけど、ヒロトが言うところのブルースの感じが、25歳ぐらいからわかってきたんですよね。口で説明するのは難しいけど、ブルーハーツとロバート・ジョンソンやサム・クックは一緒だと。要するに、ギターの鳴り方が云々というよりも、彼らの音楽から受け取るものは一緒なんだということが、感覚としてわかってきたんです。2000年代後半のGOING UNDER GROUNDは、そのジレンマがわかってきちゃったからこそキツかったな、というのがありましたね」
※松本の出身地である埼玉県のラジオ局。
――ぼくは雑誌のクイック・ジャパンで、ヒロトの軌跡を追いかけるルポ※を連載していたことがあるんです。
※クイック・ジャパンVol.36(2001年4月発行)掲載〈ヒロト・アーリー・デイズ(前篇)〉、Vol.37(同年6月発行)掲載〈ヒロト・アーリー・デイズ(後篇)〉
「その連載は読みました」
――ぼくは、ブルーハーツ以前にヒロトがやっていたザ・コーツというモッズ・バンドのライヴを観ていたから、“人にやさしく”を聴いたとき、ヒロトはオーティス・レディングの“Try A Little Tenderness”をこんなふうに昇華することができたんだ!と直感した。〈Try A Little Tenderness〉をヒロト流に訳したら〈人にやさしく〉になるんだなと。そう思ったら、震えるぐらい感動して……。
「うんうん、なるほど。そうですね」
――そういうふうにブルーハーツの音楽を理解できたから、素生くんのその感覚はすごく腑に落ちる。
「はい。じゃあ、その感覚がわかるとどうなるかというと、そう思えない曲は駄作でしかなくなるんです」
――めちゃくちゃハードルが上がって、ジャッジの基準が厳しくなるという。
「そうなんですよね。だからたぶん、(ブルーハーツがやったことは)全部発明っていうか、自分の魂に忠実に、世の中の流れとかも気にせず、〈いや、俺、今これだから最高!〉となっている奴がそれをやるのは、本当に最高なんです。それは最高にロックンロールなことだけど、〈いや、でも本当はそうじゃないのにな〉と思いながらそれをやるのは、ロックンロールとはかけ離れている話だから……。ジャンルに関しては、俺はあんまり自分で分けているつもりはなくて、ただその音楽を聴いたときに、生活とか後のことはどうでもよくなるというか、〈この瞬間、死んでもいい〉と思えるような音楽を自分のなかからもっと生み出したい。ここ数年やってきて、最近ようやく〈この歌を歌っている瞬間、俺はもう他のことはどうでもいい〉と感じられるようになってきた」

バンドのすべてを曝け出したドキュメンタリー「the band 記録と記憶」
――確かに今回のシングル、“超新星”と“よそもの”の2曲を聴いても、すごく吹っ切れた感じが伝わってくるんです。このシングルは新生GUGが〈今の俺たちはこうです〉って裸の姿を晒したステイトメントなんだな、と。
「そうですね……最近、俺たちは馬鹿だなっていう結論に達しましたけど。レーベルの事務所でダベっていて、バンドマンは本当にコスパが悪い、それを一所懸命にやってる俺たちは馬鹿じゃないのか!?って。元も子もないですけど(笑)」
――いやいや(笑)、でもここ10年くらい顕著な風潮として、コスト・パフォーマンスを追求するという価値観が広まって、〈コスパが悪い=悪〉みたいな空気が蔓延しているのが現状で。それはバンドマンもそうだし、僕みたいな物書きも完全にそうだから、じゃあ、なんでこんなことやってるんだろう?という話にはなるよね。
「そう! で、なんでやってるんだろうと思いながら、でも、この曲が出来たからいいやとか、この本が書けたからいいやっていう、その煌きを更新していきたいだけなんですよね、実は」
――まさに。それで食えるに越したことはないけど、たとえそうじゃなくてもやってしまう業みたいなものがありますね。
「もう、業でしかないんだろうな。最近、あるミュージシャンの友達の家に遊びに行ったら、とにかく豪邸だったんです。〈えーっ! 音楽でこんなに儲かる?〉っていう話になって、〈いや、楽曲提供とかいっぱいやってるからね〉と言うので、ちょっと調べてみると〈これはこの家、建つな〉みたいな(笑)。でも、俺が全身全霊を懸けてそれをやったとしても、果たして自分の心が満たされるかといえば、満たされない。だから俺たちは馬鹿だっていう話になったんです!」
――そうだなあ……(笑)。
「それをやって満たされるなら、そっちに行けばいいじゃないですか。ただ、それをやっても満たされないということは、頭が悪くてしょうがないんだろうな、と思って厭になっちゃったんですよ。ついさっき、2時間前に(笑)」
――そうなんだ(笑)。コンビニとかファミレスとか居酒屋みたいに、ほんの1円の違いにしのぎを削っているような業態で、コスパを追求するのは当たり前の価値観だけど、音楽業や文筆業にその物差しだけを当てると成立しなくなっちゃうでしょう。商売なのか表現なのかわからないことに人生を懸けるというのは古典的な命題で、コスパが悪いのが厭ならやめるか、なんとかして続けるか、その二択しかない。今回の取材の前に、GUGがオフィシャル・サイトとツアー会場のみで販売したドキュメンタリー・フィルム「the band 記録と記憶」を観たら、〈ファンに夢を与える〉なんてものじゃなくて、それとは真逆のことをやっているから愕然とした。
「ハハハハ! そうでしょ?」
――普通は隠しておくようなことをほぼ全部出しちゃってる。赤裸々という形容はこのためにある、みたいな感じ。でも感動した。ここまで裸にならないと、もう一回スタートできないという思いがあったのかな、って。
「まあ、そうですね」
――だって、辞めたメンバーををもう一回呼び出して、なんで辞めたのかを語らせる場面とか映してるし。
「はい。彼らがまた好き勝手なことを言ってるじゃないですか」
――そうそう、それが良かった(笑)。
「ぶん殴ってやりたい、って思いましたよ!」
――(爆笑)。あれはもちろんヤラセじゃないでしょう?
「俺らは会っていないですもん。俺らはこの作品について、一切口を出していないんですよ。これはカットしてくれとか何も言ってない。それをやると俺たちってカッコいいだろ?ってことになっちゃうし、これを撮ってくれた監督(瀬川功仁)の作品でもあるから、完全にお任せ。上がってきたものを観て、〈ねえ、これ出すのぉ?〉ってなった(笑)」
――そうでしょう(笑)。いや、素晴らしい作品だと思います。現役のバンドのドキュメンタリーでここまで内情を曝け出したものは観たことがない。
「そう。今、俺たちが取り戻そうとしているのは、2001年にデビューして、メジャー・レーベルと契約して、わりといろんな人に作品を聴いてもらえて、ある年代の人たちに〈GOING UNDER GROUNDって知ってる?〉と訊いたときに〈あ、知ってる〉とか、ライヴは観たことがない人でも〈“トワイライト”っていう曲は知ってます〉とか、そういうふうに認知されている現状もわかりつつ、ソフトにされていた部分を一回全部ぶっ壊して、ゼロに戻して、思う存分自分たちの音楽をやりたいという実はシンプルなことなんです。そこから派生していく問題、たとえば子供がいるしとか、街で生きて暮らしていくことだとか、そういうことは、俺はこっち(音楽以外の仕事)で賄うし、とにかく音楽やバンド以外で手垢まみれになった部分を一回きれいにしたいという想いがずっとあったんですよね。それをやらないと、自分がこの瞬間に死ぬ、っていうときに、あれやっとけば良かったとなっちゃうから、自分の人生のプライオリティーにおいて、それだけは厭だなと思ってるんですよ。
だから、今のGUGを外部の人に伝えるに当たって一番わかりやすいのは、〈やり直してる〉っていう言葉かな。あ、GUGってこんなバンドだったんだねと再確認してもらえたらいいけど、別に自分のなかのプライオリティーとして高いわけではなくて、俺たちはただ、俺たちの歌を歌いたいだけ、なんです。あとは全部付属品みたいなもので、CDが売れるとか、ライヴにお客さんがいっぱい入るとか、たいした問題ではあるんだろうけど、そんなにたいした問題でもないと思っている自分がいます。それよりも、この曲が書けたとか、これを今歌えたということのほうが、自分のなかでは大きい。だから、〈プロのミュージシャンっぽくない考え方だなあ〉というのは、自分でも思いますけどね」
――いろんな意味で初心に返ったという。
松本「そうですね」