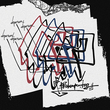GOING UNDER GROUND(以下、GUG)の2年半ぶり、3人編成になって初のアルバム『Out Of Blue』は、何者をも恐れぬ正真正銘のロックンロール作品だ。バンド・サウンドは威風堂々と力強く、フロントマン・松本素生の歌声は雲一つない青空のように澄み渡っている。リード・シングル“the band”と同様のパンキッシュな疾走感が全編を貫いていると共に、キャリア20年を誇るバンドならではのふくよかなグルーヴが気持ち良い。つまり『Out Of Blue』は、長年GUGを愛聴してきたファンのみならず、これまで彼らに触れることのなかったリスナーが聴いても〈フレッシュだね〉〈カッコイイね〉と親指が立つアルバムになっているはずだ。今作が、多くの新しい出会いをもたらすことは間違いない。
その後押しをすべく、Mikikiでは、松本に若いミュージシャンとの鼎談を提案してみた。そこで彼が希望したのは、8月にリリースしたニュー・シングル“マイガール”が話題のシャムキャッツ、そして5月にセカンド・アルバム『SALE OF BROKEN DREAMS』を発表し、先日行われた〈フジロック〉のライヴも好評だったHomecomings。ここでは、シャムキャッツから夏目知幸(ヴォーカル/ギター)、Homecomingsから畳野彩加(ヴォーカル/ギター)、福富優樹(ギター)の3人を招いて、和やかな雰囲気のなか取材が行われた。
★GOING UNDER GROUND“the band”のインタヴュー
★シャムキャッツ“マイガール” に合わせての、KIRINJI堀込高樹との鼎談
★Homecomings『SALE OF BROKEN DREAMS』のインタヴュー
シャムキャッツとホムカミに出会って、自分たちは遅れてるなと思った(松本)
――まず松本さんがなぜこの2バンドと話したいと思ったのかを教えてください。
松本素生(GOING UNDER GROUND)「俺は家が近いのもあり、よくCOCONUTS DISKの吉祥寺店に行っているんですよ。あそこはインディーのバンドをいろいろとリコメンドしているじゃないですか。そこでシャムキャッツとHomecomingsに出会ったんです」
――それぞれどの作品から聴かれていますか?
松本「シャムキャッツは『たからじま』(2012年)、ホムカミは“I WANT YOU BACK”(2014年)の7インチを買ったのがきっかけかな。そのあと京都のMETROに行ったときに福富くんが来ていて、〈Homecomingsというバンドをやってるんです〉と7インチをくれたんですけど、〈俺もう買ったよ〉と」
福富優樹(Homecomings)「そこで、〈え!?〉って(笑)」
松本「夏目くんとは最寄りの駅が一緒みたいで、電車でよく見かけて〈あ、夏目くんだ!〉と思ってました。でも面識がないし〈僕バンドやってて……〉といきなり言うのも変だなと思って、ずっと声をかけられずにいた(笑)。今日が初対面なんですよ」
夏目知幸(シャムキャッツ)「ハハハハ(笑)! 僕もまったく一緒で、いつも電車で〈松本さんだ!〉と思っていたんですよ」
――両バンドの音源を聴いたときには、どんな印象を持たれましたか?
松本「俺は2組とも絶対に自分と似ているところがあると思ったんです。ハモれるところがあるなって。俺らがずっといた場所はもうちょっとJ-Rock寄りみたいな、いわゆるメジャーの土俵――例えばちょうど今日〈ROCK IN JAPAN〉に出たんですけど、シャムキャッツもホムカミも、ああいうところに来るお客さんに向けた音楽とは別のところでやっている感じがして、すごく自由だなと思ったし、羨ましさを感じた。もし学校のクラスにそういう人がいたら、俺もそっちに混ざりたいと思える存在」

――松本さんが彼らのそうした点に魅力を感じたということは、いわゆるJ-Rock的なカルチャーに居心地の悪さを感じている面もあったのでしょうか?
松本「(キッパリと)あった! それはいまでも……いやデビューしてからずっと思っていて。自分が好きな場所とはちょっと様子が違うな、音楽を本当に好きな人がバンドを聴いてくれているのかな、と思っていました。ちょっとおごりがあるように見えるかもしれないけど、音楽が好きな人に〈良いじゃん〉と言ってもらいたかったんです。だから、そことはちょっと違うところに行っているなというのを認識しつつの、この15年だった。そうしたなかで、この2組みたいなバンドに出会って、自分たちは遅れてるなと思っちゃったんだよね」
一同「へー!」
――3人から見て、松本さんがJ-Rockのシーンやカルチャーに居心地の悪さを感じていたというのは意外なことでした? それとも納得できること?
夏目「僕はめちゃくちゃ納得です。自分は高校生のときに、GUGの『かよわきエナジー』(2001年)や『ホーム』(2002年)をリアルタイムで聴いていたんです。高校1年生の冬にスノーボードに行ったんですけど、スキー場に向かう深夜バスのなかでも、ウォークマンでGUGを聴いていた。自分の恋や反抗心などのヒリヒリとした気持ちとGUGの音楽が描く傷口みたいなものが合わさっていて、自分の青春と完全にシンクロしていたんですね。別にJ-Rockという括りで聴いていたわけじゃなくて、自分がグッとくる音楽の1つとして好きでした。だから自分のリスナーとしての経験から、いま松本さんが言っていたことはすごく納得できたし、〈こんなに正直に言えるのか!〉とちょっとビックリしたくらい」
松本「でも本当のことだからね(笑)。夏目くんが聴いてくれたのはファースト~セカンド・アルバムの頃ですよね。(GUG)が超良いときです」
一同「ハハハ(笑)!」
――松本さんがその頃のGUGを〈超良い〉と断言できるのは、どういうポイントからですか?
松本「当時の俺らは、なんだかわからない反骨精神に溢れていたんですよね。デビューする前後はまだ景気も良くて、下北沢のシーンみたいなものがあった。自分たちはそこに完全に属せてないという感じもありつつ、属してたまるかと思っていたんです。みんなと同じことをやってもおもしろくないじゃんという気持ちが初期の作品には反映されている。『かよわきエナジー』『ホーム』『ハートビート』の頭3作は特にそうですね。それ以降はもうちょっとプロっぽくなっていったというか、やっぱり技術を覚えちゃって、手癖で鳴らしていた瞬間もあったと思う。シャムキャッツやホムカミを聴いたのは、その真っ盛り(の時期)でしたね。彼らを聴いたときに、いまのままだと恥ずかしくて〈好きだ〉と伝えられないな、と思ったんですよ。夏目くんに〈俺、シャムキャッツが好きなんですよ〉と堂々と言えるようにならないといけないと考えた」
夏目「えー! そんなことを言われるとは(笑)。バンドのメンバーにいますぐ伝えたいですね」
私たちにとってはいちばん影響が大きい存在なんです(畳野)
――Homecomingsの2人は、夏目さんより年齢が一回り下だと思うんですけど、GOING UNDER GROUNDとの出会いは?
福富「『ホーム』が出たのは僕らが小4くらいの頃なんですよね。僕が最初に聴いたのは、小6のときに〈Mステ〉で“トワイライト”を歌っていたのを観て、当時の僕にGUGやスピッツ、アジカンが刺さったんです。それが音楽を好きになったきっかけであり、ずっと自分の軸にもなっていて」
畳野彩加(Homecomings)「私は福富から教えてもらったんですよ。高1くらいまでは本当に音楽に興味がなくて、ただのアイドル・ファンかつ女子バレー部の一員で(笑)。高1のときに福富と同じクラスになって、そのときに彼がバンドをやっているという話を聞いて、〈へー〉と思ったんです」
福富「クラスでライヴのチケットを配ると、彩加さんが観に来てくれて、そこでバンドって素敵!となったらしく(笑)。なんか入口になるものを貸してくれと言われたので、GUGが入ったMDを作ってあげたんです」
畳野「そこでGUGを聴いて、〈こんなんあるんだ!〉と思ったんですよ。バンド・サウンド自体がすごく新鮮で、それまでなんとなく聴いてきた音楽が違う聴き方になった。歌詞を聴いたり、曲の流れに意識が行ったり、ちゃんと音楽を聴くきっかけになった存在なんです」
松本「それは嬉しいですね。ちゃんとやってて良かったと思うし、その反面、もっとちゃんとやれたはずだという俺もいるんですよ」
畳野「私たちにとってはいちばん影響が大きい存在なんです」
福富「いまだにツアーに行くときも、僕が作ったGUGベストを車で聴きながら行ってますからね。盲目的なファンですよ(笑)」
――そのなかでもHomecomingsの2人が特に好きな作品は?
福富「うーん、僕は『ホーム』がいちばんですかね。ちょっと暗いアルバムなんですけど」
松本「クソ暗い作品だよね。音も変だし」
福富「こもった感じの音ですよね。でもその感覚にグッとくるというか」
夏目「“夜の宝石”みたいな、ドラムがほとんど聴こえないような曲もありますよね。スネアがすごく遠くて」
松本「俺の立場で言うなら『ホーム』を良いと言ってくれる人とは絶対に友達になれるんです」
一同「ハハハ(笑)!」
松本「それは絶対あります。〈『ハートビート』が最高でしょ〉と言われると、〈そっか、なるほど〉って(笑)」
――畳野さんは特に好きな作品と言えばどれですか? ここで『ハートビート』とは言いにくいですけど(笑)。
畳野「いや、私も福富と被っちゃうんですけど、『ホーム』ですね。時期によっていろいろ変わるんですけど、結局戻ってきちゃうのが『ホーム』なんですよね」
松本「『ホーム』を出したときにズッコケたんですよ」
夏目「えー!? めちゃめちゃ良いのに!」
松本「セールス的にもそうなんだけど、俺ら自体も半信半疑で、〈わからないんだけどこれが出来ちゃったんだよね〉みたいなノリだったしね。だから俺らのなかでも、次はちゃんと広がるアルバムを作ってみようとしたのが、次の『ハートビート』だったんです。俺らはいったんそこで終わっちゃっているんですよ。GOING UNDER GROUNDというものは1~3枚目で完結していて、そこから先は模索し続けてきた」
福富「確かに『h.o.p.s.』(2005年)からちょっと違いますよね。盲目的なファンからすると3作目までが一つの物語で、そこから変わっていく流れだった」
松本「ブルーハーツの歴史と一緒ですよ。一応好きではいるけど、初期の3枚には敵わないでしょ、と言われるような。俺らはそういうバンドだったと思う」
――その期間を10年以上続けてこられたわけですよね。
松本「いやー、もうキツかったっすよ(笑)」
一同「ハハハ(笑)!」
松本「そのなかでメンバーが2人抜けちゃいましたからね」