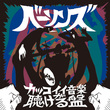今年でデビュー20周年を迎えるGOING UNDER GROUND(以下、GUG)が、新作『FILMS』をリリースした。メンバー脱退やサポート・ミュージシャンとの死別など数々の分岐点を乗り越えながら、音楽カルチャーにおける激動の時代を生き延びてきたGUG。2015年以降は、中学時代の同級生にしてオリジナル・メンバー――松本素生(ヴォーカル/ギター)、中澤寛規(ギター)、石原聡(ベース)による3人組となりつつ、『Out Of Blue』(2016年)、『真夏の目撃者』(2017年)と充実した内容の作品を精力的に発表してきた。さらに、今年の春には初期の代表作にあたる3作、『かよわきエナジー』(2001年)、『ホーム』(2002年)、『ハートビート』(2003年)をアコースティック・アレンジで再録し、自身のオンライン・ストアとライヴ会場限定で販売。20年を迎えてなお、バンドはギアを弱めるどころか、まずますアクセルを力いっぱいに踏みしめている。
『FILMS』は、そんなGUGの好調っぷりを、なによりも雄弁に伝えてくれるアルバムだ。エレクトロ・ポップ的な意匠が目立った前作『真夏の目撃者』と比較するならば、本作は〈ロックンロール・バンド〉GUGを刻印した作品と言えるだろう。逡巡なく放たれる多彩なギター・サウンドと、しなやかなリズム・アンサンブルが、酸いも甘いも味わい尽くしたうえでロック、言い換えれば〈バンドで音を鳴らすこと〉に心酔し続ける彼らの横顔を映し出す。また、歌詞の面では、40歳を迎えたメンバーたちならではの大人な味わい――かつて抱いた夢は消え、傷痕だらけになりながらも前へと進もうとする意志を託した、ビターな描写が目を引く。はたして、今のGUGを突き動かしているものは、いったいどんな想いなのか? 松本素生を訪ねた。
誰かを〈これで大丈夫?〉と不安にさせるものじゃないと、つまらない
――松本さんは本作『FILMS』を〈今までと肌触りは確実に違うアルバム〉とツイートされていましたね。ご自身では具体的にどんなふうに違っていると思われますか?
「自分たちが積み重ねてきたものを、自分たちで大事にする必要があんのかな?と思うようになったんです。バンドをやる理由は楽しいからなのに、そのこだわりいる?みたいな。それは3人になってからずっと思ってたんだけど、前2作――『Out Of Blue』と『真夏の目撃者』を作ったことで、〈GUGらしさへのこだわり〉が完全になくなった。結果的に、マンネリではない作品が作れたから、自分でも聴いていて驚きがあるし、なにより楽しいんです。そういった意味での肌触りかな」
――前作『真昼の目撃者』は、エレクトロニクスやダンス・ビートが大胆に採り入れられていたりと、挑戦作でもあるように感じたんです。
「『真夏の目撃者』はレーベル社長の庄司(信也)も首を傾げてましたね(笑)。〈え? これでいくの?〉って。俺は、〈いやいやこれで大丈夫だから〉と。〈GUGと言えばってのがあるから不安になるだけだから〉って。でも、誰かが不安になったり、大丈夫かな?って思ったりすることをやってないと、おもしろくないんですよね。もう結論みたいになっちゃうけど、僕にとってはおもしろいか/おもしろくないかっていうその一点だけしかないんです。
CDが30万枚とか売れてて、横アリで2デイズやりますっていうバンドだったら、もうちょっと別の考え方やショウビズ的な視点があるんだろうけど、〈GUGくらいの規模でやっているバンドが、どうしてそこに合わせなきゃいけないんだろう?〉というのは、結構ずっと疑問でした。GUGというバンドを例えるなら、20年やっている街の中華屋みたいなもんだと思うんです。〈美味しい〉と言う人もいれば、〈あんまり好きじゃないんだよな〉と言う人もいる、でも、お店としては〈これで良いんだ〉と思ってやっている。なのに、なんでわざわざ日高屋みたいな考えでやんなきゃいけないのか――そこを基準にすることこそ、いまの時代では時代遅れだと思っているんです。そもそも曲を作ってCD売ることもそう。CDを作ってツアーをやる……その謎はいまも考え中なんですけどね」
――今年の春にライヴ会場とオンライン・ストア限定でリリースした初期3作のセルフリメイク盤――『かよわきエナジー 2018~forevergreen~』、『ホーム 2018~midnightblue~』、『ハートビート 2018~emotionalred~』はどういう位置付けなんですか?
「俺のなかでは、完全にそれらを過去にする作業というか、〈もういまのお前たちにはこれを作れないよ〉という確認作業でもありました。こういう瑞々しさとかはもう絶対に出ないから、覚悟しろって気持ちで向き合いましたね」
――資料では〈アコースティック・アレンジにて再録〉となっているけど、実際は打ち込みが入っていたりストリングスを使っていたり、サウンドは実に多彩。〈GUGらしさ〉から解き放たれたうえで、音楽的な創造性の爆発が起きている3作だと感じました。
「なんかね、もうこのバンドであるかぎりは、なんでもいいってのがあった。ただ、自分たちの独特な匂いは、残していきたいと思ったんです。そのためには、〈こういう曲がみんなに人気だよ〉とか〈ライヴで盛り上がるね〉とかを排除しないといけないんだよね。そのあたりが緩くなってくると、だんだん自分たちの匂いがしなくなってくる。俺はやっぱり自分たちの作品を聴いても感じますもんね。いちばん最初に出した『Cello』(98年)やメジャーのファースト『かよわきエナジー』には、むせかえるような匂いがある。ただ、それでご飯を食べられるようになって、ビジネスになっていくなかで、徐々に匂いが薄まっていった。そこで、〈あれ? これは?〉ってのを経験したからこそ、今は匂いを残したいんです。ライヴでも、その匂いを残すために最新の曲を中心にやりたいし、昔の曲はあんまり演奏しなくなりましたね」

とにかく、まだまだ前には進んでいたいんだ
――そういった気持ちがはっきりしたことで、制作の方法にも変化があったんですか?
「今回は、ふと生まれてきた曲を入れたというのがデカいです。アルバムのために書いた曲ではなくて」
――以前はもっと目的を持って曲を書いていた?
「〈シングル向きに書こう〉とかはあったし、曲をメンバーに聴かせる際にも、自分のなかでふるいにかけていたんですよ。裸をさらけ出したものでも、結局最後まで股間だけは隠していた、というか。〈これちょっと出ちゃっているから、今回は一回外してほかのを聴かそう〉って(笑)」
――ハハハ(笑)。
「3人になって初めてのアルバム『Out Of Blue』は、第二のファースト的な作品になったんだけど、でもファーストって何回も出来るものでもないし、次の『真夏の目撃者』の制作時には、次何を作ればいんだろう……と思っていました。で、ナカザ(中澤)とプリプロに入っているときに〈曲出来ないわー〉と言っていたら、〈とりあえず、あるやつ全部聴かしてくれない?〉となり、そこで〈剥き出しすぎるし聴かせなくていいか〉ってものも、すべて聴かせたんですよ。そうしたら、〈いやこれ良いっしょ、こっちも良いじゃん〉みたいな反応があった。ほかの2人も〈GUGらしさ〉みたいなものに飽きていたんですよね。だから、バンドとしてドンドン風通しがよくなるなかで、〈演奏していて楽しい〉とか〈新鮮だ〉とかを最優先して作ったのが『真夏の目撃者』というアルバム。そこで、やっぱりこの方向性、こうあるべきだとなった前提で最初から作れたのが、今作『FILMS』ですね」
――さっき『FILMS』の楽曲は自然と出てきたとおっしゃっていましたが、いざ並べてみて共通項を見出すことはありました?
「〈とにかく、まだまだ前には進んでいたいんだな〉ってのは思いましたね。つまり、今も居心地の悪さを抱えているんだなってこと。その気持ちは全曲に共通しているんじゃないんですかね」
――〈今いる場所から出ていかなければいけない〉というテーマは特に“HOBO”の歌詞などに顕著ですよね。今作はいつになく大人の哀感というかビターな味わいがある作品にもなっています。
「歌の出発点は日々のなかで感じていることで、そのことだけは20年間変わっていないと思うんです。だって、20歳そこそこでデビューして、その年齢の若者がストレートに感じていることを歌ったらやっぱり甘酸っぱいじゃないですか? 今年、俺は40歳だけど、同じようなことが曲の出発点なのだとしたら、歳をとればとるほど、仕事とか家族とか暮らしのなかでいろいろある。そこでビターになるのは当然だと思うんです」