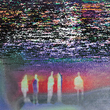右手左手関係なく指10本で弾いている感じ。でも、それがピアノだと思う
――ジャズとヒップホップ、それぞれのルーツについて訊かせてください。まず、ピアノを弾き始めたのはいつ頃ですか?
「14歳のときに、オーストラリアに引っ越すことになって。僕は黒人と白人のハーフで、家ではパプア語で話していたから、英語がそんなに上手くなかった。それで引っ越しする前、お爺ちゃんに言われたんです。〈お前は向こうに行ったら白人に見えるから、みんなオーストラリア人だと勘違いする。でも育ってきた文化も違うし、言葉も話せないから、友達は絶対に作れない。だから楽器を始めた方がいい〉って」
――すごい話ですね!
「お父さんのピアノが家にあったから、適当に弾きはじめて。最初はクラシックから入りました。それからオーストラリアで音楽の高校に入って」
――ピアニストだと誰が好きですか?
「一番好きなのはデューク・エリントンですね。あとは、レニー・トリスターノがとにかく好き。テディ・ウィルソンのような1920~30年代のジャズにもハマっています。もちろん、ビル・エヴァンスとかモダンな人も聴きますけど、家で聴くのは古いのが多い。歳を取れば取るほど、若いときに聴いていた音楽にまた興味が湧いてきて」
――他にはどのあたりを?
「ピアノを始めたときは、ニューオーリンズ系のピアニストをよく聴いていました。プロフェッサー・ロングヘアやジェイムズ・ブッカーみたいな」
――今回のアルバムを聴くと、どれも頷ける名前ばかりですね。
「そうですか? 若い頃はジャズってライヴの音楽だと思っていたから、レコードは買わずにライヴばかり追いかけていましたね。オーストラリアにいた頃だと、アンドレア・ケラーやティム・スティーヴンスは何度も観ました。あと、ポール・グラボウスキーはヤバイ。今年の〈東京JAZZ〉にも出演していて、来日中に彼のアルバムをプロデュースしたんですよ」
――アーロンさんのプレイは、繊細なタッチとフリーキーな過激さを併せ持っているように映りますが、ピアニストとしてどんなことを意識しています?
「それは演奏するシチュエーションにもよるかな。僕にもピアニストとして長所と短所があって、例えば速く弾くことはできない。でも弾く音が綺麗だと知っているから、その音色を前に出してゆったりさせることに集中しています」
――スキルよりテクスチャーを大事にしている?
「そうそう。ピアノを上手く弾きたいとも思わないし、そもそも自分はピアニストではないので(笑)。僕は〈音楽を作る人〉だし、作曲家は音色が好きだから」
――ヒップホップからの影響が、ピアノの演奏に出てくることもありますか?
「あー、あるかもしれない。J・ディラのビートをよく聴くと、サンプルの音がスネアの後ろから出てきますよね。そういうタイム感とか。最近、(ピアノを弾く)左手を遅くして右手を速くしたり、その逆をやったりもしていて。ヒップホップっぽいコード進行を使うこともあれば、自分のピアノを(トラック用に)サンプリングすることもあるし」
――左右の手が非対称に動き回るプレイは、アーロンさんの十八番って感じがしますね。今回のアルバムの聴きどころにもなっている。
「僕は右手と左手(の違い)はあまり関係ないので。指10本で弾いている感じ。でも、それがピアノだと思いますね」