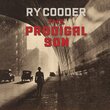60年代から活動するアメリカのヴェテラン・ミュージシャン、ライ・クーダー。スライド・ギターの名手、アメリカン・ルーツ・ミュージックの探求者、ヴィム・ヴェンダース監督の「パリ、テキサス」(85年)などに代表される映画音楽家、アフリカ音楽や〈ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ〉(97年)でのラテン音楽の紹介者――長きにわたるキャリアを通して、ライ・クーダーはひとつの場所に安住せず、様々なフィールドでその足跡を残してきた。
そんなライ・クーダーが大統領選をテーマとした前作『Election Special』(2012年)から約6年ぶりに新作『The Prodigal Son』をリリースした。アメリカ音楽史の古層から掘り起こされた霊歌~ゴスペルを現代的に解釈したカヴァーを中心に、アメリカの政治状況に鋭い視線で切り込んだオリジナル曲も収録。本作はどのようにして作られたのか? あるいは、そのメッセージとは? ジュリアン・ベイカーについての記事でも筆を揮った映画評論家・大場正明がライ・クーダー渾身の新作を読み解いた。 *Mikiki編集部
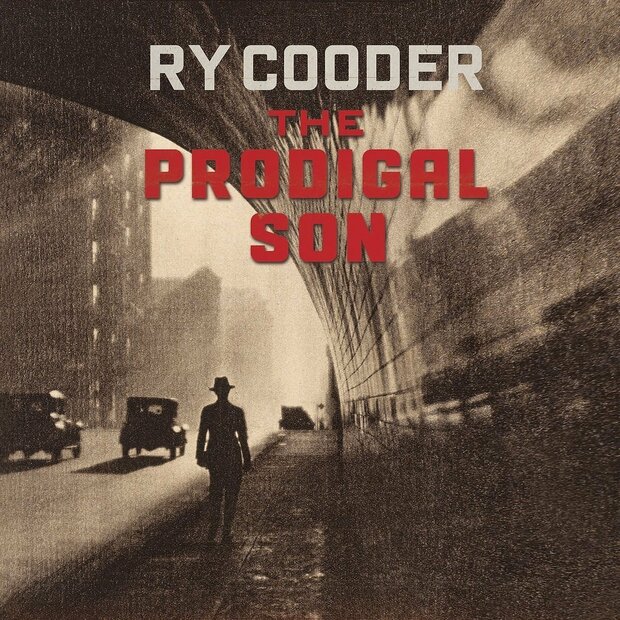
21世紀も創作意欲が衰えないヴェテラン、ライ・クーダー
自身が生まれ育ったロサンゼルス郊外のサンタモニカを拠点にしてきたライ・クーダーの活動や表現は多岐にわたる。彼はスライド・ギターの名手であり、マルチインストゥルメンタリストでもある。ルーツ・ミュージックの探求者であり、70年のアルバム・デビュー以来、ブルース、フォークをはじめ、カントリー、テックス・メックス、ジャズ、ハワイアン、アフリカなど様々な音楽を取り込み、独自のタイムレスな世界を切り拓いてきた。
80年代に入る頃からは、映画音楽にも積極的に取り組み、「パリ、テキサス」を筆頭に、映画の題材やストーリーと深く結びついたサントラを手がけた。また、『Talking Timbuktu』(94年)のアリ・ファルカ・トゥーレやブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブのキューバの老ミュージシャンなど、異色のコラボレーションでも注目を集めている。
21世紀に入っても、ライの創作意欲は衰えていない。もともと彼は、音楽を通したストーリーテラーでもあったが、2000年代半ばから後半にかけて発表された〈カリフォルニア三部作〉は、歴史と物語と音楽を緻密に結びつけ、明確なヴィジョンを提示するようなコンセプトに基づいている。
ロサンゼルスに実在したメキシコ系のコミュニティーを題材にした『Chávez Ravine』(2005年)では、強引な再開発計画によって土地と家を奪われた貧しい人々の物語が語られる。ウディ・ガスリーやジョン・スタインベックの世界を意識したような『My Name Is Buddy』(2007年)では、時空を超えた旅をする主人公の赤猫が、労働者や農民や黒人など抑圧された人々の目撃者となる。
最終章の『I, Flathead』(2008年)では、カントリー・ミュージシャンを主人公に、ビートニクやDIY文化やSFなどの要素が盛り込まれ、戦後のカリフォルニアが描き出される。だが、ライの歴史と物語へのこだわりにはまだ続きがある。彼はこの後、戦後のロサンゼルスを舞台にした短編小説集『Los Angeles Stories』(2011年)を発表しているからだ。
さらに、三部作に続く『Pull Up Some Dust And Sit Down』(2011年)と『Election Special』では、新たな方向性が打ち出される。これまでライは、政治的な意図を込めるにしても、歴史を通して現代を見直すようなスタンスをとってきたが、経済危機や大統領選にインスパイアされたこの二作品では、経済格差、銀行、ウォール街、共和党、移民政策、イラク戦争、グアンタナモ収容所※などに対して、痛烈な批判が加えられている。
ライの隠れたルーツ――ブルーグラスとゴスペル
では、約6年ぶりの新作になる『The Prodigal Son』では、それがどう変化しているのか。曲目は、ピルグリム・トラベラーズ、スタンレー・ブラザーズ、ブラインド・ウィリー・ジョンソン、ブラインド・アルフレッド・リード、ブラインド・ルーズベルト・グレイブスらのカヴァーと3曲のオリジナルで構成されている。古いブラック・ゴスペルとホワイト・ゴスペルを中心とした作品だ。
ライはデビュー作『Ry Cooder』(70年)で、リードの“How Can A Poor Man Stand Such Times And Live?”やジョンソンの“Dark Is The Night”を取り上げている。しかし、単純に原点回帰と思うのは大きな間違いだ。
前作と新作の間に、ライと彼の息子でドラマーのジョアキムは、ブルーグラス界の重鎮リッキー・スキャッグスと彼の妻シャロン・ホワイトとともにツアーに出ている。彼らは一年かけて準備し、一年にわたるツアーを行った。ライは、このツアーに関して、いくつかのインタビューで興味深い発言をしている。
彼は、ハイスクール時代にブルーグラスを聴き、バンジョーを習っていた。そして、J・D・クロウのようなバンジョー奏者になり、ブルーグラス・バンドの一員として活動することを夢見ていた。そんな彼は、ビル・モンローやドク・ワトソンと一夜だけ共演したことがある。バスの故障でバンドのメンバーが揃わず、バンジョー奏者として彼が参加することになった。しかし結局、お前にはまだ早いといわれ、チャンスを生かすことはできなかった。その後、彼はギタリストとして成長していくことになる。
さらに、もうひとつ印象に残るのが、その十代の頃にブルーグラスの代表曲を覚え、さらにゴスペル・ソングもみな覚えなければならなかったと語っていることだ。ニール・V・ローゼンバーグの「ブルーグラス―一つのアメリカ大衆音楽史」には、ブルーグラスとゴスペルの深い結びつきが以下のように説明されている。
「宗教音楽はほとんどのカントリー・パフォーマーのレパートリーに見られるが、ブルーグラスのレパートリーにおいては並外れて突出している。最も影響力のあった初期のブルーグラス・バンド、モンロー、フラット・アンド・スクラッグス、スタンリー・ブラザーズ、そしてリノ・アンド・スマイリーの録音および印刷物(ソングブック)のうち、ゴスペル・ソングは、平均で30パーセントを占めていた」
そんなライの隠れたルーツが、彼とスキャッグスやホワイトを結びつけ、彼らのツアーが新作の出発点になった。新作に収められたリードの“You Must Unload(すべてを捨てて)”は、ツアーでも取り上げられ、ステージではライを中心に演奏されていたことから、彼の希望が反映された曲目であることがわかる。この新作は、ライがツアーをきっかけに、ブルーグラスを通してゴスペルを見直していったことが、そのインスピレーションの源になっている。
新作『The Prodigal Son』の政治性と世俗的視点
しかし、ゴスペル中心の作品だからといって、そのテーマが宗教一色になっているわけではない。オリジナルの“Gentrification(再開発)”には、ライの関心が垣間見える。ライの地元であるロサンゼルスという極めて人工的な都市は、ダウンタウンの再開発によって変貌しつづけている。その再開発の実態をここで確認しておいても無駄ではないだろう。ロサンゼルスの歴史を多面的に掘り下げたマイク・デイヴィスの「要塞都市LA」では、以下のように説明されている。
再開発による地域の高級化には、「新住民と旧住民、貧者と富者との間に起きるいかなる空間的相互交渉をもさせないという偏見がある」「今日の金持ち向けのエセ公共空間――豪華なショッピングモール、オフィスセンター、要塞のような文化施設――は、アンダークラスの〈他者〉に近づかないようにと警告する見えない標識であふれかえっている」
ライはそんな再開発を単純に批判するのではなく、象徴的な意味を込めている。この曲ともうひとつのオリジナル“Shrinking Man(縮んでいく男)”を繋いでみると、私たちが見えない大きな力に動かされ、気づかぬうちに他者を排除するようなシステムに取り込まれていることをほのめかしているように思えてくるのだ。
そうなると、ジョンソンの“Everybody Ought To Treat A Stranger(見知らぬ人には親切に)”や、お洒落やお金や権力を愛するクリスチャンに対して〈すべてを捨てて、身軽になりなさい〉と語りかける“You Must Unload”が、直接的、あるいは風刺を込めたメッセージとして心に響いてくる。
また、ツアーの影響はサウンドにも表れている。新作では、ほとんどの曲をライとジョアキムのふたりで演奏しているが、やはりライのバンジョーが印象に残る。ツアーでは、ライがギターではなくバンジョーを担当する曲が何曲かあったが、新作でも積極的に使っている。絡み合うバンジョーとマンドリンのリフやバンジョー特有のアクセントと、ジョアキムのパーカッションやムビラの響きが、変化に富む空間を生み出している。ライのヴォーカルも力強く、深みがあり、明らかに表現力を増している。
ライはこれまでにもゴスペルのスタイルを取り入れているが、この新作では、ゴスペルの位置づけが以前とは違うように思える。先述したローゼンバーグの「ブルーグラス」には、ブルーグラスとゴスペルの関係について興味深いことが書かれている。
ブルーグラスを育んだアパラチア地方には、膨大な数の山岳宗派が存在していた。ならば宗派同士が反目しあってもおかしくないが、そこには「すべての人が自分自身の説教師であるという広く信じられている感覚」が存在した。人々は教会に通うことを重視しなかったが、それでも宗教についてよく語り、考えていたという。著者はそんなことを踏まえ、ブルーグラス・ゴスペルを「世俗的な文脈で語られる神聖なるものについての対話である」と定義している。
ゴスペルを中心としたライの新作には、神や聖書や天国や審判などの表現が頻出するが、ライの視点は、宗教的ではなく世俗的である。オリジナルの“Jesus And Woody(ジーザスとウディ)”では、イエスがウディ・ガスリーに語りかけ、新約聖書の〈放蕩息子のたとえ話〉に基づくタイトル・トラックの“The Prodigal Son(放蕩息子)”では、本物の宗教を探すために旅立った放蕩息子が、ベーカーズフィールドで、スティール・ギターを奏でるラルフ・ムーニーという神に出会う。
この新作は、ブルーグラス・ゴスペルの作品というわけではないが、ライ・クーダーの流儀に則った「世俗的な文脈で語られる神聖なるものについての対話」と表現することもできるだろう。