
リュカの秘かな愉しみ
望むだけ深く息を吹きかける。これはジャック・ケルアックが散文の信条としたことのひとつだ。リュカ・ドゥバルグの弾くスカルラッティを聴いていて思い出すのも少々へんだが、乱反射する即興の煌めきが関係したのかも知れない。あるいは、物語ることへの、私的で詩的な情熱が――。
この夏、トッパンホールでもドメニコ・スカルラッティをたくさん弾き継いで、リュカ・ドゥバルグは譲れない愛着と独自の方法を示した。響きと空間に対する彼独特の感覚が活き、フラジャイルな光彩を不透明に放った。個的な神秘を温めながら、ざらついている。
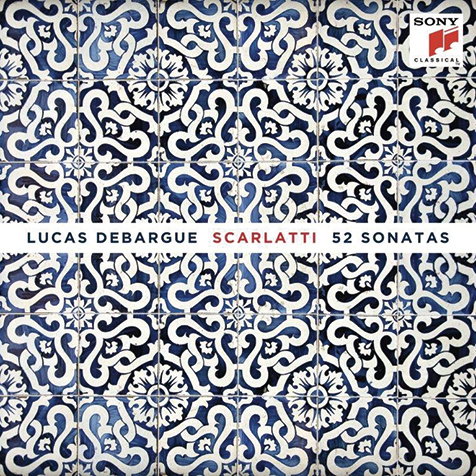
昨秋に録音されていたアルバムでは52のソナタを4枚に配列し、もっと内向的で親密な、くつろいだ集中のなかで、多様な作品に映し出される自己をみつめている。それは万華鏡の幻影か、重なり合う鏡面か。青年は一心にそれをみる、執心と愛着の深さを身上として。
なにかをみせよう、といった仕草は、ここではほとんど感じとれない。古い楽譜のページを密かにひらくような素振りで、それぞれの曲を弾く無心の愉しみを、幸福感に同調させている。表現への意欲を示すより、内面の探索という趣が色濃く、個的な没入感が優勢だ。様々な意匠は凝らされているが、技巧をみせるのではなく、むしろ不器用で、武骨な手触りで彫り込むような趣もある。つまりは、手の内をみせるのでも、手の内に収めるのでもなく、手の内そのものの音楽を息づかせている。
ひとことでいえば秘儀的であり、個人的な儀式のようにもみえるが、祈りというよりも、忘我の戯れに近い。饒舌にして寡黙。細部に飽くことのない好奇心が宿っている。ページを捲るごとに、インクの滲みを指でなぞりつつ、紙面の凹凸を確かめるようにして、親密な聴取の体験を呼び覚ます。聴き進むほどに、フラジャイルな迷宮に嵌まっていく感覚が濃密になる。そこはやはり孤絶した時空だ。明晰さと陰翳の襞のうちに、なにかがひっそりと謎めいた息をしている。尽きることのない、小さな物語たちが、そっと光る。















