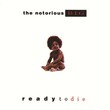2020年2月に銃撃され、20歳の若さでこの世を去ったラッパーのポップ・スモーク(Pop Smoke)。彼は、ヒップホップ/ラップ・ミュージックの新潮流〈ブルックリン・ドリル(Brooklyn Drill)〉の旗手として注目を集めていた。ポップが亡くなってからもその勢いはやまず、ブルックリン・ドリルが発展していっている状況は、こちらのコラムでお伝えしたとおり。
今回は、ブログ〈にんじゃりGang Bang〉で知られる書き手のアボかどがブルックリン・ドリルのルーツを探った。なぜ米NYブルックリンという街で生まれた音楽にUKドリルのビートが取り入れられたのか? その背景には、ブルックリン・ヒップホップとレゲエとの深い関係性や長い歴史があった――。 *Mikiki編集部
ブルックリンとUKの共通点はカリブ系の多さ
故ポップ・スモークのブレイクにより注目を集めたNY発のヒップホップのサブ・ジャンル、〈ブルックリン・ドリル〉。ここ日本でもXXS MagazineやFNMNLといった媒体や、このMikikiでも特集が組まれており、その解説も進められてきている。
既に多くのメディアが紹介している通り、ブルックリン・ドリルはシカゴ発のサブ・ジャンル〈ドリル・ミュージック〉が渡英し、同地の音楽〈グライム〉と結び付いて発展した〈UKドリル〉が、インターネット上で〈○○っぽいビート〉を販売する〈タイプ・ビート〉と呼ばれるビート販売文化を通してNYのブルックリンに逆輸入されて誕生したものだ。
しかし、一人のラッパーがタイプ・ビートで曲を作るという行為は、非常にパーソナルなものではないだろうか。それがなぜ、ブルックリンのラッパーがこぞってUKのビートを買い求めるようになり、新たなムーヴメントの発生にまで至ったのか。また、なぜクイーンズといったNYの他のエリアではなく、ブルックリンでそれが起こったのか。
ブルックリン・ドリルのシーンから最初にスターとなった故ポップ・スモークは、Complexのインタビューで「ブルックリンとロンドンは同じだよ。(中略)同じような食べ物を食って、同じ飲み物を飲んでいる。(中略)同じスラングも使う。従兄弟みたいなものだよ」と、遠く離れたUKの地にシンパシーを感じていることを語っていた。ブルックリンとUKには、大きな共通点がある。ジャマイカをはじめとするカリブ系の人口が多いことだ。
シカゴとイギリス、ブルックリンの3つの地を舞台に語られることの多いブルックリン・ドリル。本稿ではここにさらにジャマイカも加えつつ、主にブルックリンのヒップホップがレゲエの影響と共に歩んできた歴史を振り返り、ブルックリン・ドリル誕生の由来を探っていく。
ブルックリン・ヒップホップ史とレゲエ:
80年代前半に活動しはじめたハウィー・ティー、90年代初頭に登場したバスタ・ライムズの
ブルックリンのヒップホップ史におけるUKとの古い接点では、UK出身でブルックリンに移住し、80年代前半から活動していたプロデューサーのハウィー・ティー(Howie Tee)の存在があった。また、ハウィー・ティーにはジャマイカ出身でブルックリンに移住したラッパーのチャブ・ロック(Chubb Rock)という従兄弟がいた。2人のタッグは87年にシングル“Rock ’N Roll Dude”をリリース。同曲のビートはランDMCなどとの同時代性を感じさせるロック風のギターをフィーチャーしたものだったが、チャブ・ロックの荒々しい発声のラップはレゲエとの共通点も発見できるものだった。
そして、ハウィー・ティーは89年にはブルックリン出身でジャマイカ系のラッパーのスペシャル・エド(Special Ed)のアルバム『Youngest In Charge』を手掛けた。同作収録の“Heds And Dreds”は非常にレゲエ色の強い曲で、ブルックリンのヒップホップ史におけるレゲエ要素導入のかなり早い例として挙げられる。
同作がリリースされた時期の80年代後半から90年代前半にかけて、それまでのヒップホップの特徴として強かったマチズモを排してサンプリングの面白さに重きを置いたアーティストが多く活躍していく。そして、その時期に登場した〈ニュースクールのリーダーたち〉と名乗るグループにもまた、ブルックリン出身でジャマイカ系のラッパーが在籍していた。バスタ・ライムズだ。
リーダーズ・オブ・ザ・ニュースクールはサウンド面ではレゲエ的な要素はなかったものの、バスタ・ライムズのパワフルな高速ラップはレゲエからの影響を強く感じさせるものだった。ア・トライブ・コールド・クエスト(以下、ATCQ)が91年に発表したポッセ・カット“Scenario”での凄まじいヴァースが話題となり、バスタ・ライムズはその強烈なラップ・スタイルを武器に人気ラッパーへと登り詰めて行った。