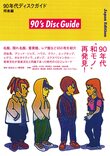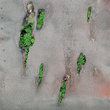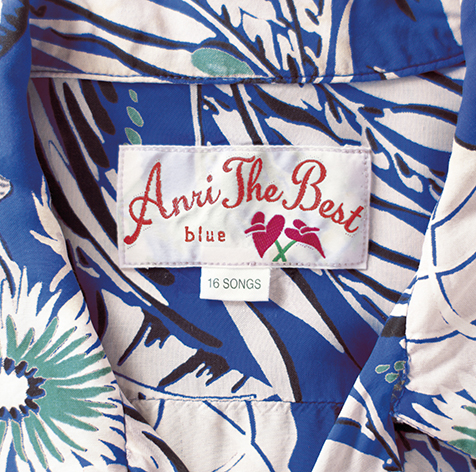UKダンス・カルチャーを受け継ぐジョイ・オービソン『still slipping vol. 1』
――では、その流れでジョイ・オービソンについて話しましょう。彼がリリースした初のアルバム・サイズの作品『still slipping vol. 1』を聴いて、いかがでしたか?
野田「すごくうまいなって思ったな」
河村「そうですね。ちょうどいいところに全部落としこんでいますね」

JOY ORBISON 『still slipping vol. 1』 XL/BEAT(2021)
野田「リズムがこなれている。ジョイ・オービソンの基本は、やっぱりガラージだよね。シャッフル気味の、2ステップのビートで」
河村「このバウンシーな跳ねるリズムがUKの感じですよね」
野田「ハウスやテクノの4つ打ちじゃなくて、ジャングル由来のビートなんだよね。一言で言うと、〈UKの音〉。ジョイ・オービソンを聴いていると、イギリスに行きたくなるよね(笑)」
河村「ただ、すごくいいアルバムだけど、インパクトがあるシングルのような、それこそシーンの流れを変えてしまうような作品ではないかな、とは思っていて。もちろん、すごくよくまとまっている作品なんですが。〈ミックステープ〉と銘打たれているから、ちょっとスケッチっぽさも感じましたし」
野田「コアレスにしても、まとまった作品をリリースするまでに時間がかかったよね。だけど、UKは12インチ・カルチャーがずっと続いているから、それはある意味でしょうがない。シーンに属しているDJやプロデューサーだったら、12インチで作品を発表しつづけることは真っ当な行為だからね」
河村「ジョイ・オービソンに関しては、最近はデジタル配信の曲もありますけど、一時期まではストリクトリーにアナログ・レコードを出しているイメージがありました」
野田「たぶん、レイ・キースに生粋のものを叩き込まれたからだよ(笑)。レイ・キースはジャマイカ系移民だから、そう考えるとジョイ・オービソンの家族っておもしろいよね」
河村「従姉妹のお姉さんが彼にUKガラージを教えた、というエピソードもありますね」
野田「ジャケットがまた最高だよね。そのガラージを教えてくれたお姉さんの写真なんだけど、正直に言って、どう見ても労働者階級で、そこがすごくいいなと思った。きっと、彼のそういう背景もアルバムに影響している気がする。

というのも、ちょっと話は逸れるけど、今回の〈ユーロ(UEFA EURO 2020)〉でおしゃれな若者たちが騒ぎまくっている光景を見て、昔ながらのフットボール・ファンとしては異様だなと思ったんだよね。90年代まではさ、サッカーっていうのはもともと労働者階級の娯楽だから、スタジアムはガラの悪いフーリガンかケン・ローチの映画に出てくるようなしがないオヤジ連中がいる場所だった。そんなフットボールでさえ、言い方は悪いけど、いまでは中産階級に乗っ取られちゃったんだよね。もちろん〈安全になって何が悪いんだ〉という反論はあるんだけど、逆に言うと入場料が上がっていて、労働者階級の人々はスタジアムに行けなくなってしまった。
同じことは、音楽についても言えるよね。クラブだって入場料が上がって、昔のように行く場所がない貧乏人が遊びに行ける場所ではなくなってしまった。そんななかでジョイ・オービソンのようなプロデューサーが出てきて、こういう作品をリリースするのは、UKのソウルというか、栄光の労働者階級文化だよね」
河村「去年、RAに対する批判記事が話題になっていて、そこでは〈ロンドンの労働者階級の主に黒人たちが作っていたUKファンキーやハウスのシーンをRAは一切取り上げなかった。それは人種差別的なんじゃないか? 中産階級の白人たちの視点から見た音楽しかここには載っていないんじゃないか?〉と書かれていたんですね。
ジョイ・オービソンも白人で、それこそRAのようなメディアから評価されてきたアーティストでもあるので、ローカルなシーンでどう思われているかはわかりません。でも、少なくとも本作を聴くと、UKファンキーに通じるUKガラージ由来のハウス的なビートの、彼の音楽への影響力の大きさを改めて感じます。しかも、UKガラージを彼に教えた人をジャケットに持ってきているわけで。そのあたりは音楽性を含めて、そういったシーンに対するリスペクトとか、彼がどんなシーンから出てきたのかとか、みずからのスタンスを示す作品でもあるのかなと思いました」
野田「あと、彼の作品にはソウル・ミュージックの要素があるからすごくソウルフルで、ノーザン・ソウルの時代から伝わるUKの労働者階級が好きなスタイルをちゃんと継承しているんだなって感じる。
それともうひとつ、コンセプチュアルなアルバムじゃなくて、こういう作品だったのがいいなと思ったな。同時代にデビューした人たちは、みんなコンセプチュアルな方向へ行ったじゃん。ジェイムズ・ブレイクなんて〈DMZ〉※で朝まで回していたわけだけど、LAへ移住して、まったくちがう方向へ行った」
河村「ジェイムズ・ブレイクは、初期のライブで“Anti War Dub”のカバーをやっていましたよね。さすがにいまはもうやっていなさそうですが、歌モノでもないシーンのアンセムをライブでやるというのは、自分たちがどこから出てきたのかを表明しているような気がしていたんですが」
野田「いまでもリスペクトがあるんだろうけどね。でも彼は、もうあの場所には戻れないんじゃないのかな。マウント・キンビーにしてもそうだけど」
河村「その周辺のアーティストで言えば、アントールド※もテクノとかインダストリアルとか、別の方向に行きましたね。ただ、彼のレーベル、ジェイムズ・ブレイクの作品もリリースしていたヘムロックは最近復活して、そちらはしっかりダブステップでしたが」
野田「そんななかで、ジョイ・オービソンが初心を忘れずに、デビューした頃から一貫している姿をこのアルバムで見せたっていうのはデカいんじゃないかな」
河村「なるほど。ブレていないと」
野田「そう。ブレなかった。本当にこのスタイルが好きなんだろうね。河村先生は厳しいことを言っていたけど、俺はすごく好きで、素晴らしいアルバムだと思います(笑)」
河村「いやいや(笑)。アルバムとして、すごくいいですよ。ただ、いままでシングルでインパクトのある曲ばかりを出していたことも僕としては重要なので、それとの比較での印象です」
野田「こういうDJやプロデューサーがアルバムを出して失敗する例って、けっこうあるじゃん。だから、アルバムは壁だったと思うけど、直球でいいなと思った。ただ、タイトルに〈vol. 1〉とつけたのだけはいただけないな」
河村「(笑)」
野田「〈vol. 2〉があるってことを言っちゃっているから、そうじゃなくて〈これなんだ〉って言ってほしかったね。でも、ジョイ・オービソンはきっとそういうタイプじゃないんだろうね。〈『Timeless』※みたいなアルバムは作っちゃいけない〉ってレイ・キースに言われたのかもしれない(笑)」
河村「〈あんな壮大なアルバムを作ったら戻れなくなるぞ〉って(笑)」
野田「〈もっとフロアに近い音のアルバムを作れ〉ってね」