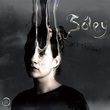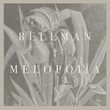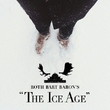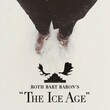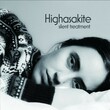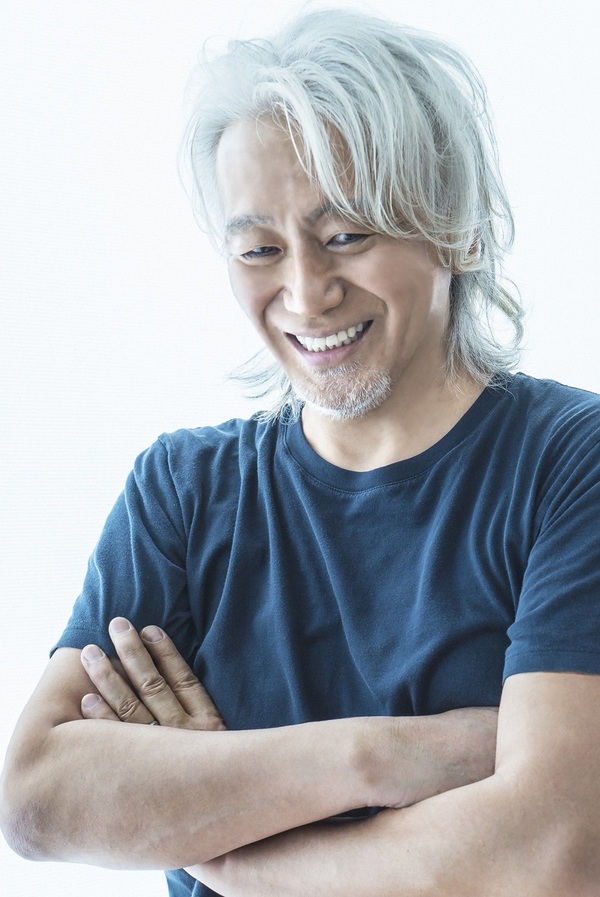クラシック~現代音楽に接近
『Átta』はまさにそのような作品になっている。本作ではビートは“Klettur”や“Gold”“8”といった楽曲でスパイス的に(だが効果的に)使用されているのみだ。そして音楽に浮遊感をもたらすために、彼らは、ロンドン・コンテンポラリー・オーケストラ(以下LCO)や長年のコラボレーターであるブラッスガット・イ・バラを招いている。ここではLCOに注目したい。LCOは近年、エレクトロニック・ミュージシャンのアクトレスやパウエル、マシュー・ハーバートらとの越境的なコラボレーションを通じて、オーケストラというフォルムのポテンシャルを拡張させているグループ。彼らの壮大かつ繊細なストリングスが『Átta』全編を覆っている。
先行曲“Blóðberg”の、寄せては返すさざ波のごときストリングスと呼吸を合わせるように歌う、ため息のようなヨンシーのヴォーカルは、美しく切ないエモーションを見事に演出している。このヨンシーのヴォーカル・スタイルは『Átta』全体で貫かれており、“Skei”や“Mór”のような壮大な楽曲のなかでは、彼の声はストリングスのなかに埋め込まれているかのようなミキシングが施されている。そうした音処理も本作の浮遊感のひとつの要因と言えるだろう。
また、『Átta』のアンビエント的な側面も触れずにはいられない。先述したように本作はリズム/ビートを意識させる要素が少なく、アンビエントなサウンドに接近している。同様に本作のストリングスもメロディーが前面に出るというよりは抽象的なスタイルだ。『Átta』がこうした音作りになった理由としては、昨今のヨンシーのソロ活動(2021年の『Obsidian』や2022年の『Sounds Of Fischer Vol. 1』)が、アンビエント色の強いものであることも影響しているのではないか。その方向性がオーケストラと出会うことで産まれたのが『Átta』の透明で荘厳な美しさであると言えよう。
本作にプロデューサーとして参加しているポール・コーリーはニコ・ミューリーやヴァルゲイル・シグルズソンなど、アイスランドのレーベル、ベッドルーム・コミュニティー周辺のアクトと仕事をしてきたプロデューサー。キャリアを通じてクラシック~現代音楽を他ジャンルの視点から解釈する知見を培ってきた彼の手腕が『Átta』にも活きている。
そうしたサウンドでシガー・ロスが表現したかったことは何だったのか。ヨンシーは本作がコロナ禍やウクライナ情勢のもとで作られたことについて言及しており、制作中に〈世界は少し暗いと感じていたが、もしかしたら希望はあるかもしれない。闇があれば、光がある〉と感じたと述べている。混迷を極めるこの世界に、光を投げかけるためにはどのようなサウンドにすればいいかを考え、導き出されたのがこの『Átta』なのだ。この音に込められた世界への祈りに対して自身がどういうふうに向き合うかは、リスナーひとりひとりによって異なるだろう。けれども、それがポジティヴなものであることを願うばかりだ。
本文で言及されたシガー・ロスの過去作。
左から、99年作『Ágætis byrjun』(Smekkleysa)、2002年作『()』(Fat Cat)、2005年作『Takk...』(EMI)、2013年作『Kveikur』(XL)
シガー・ロスによる2020年のサントラ『Odin's Raven Magic』、ヨンシーの2020年作『Shiver』(共にKrúnk)、マシュー・ハーバート&ロンドン・コンテンポラリー・オーケストラの2023年作『The Horse』(Modern)