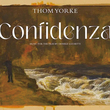うつむいた心にポジティヴな光をもたらす〈五月病バンド〉が迎えた変化の時――〈19200〉を繰り返す日々に刻んだその生き様とは?
誰が言い出したか、ネット上で付けられた呼び名は〈五月病バンド〉。メンバーも当初は〈中傷か?〉と思ったそうだが、実は〈五月病に効く〉という意味だったため、その後はみずから使用するようになったという、アノニマスさんも時にはいいことするね、というお話。確かに言い得て妙で、平田勝久(ヴォーカル/ギター)の硬質な歌声と尖ったギター・サウンド、深く沈み込むような空気感のなかには、うつむいた心に強く訴える何かがある。
「僕は皮肉の塊だと思うんですよ。〈元気出そうぜ〉と歌われても、お前は元気だろうけど俺は元気じゃないし、と思ってしまう人間なので。それよりも、何とも説明できない、暗くまとわりつくような音楽に救われることが多かったんですよね」(平田)。
平田のフェイヴァリットはシガー・ロス。ほかに4人の共通点としてレディオヘッド、コールドプレイなど重厚なUKロックを挙げているように、これまではダークなミッドテンポの曲調が多かった。が、新作ミニ・アルバム『19200』には、強烈な熱量を放つアッパーなロック・チューンがズラリ。バンドは変化しつつある。
「〈暗い〉と言われても、誰かに光を与えるポジティヴなアルバムを作りたかったので。サウンドも練りに練って、歌詞もちゃんと聴かせられて、うまくバランスが取れたと思います」(中井真貴、ベース)。
「ライヴで映える曲ばかりだと思います。そこに1曲インストを挿むことで、reading noteらしさが強く出ましたね」(平郡智章、ドラムス)。
そして〈五月病バンド〉の真骨頂である歌詞の世界。逃げ場のない競争社会への疑問をぶつけた“エクストラタイム”や、〈繋がり〉を強調する流行りの音楽への不信を露にした“clap hands”など攻撃的なテーマの一方で、〈もう逃げたりしない〉とつぶやく“なにもない部屋”、いつかは消えてしまう自分の儚さを見つめた“呼吸”など、鋭くも美しい内省的な言葉が光る。そこに作為の跡はない。
「“呼吸”の歌詞が送られてきた時には泣きました。これもreading noteらしさが詰まった1曲だなと思います」(鈴木政孝、ギター)。
「苦しい曲は、苦しまないと書けない。融通が利かないんです。大量生産に向いてない(笑)。でも音楽は音を楽しむものだけど、バンドはメンバーの生き様を見せるものだと思うので。これからも作り方は変えないです」(平田)。
『19200』とは、人間(男性)が一日にするまばたきの平均回数。「〈19200〉を刻めたということは、1日をちゃんと生きれたということ」(平田)という、新たなステージを見据えたreading noteの決意表明だ。注目してほしい。