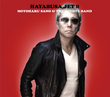民謡はひとつの枠で括れない
――まず耳を惹きつけるのは、アレンジ面における自由度の高さですよね。そこら辺が、元来民クルが備えているいかがわしさの向上ぶりと比例しているのが素晴らしい。
田中「やっぱりそれも重ね録りしながらいろいろトライできたことが大きい。でも自分たちとしては、やってることがそんなに変わった気がしないんですけどね」
――先だって行われた〈Peter Barakan’s LIVE MAGIC! 2023〉のステージを拝見しましたが、音楽ショウとしてのエンターテインメント性が著しくアップしていたことにも目を瞠った。
田中「ヨーロッパツアーなど海外でライブを重ねるなかで、お客さんとのコミュニケーションや、オーガナイザーやエージェンシーのアドバイスなどからバンドとして多くのことを学んだ部分が反映されているのかもしれません」
――もし民謡をストイックに突き詰めようとすれば、否が応でも本物感を目指さざるを得なくなるところがあると思うけど、そのあたりはどうですか?
田中「自分たちの場合は民謡という大衆音楽のある種の猥雑さに引かれている部分もあるので。いかがわしさとか胡散臭さという部分って、メンバーみんなが好きなところなんじゃないですかね。なんかこう、ストレートに行くのを避けるというか。
ただ、お客さんは、みなさんいろんな見方をしてくださるというか、聴いている方にもいろんなタイプがいらっしゃって、それこそおじいちゃんおばあちゃんから元気に飛び跳ねる子供まで、いろんな角度で刺さるポイントがあって、そのなかで〈いかがわしさ〉や〈エキゾ〉の部分に反応してくれる方もいらっしゃる。多面的な部分があるのも民クルらしさかもしれません」
――こんなおもしろエキゾな音楽を奏でるバンドが日本にいるとは!っていう出会い頭の衝撃がいまだに残っているもので(笑)。とにかく今回はアプローチ方法が多彩になった感があります。
田中「1曲目の“佐渡おけさ”とかアンビエントな感じを出しながらフリーフォームな部分もたっぷり入れたりしているし、コーちゃんが作った“貝殻節”みたいにサルサで思いっきり踊れる感じがあったりとか、曲によって音作りのテーマがハッキリと異なっていますね。
あと、民謡はすごく歴史が長くて、労働の場で歌われていた曲がやがて地域の有名な民謡になったり、江戸時代にはお座敷などで芸者さんがうたう端唄が小唄になったり、遊び場での流行り歌になったり、あるいは豊作を祝うために祭りでうたわれた曲もあったりして、いろんなタイプの曲がある。それぞれのスタイルに合わせるってわけじゃないですけど、ひとつのグルーヴで突き進むものもあれば、展開がいろいろ変化していくメロディアスな曲もあるし、そういう多様さがアレンジの幅広さに直結している。民謡とはこれ、と、ひとつの枠で括れるものじゃない。
僕らも〈民謡+ラテン〉とは謳っていますけど、そこはプロモーションのキャッチコピーに過ぎなくて、ある意味もはやそこからもはみ出てしまっているところがある」
――いい意味での捉えどころのなさも魅力ですよね。
田中「だんだん何を聴いているのかわかんなくなってくる人も多いんじゃないかと(笑)」

民クルなりのリズムのなまり
――今回は多彩な要素がしっかりと煮込まれた結果、風味豊かな極上のスープが出来上がっています。
田中「ファーストの頃は、この曲のこのフレーズはここから持ってきました、というようなわりと元ネタがハッキリわかるシンプルな作りになっていましたが、今回はネタがちょっと判別しづらいぐらいもっと踏み込んだ作りとなっていて……」
大沢「ミックスするにあたっての決まったやり方ってなくって、試行錯誤しながらいろんな要素を混ざり合わせてみたら、こういう幅広い世界になってしまったというだけで。でも、ジャンルは?となると、どれも〈民謡〉ってことになるっていうね」
田中「どれもこれもひとつ民謡ってことで収めていただければ、ってことです(笑)」
大沢「本格的にサルサやルンバをやっている感じもないですし、ラテンやカリブの音楽が好きなメンバーが多いのでそちらの方向には行きがちですが……。基本的には好きなことを楽しんで演奏する、そのスタンスは大事にしていて」
田中「民謡をベースにそれらをやることで、とやかく言われなくなるところもある(笑)」
――(笑)。
田中「本当だったら怒られちゃいそうになるところを、僕たちこういう感じなんで、という姿勢を示すことで各方面の問題がオールクリアになるという(笑)。
ただ、民クルらしいリズムっていうことでは、ドラマーがいないラテンパーカッションによる編成というのも大きいと思います。その影響でリズムが歌に寄り添っていく傾向にあるというか、キックでリズムを刻んでいかずに余白を作るというか、けっして歌を殺さない自由度の高さが生まれる。そこら辺がちょっとうまくハマっていると思うし、僕らなりのリズムのなまりを生み出しているように思う」