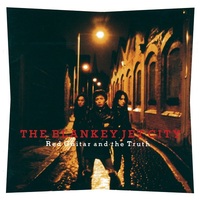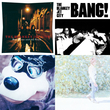発表されるのと同時に大きな話題になった、BLANKEY JET CITYのサブスク解禁およびオリジナルアルバムの再発。2024年7月28日に全カタログの配信がついにスタート、往年のファンは歓喜に沸き、彼らのレガシーを初めて知る若い聴き手は衝撃を受けている。数十年越しのブランキー旋風が巻き起こる今、BLANKEY JET CITYとはどんなバンドだったのかを振り返りたい。時代を並走した音楽評論家・小野島大が、出会いの衝撃から終焉の意味合いまでを綴った。 *Mikiki編集部
解散から24年、きちんと評価される日が訪れた
BLANKEY JET CITYの全10アルバムの音源がついにサブスク解禁された。同時にアナログ盤も発売。そのうち7作は初アナログ化だ。待ちに待った待望の再発プロジェクトである。
ブランキーは長いことサブスク未配信で、CDも品切れ状態が続いていた。DL配信は細々と続いていたしYouTubeに断片的な映像等はあるが、現在の一般的なリスニング環境を考えれば、新たなリスナーがブランキーの音源に接することはきわめてハードルが高かった。これまでサブスクでの配信がなかったのはさまざまな事情があるようだが、ともあれ結成して37年、デビューして33年、そして解散して24年というタイミングでやっと彼らの音楽がきちんと評価される日が訪れたことを素直に喜びたい。
ロックの修羅道を生きる3人の登場という事件
ブランキーは浅井健一(ボーカル/ギター)、照井利幸(ベース)、中村達也(ドラムス)の3人。名古屋で友人同士だった3人が1987年に東京で結成した。バンドブーム最中の1990年、当時人気を集めていたテレビ番組「いかすバンド天国」に出演、俄然注目を集める。中村はザ・スターリン、THE STAR CLUB、the 原爆オナニーズなど日本の大物パンクバンドのメンバーを歴任するなど知る人ぞ知る存在だったが、ほかの2人は当時ほとんど無名だった。
筆者が初めてブランキーを見たのも同番組だったが、なにげなくテレビをつけた瞬間、その姿に目が釘付けになった。曲はのちにファーストアルバム『Red Guitar and The Truth』(1991年)に収録された“狂った朝日”だったが、抜き身のナイフを突きつけるような異様な迫力と、ナマの感情を一切の虚飾なく表現する歌詞の切迫したリアリティ、とんでもなく高い演奏力に度肝を抜かれた。ほかのバンドとはまるで次元が違った。バンドブームも末期、それまでのシンプルで明るく楽しいだけのロックバンドたちとは全く位相の異なる3人組の唐突な出現はとんでもない衝撃であり、ひとつの事件だったと言える。
タトゥーだらけの逞しい肉体と、黒の革ジャン、革パンという見るからにコワモテの不良たち。パンクやロカビリー、ニューウェーブなどを消化した独自の攻撃的なロックンロール。しかしそんな男たちは、飼っていた猫の死に涙を流し、おばあさんの編んでくれたセーターに安らぎを見いだし、ノイローゼになった友人に冷たい態度をとってしまった自分を責め続けたりする、繊細で壊れそうな優しい少年の心情を、驚くほど率直でストレートな言葉で歌う。ほとんどの曲を作り歌う浅井の一見か細く弱々しいが強靱な芯の通ったボーカル、グレッチのギターから紡ぎ出される表現力豊かなギタープレイと、照井・中村のパワフルなリズムセクションが相乗したブランキーのバンドサウンドは、聴く者の心をいきなり鷲づかみにするような鮮烈なインパクトがあった。彼らの肉体に掘られたタトゥーの数々は、退路を断ち、平凡な日常を切り捨てロックの修羅道を生きる決意の表れだった。