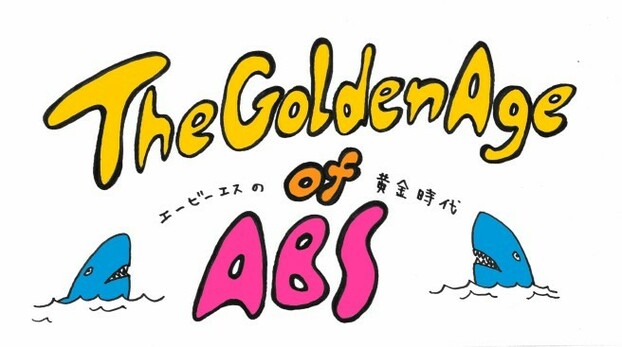
温泉に行きたい。オフシーズンの平日に行くのが最高だ。人の気配のない温泉街を歩いていると、湧き上がる気持ちで突然叫びたくなる。地元の老人しか入っていないガラガラの湯に浸かってみる。自分の知らないところでも毎日温泉は出続けていることが感慨深い。誰が気にしていなくても世界は関係なく動いていると思うと、希望を感じられる。私は生きているのだ、と実感できる。
友人の女性になかなかの温泉通がおりまして、その方などは温泉に入った時のフィーリングを指して「ガイアを感じる」と表現しています。さすがになんかヤバイだろと思うも、考えてみれば、大して世に必要とされてるわけでもないオルタナティブな音楽にいまだにしがみついてコチャコチャやっている自分も、はたからみたら信者みたいなもので十分ヤバイ気がするし、別に人のことは言えない。
有名無名関わらず全国さまざまな温泉を攻めてきた彼女だが、なかでもすごいのは、もはや山の中腹から勝手に湧き出て溜まっている温泉だとか、かつては営業していたがもう閉まってしまった施設で今でもこんこんと湧き続ける温泉だとか、そういった、人の手に管理されていない〈野良湯〉までディグしている点である。
当たり前だけど、そうなってくるとお湯が適温でなかったり、ちゃんと浸かれるほどの量が溜まっていなかったりするわけだが、彼女に言わせると、様々な鉱物の結晶が溶け込んだそのお湯の成分を肌で感じて吸収することが一番大事なのであって(飲んだりもする)、肩まで浸かってあたたまりたいとかほっこりしたいとか、そういうことではないそうである。もはや求道者だ。
そんな「ハードコア温泉道」を、彼女は当時勤めていた会社の社長と二人で巡っていたそうなのだが、この社長というのがこれまた、お湯が湧いていると見れば、たとえそれが水たまり程度の量であってもところ構わず裸になって飛び込んでしまうようなかなりの温泉狂いだったとのことである。温泉ハードコア独自の情報ネットワークを駆使した二人の珍道中は、地元の人しか知らない山奥の掘建て小屋から洞窟の中にまで至り、もはや〈インディ・ジョーンズ〉さながらの温泉巡礼であった。
と、話を聞きながら、「そんな山奥の野良湯で男女ふたりっきりとか……エロそうだな……」と俺は思った。だが実際はまったくそんなことはなかったらしく、というのも「混浴だからといっていかがわしい行為をすることは湯を穢す冒涜行為である」という強い意識が二人にはあったそうで、したがってセクシーな催しは一切行われなかったのだ。ここで重要となるのは「我々はお湯に入らせていただいている」「大地からの恵みを施されている」という〈もらい湯の精神〉である。
しかしだからといって、その社長がよほどの堅物なのかというとまったくそんなことはなく、むしろ温泉以外では、女遊びは激しいわ、ややこしい薬を常用するわでろくなもんではなかったらしい。従業員の大半がなんらかの中毒者であった会社に嫌気がさし、彼女は会社を辞めた。

































