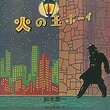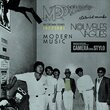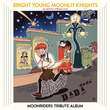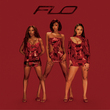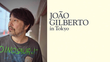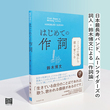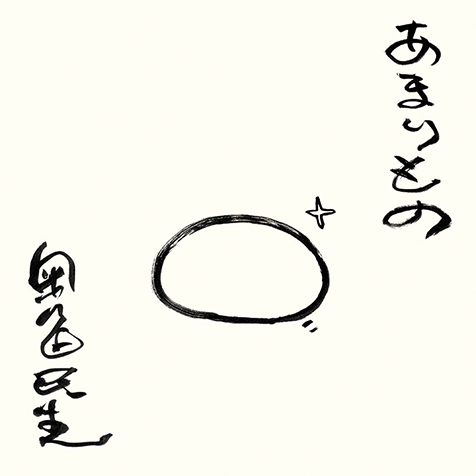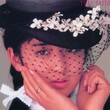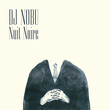原曲のイメージから離してカヴァーするのが流儀かもしれない
——今回お二人はムーンライダーズのトリビュート・アルバム『BRIGHT YOUNG MOONLIT KNIGHTS』に参加されていますが、選曲の経緯を教えてください。曽我部さんは“夏の日のオーガズム”をカヴァーされていますね。
曽我部「この曲は、当時から大好きだったムーンライダーズの曲なんですよ。12インチで買ったんですけど、とても良い曲だなあと思って。ニュー・オーダーみたいな感じもあるし(笑)」
——確かに(笑)。12インチで聴くと、ニュー・オーダーの“Blue Monday”的な雰囲気がありますね。カヴァーの際のアレンジのポイントは?
曽我部「カヴァーするときは、まず弾き語りで人前でも歌えるぐらい練習するんですよ、自分の曲だと思い込めるぐらいに。そこからコード感とかを自分が好きなように変えたりして、じゃあこれを人に聴かせるためにはどんなふうにレコーディングしようかと考えるんです」
澤部「へえー!! これ、最高のカヴァーですよ。原曲のイメージから離してカヴァーするのがムーンライダーズのトリビュートとしてはあるべき形なのかもしれませんが、曽我部さんのカヴァーはそれをやりつつ、ちゃんと原曲の良さも芯に残している。それって凄く難しいことだと思うんですよ。もう流石としか言いようがないですね」
——澤部さんは“いとこ同士”を選んでますね。
澤部「すっごく悩んだんですよ。いままでトリビュートに参加するときは、〈もう一回この曲にスポットを当てたい〉という気持ちで、だいたい他の人が選ばないような曲を選んできたんです。でも今回の参加アーティストを見せてもらったら、若いバンドが中心だったので、これは多少どっしり構えてないとまずいなと思って。ほんとだったらやりたい曲が1曲あったんです。2001年の『ダイア・モロンズ・トリビューン』とに入ってる、くじらさん(武川雅寛、ヴァイオリン/ヴォーカル)作の“俺はそんなに馬鹿じゃない”。でも、ここはどっしり構えてみようと吹っ切れたとき、“いとこ同士”をやってみてもいいんじゃないか?と。あえて王道を選んでみたらどうなるんだろう?みたいな気持ちもあって」
曽我部「澤部くんは正統派のアレンジできたね」
澤部「86年に出た『THE WORST OF MOONRIDERS』というライヴ盤があって、そこに入っている“いとこ同士”がすごく好きなんです。それと同じように、無骨なロック・バンド然とした感じで“いとこ同士”をやるというのは挑戦する価値があるなと思った。普段トリビュートとかだと一人で多重録音することが多いんですけど、今回はいまのバンド・メンバーを呼んで、〈この曲をやってみようと思うので、皆さん知恵を貸してください〉という感じで進めました」
——おもしろいですね。曽我部さんは自分が好きな曲を自分流にやって、澤部さんは全体を見ながら選曲してライダーズの魅力をくまなく見せようとする。
澤部「そうなっちゃうんですよ。“俺はそんなに馬鹿じゃない”をやろうと思ったのも、最初、武川さんの曲がなかったからなんです。でも、空間現代が(武川雅寛作曲の)“僕は走って灰になる”をやると聞いて。それで“いとこ同士”にしたんです」
曽我部「影のプロデューサーだね(笑)」
——バンドへの愛が溢れてますね(笑)。そんなお二人にとって、ムーンライダーズの魅力とはどんなところですか?
曽我部「まず、歌詞は大きいよね」
澤部「そうですね。ムーンライダーズはその時代の最先端の音を追ってきた人たちじゃないですか。だから音像とかが古くなっちゃってるのも結構あったりすると思うんですよ。それでも、いまも聴けるのは歌詞なんだろうなと思います。言葉は古くならないというか」
——澤部さんから見て、ムーンライダーズの歌詞の魅力は?
澤部「そうですね……。歌詞を書く人が6人いるんで、それぞれの魅力を説明するのは、ちょっと難しい部分もあるんですけど、例えば70年代から80年代にかけての(鈴木)博文(ベース/ヴォーカル)さんの歌詞は凄いと思いますね。80年代の“DON’T TRUST ANYONE OVER 30”を筆頭に、70年代には“さよならは夜明けの夢に”とかもありますし」
曽我部「博文さん、王道でロマンティックな歌詞を書くよね」
澤部「そうなんですよ。で、最初の頃は王道でロマンティックなんだけど、だんだんねじれてくるじゃないですか」
——最初は翻訳文学みたいな虚構性の強い歌詞だけど、徐々にヘヴィーになってきて、歌詞というより詩に近くなってきますね。
曽我部「『青空百景』(82年)あたりで変わった気がするね。このアルバムはヨーロッパ的な退廃とかニューウェイヴ的なものをあんまり見せてないから、あまり装飾がない詩になっている気がする」
澤部「“くれない埠頭”や“物は壊れる、人は死ぬ、三つ数えて、眼をつぶれ”とか」
曽我部「そう。これまでの記号的なイメージが、このアルバムにはあまりない気がするんだよね。もうちょっと哲学的というか、観念的というか」
澤部「僕が“DON’T TRUST ANYONE OVER 30”を初めて聴いたとき、10代後半くらいだったんですけど、30歳を越えた人たちが、自分達が若い頃に言っていた〈30歳以上を信じるな〉というフレーズを歌っている、そのヒリヒリした感じがバシバシきたんですよ。大学に行っても全然おもしろくなくて、人生がいちばん上手くいってない時期だったんです。学校が本厚木にあったんですけど、小田急線に乗りながらあの曲の〈冬の海まで車をとばして 24時間 砂を食べていたい〉という歌詞を聴いて、このまま僕は小田原まで行って海を見て家に帰ることもできるんだなぁと思ったりして。すごく響きましたね」
曽我部「その感覚、すごいね。俺が17、18のときには、まったく別のものを求めてた。海といえばフリッパーズ・ギターの〈海へ行くつもりじゃなかった〉(89年)やベン・ワットの『North Marine Drive』(83年)とか。寂しさのシミュレーションというか、もうちょっと虚構性のあるものを求めていたから。この曲はガチでしょ?」
澤部「鬱っぽいですね」
——同じアルバムには“何だ?この、ユーウツは!!”という曲もありますね。
曽我部「若いときに聴いたときは、そのガチな感じが苦手だったんだけど、いま引きこもっているような若い連中には、ベン・ワットより“DON'T TRUST ANYONE OVER 30”や“なんだ?この、ユーツは!!!!”のほうがガツンとくるかもしれないね」
——そういう時代、ということですか?
曽我部「そういう時代。だからこそ、再評価されて良いんじゃないかな」
バンドという生き物の一生を見せている
——では、これからムーンライダーズを聴こうと思っている若い世代に、お薦めのアルバムはありますか?
曽我部「初期のアルバムは記号性が高いし、アルバムごとにサウンドも違うんで『青空百景』(82年)や『アマチュア・アカデミー』(84年)、『アニマル・インデックス』(85年)あたりが入りやすいと思いますね」
——80年代の作品ですね。
曽我部「その頃だとサウンド的にも取っ付きやすいと思う。個人的には『アニマル・インデックス』がいちばんライダーズっぽいと思うんだよね」
——それはどういうところが?
曽我部「これはちょっと他のアルバムと違う感じがする。メンバーそれぞれが曲を書いて録音して、それを慶一さんがまとめるという方法だったことは後で知ったんだけど」
澤部「でも良い曲が多いんですよね」
曽我部「そう、“悲しいしらせ”や“犬にインタビュー”が大好きなんですよ」
澤部「“駅は今、朝の中”“僕は走って灰になる”“夢が見れる機械が欲しい”あたりも良い」
曽我部「でも、バンドとしてはこの先がないような感じがあるというか。個人の集合体みたいなアルバムだよね」
澤部「バンドの崩壊をひとつの方法論としてアルバムを作っているというか」
——メンバー全員が曲を書けるというのも、ムーンライダーズの大きな特徴ですね。
曽我部「それって、バンドを持続させるためにすごく効率の良いことだと思うんですよ。普通のバンドは力の強いメンバーがいて、その人が引っ張っていく。ムーンライダーズの場合は、みんなの力で動いている機械みたいな気がして。ひとり調子が悪くても他のメンバーがフォローできる。僕にはたぶん無理ですけどね。そういうやり方だとクォリティーが保証されないじゃないですか。〈大丈夫!〉ってハンコを押せる基準がないわけだから」
——そういうシステムを導入しているからこそ、個人作業をまとめたものがバンドのアルバムとして成立するんでしょうね。そのためには、メンバー全員が〈ライダーズらしさ〉を共有できていることが重要だと思います。だからこそ曽我部さんをはじめ外部の人が歌詞を書いても、バンドが演奏すればライダーズの曲になる。
曽我部「慶一さんの底なしの許容力っていうのは、一緒に仕事をしてみて本当に凄いと思いましたね。誰とやっても、何をやってもOK。ノーがない状態。懐が深すぎます」
——あれだけ個性が強いメンバーが揃っているバンドだと、それくらいの許容力や柔軟性がないと長続きしないでしょうね。では澤部さんのお薦めの初ライダーズ・アルバムは?
澤部「僕は『ムーン・オーヴァー・ザ・ローズバッド』(2006年)かな。ムーンライダーズのハードな部分もソフトな部分も両方あるんで。まだムーンライダーズを聴いたことがないスカートのリスナーが聴いたらどう思うかな?と、すごく興味がありますね」
——バンドとして完熟した後期の名作ですよね。
澤部「そう。サウンドもそれぞれのソングライティングも完熟していて、いちばん良い時期だと思うんですよ。そこから少しずつ遡って聴いていったら、ムーンライダーズというバンドが見えやすいのかなと。今回の〈in CROWN YEARS〉 に収録された6作は、それぞれ時代を反映させたポップな作品だとも思うので、このボックスから順に聴いていくのも絶対に楽しいと思います。いまわからなくても絶対にいつか必要になりますよ」
——なるほど。では最後に、お二人がムーンライダーズから影響を受けた、あるいは刺激を受けたところを教えてください。
澤部「うわあ、難しいなあ。いろんな影響の受け方をしているので一概には言えないんですけど、歌詞はもちろん曲にも影響を受けていて。岡田(徹、キーボード/ヴォーカル)さんのとても理論的に構築している楽曲や、慶一さんの〈なんでこんなに正反対の要素が一緒の曲に入ってるんだ!?〉みたいな力技の曲とか、いろんな面が一枚のアルバムに入っている。そういう、バンドが持つべき多様性みたいなものには、ずっと憧れてますね。自分一人なのに〈バンド〉と言って始めちゃった自分としては、ムーンライダーズみたいに何人ものメンバーが曲を書いてくるようなバンドをやれていたら…と思うことがよくあります」
曽我部「いまから増やせばいいんだよ(笑)」
澤部「曲が書けるメンバーを(笑)」
——曽我部さんはいかがですか?
曽我部「僕はやっぱり、バンドの人生というものをちゃんと見せようとするところですよね。休んだり、あるときはすごく変わってみたり。それを丸ごと見せてくれるのはほんとありがたいと思っていて。ストーンズもそうだけど、そういう腹の括り方があるバンドってあまりいないですよね。その点ではっぴいえんどは真逆だと思うんです。彼らは作品を作るために集まった集合体だったと思うけど、ムーンライダーズは〈バンドなんだ〉というのがすごいある。バンドという生き物の一生を見せる。それって、彼らがいちばん下敷きにしたであろうグレイトフル・デッドと近いものも感じますね」
——なるほど、〈生き物〉なんですね。だから変化し続けた。いまは冬眠中ですけど。
曽我部「そういえば、いまのうちにアナログは買っておいたほうが良いと思う。まだ中古盤屋で千円以下のものもあるけど、たぶん2017年には倍になると思うんで」
澤部「そうそう。確かに最近見なくなりましたねー」
曽我部「こういうこと言って高騰しちゃうとイヤなんだけどね(笑)」
ムーンライダーズからのお知らせ
Pied Piper House Presents 『火の玉ボーイ 40周年記念デラックス・エディション』『MOON RIDERS in CROWN YEARS 40th ANNIVERSARY BOX』『BRIGHT YOUNG MOONLIT KNIGHTS -We Can't Live Without a Rose- MOONRIDERS TRIBUTE ALBUM』発売記念 鈴木慶一+長門芳郎トークショー&サイン会開催決定!
2017年1月19日(木) 19時~ タワーレコード渋谷店 5F PIED PIPER HOUSE in TOWER RECORDS SHIBUYA 前特設スペース
出演:鈴木慶一、長門芳郎
★詳細はこちら
スカートからのお知らせ
スカート『静かな夜がいい』発売記念ワンマンライブ 〈(できれば)静かな夜がいい〉
2017年1月28日(土)東京・渋谷WWW
開場 17:30 / 開演 18:30
前売り 3,000円(ドリンク代別)
★詳細はこちら