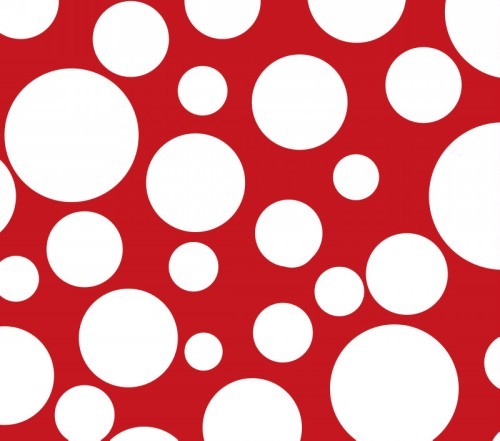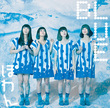アーバンギャルドが初のライヴ・アルバム『アーバンギャルド2016 XMAS SPECIAL HALL LIVE 天使 des 悪魔』を発表した。昨年12月17日に東京・渋谷区文化総合センター大和田 さくらホールで開催されたコンサートの音源を収録した本作は、11曲を収録した初回限定特別価格盤と、15曲入りのCDにライヴ映像を収めたDVDを付けた通常盤の2形態でのリリース。天使と悪魔の対決をテーマにしたライヴ・パフォーマンスからは、現代人が抱えるアンビヴァレンツな感情を表現してきたアーバンギャルドの本質が生々しく伝わってくる。ギター・ロックに歌謡曲、テクノ・ポップなどを融合させた彼ら独特のサウンドをよりリアルに体感できるのも、本作の魅力だろう。
今回はバンドをアジテートする松永天馬と、浜崎容子の2人にインタヴューを実施。ライヴ盤をリリースする意図やライヴへのスタンスを軸にしながら、イヴェントやフェスに重点が置かれるバンド・シーンや、マーケティングを重視した作品が増え続けるエンターテイメントの現状についてまでたっぷりと語ってもらっている。来年、10周年を迎えるアーバンギャルド。鋭い批評性に裏付けられたクリエイティヴィティは、ここにきてさらに精度を増しているようだ。
情報を制限したい
――まず、今回ライヴ盤を出そうと思った理由を教えてもらえますか?
松永天馬(ヴォーカル)「いまのリスナーって、ライヴの映像作品をコレクションはしたとしても、それを繰り返して観たりはしないのかなと思ったんですよね。それよりもCDのほうがプレイヤーに取り込んで、何度も聴いてもらえるんじゃないかなと。あとね、アーバンギャルドのライヴってすごく情報量が多いんですよ。演劇的なところとか、映像やMCを含めてひとつのステージにいろんな要素が詰まっているので、その情報を限定して、音だけで聴いてもらえる機会を作りたいという気持ちもありましたね」
――あえて音源だけでライヴを体感してほしい、と。
松永「はい。情報量が少なければ、受け取る側は想像力を使うと思うんです。ライヴ・アルバムには、まさにそういうおもしろさがあるのかなと。YouTubeとかだと映像と一緒に曲を聴くことになるので、受け取り方を限定してしまうと思うんですよ。もちろんすごく便利だし、曲を広めるうえでわれわれも利用していますが、良い音楽というのは本来、聴き手のなかで自然と映像が浮かんでくるものですからね。音や歌詞をじっくり聴くことで、その人の中で勝手に映像化されるというか。今回のライヴ盤もそういう楽しみ方をしてほしいですね。通常盤にはDVDも同梱していますが、選択肢として音だけでまず聴いてほしいです。アーバンギャルドのようなポップ・ロック、テクノ・ポップのバンドがライヴ盤を出すこともそんなにないかな、と思うんですが、実はわれわれのライヴは〈テクノ・ポップ〉という言葉からは程遠い肉体性もあって、ライヴ・バンドとしての側面も強くて。スタジオ・アルバムとは違ったアレンジもあるし、来年の10周年に向けて、さらにライヴを盛り上げていきたいという狙いもあります」
浜崎容子(ヴォーカル)「……情報を制限したいと言ってるわりに、この時点ですでに情報がめちゃくちゃ多いですね(笑)」
松永「確かに(笑)。もう一つ加えると、ジャケットもライヴを想像させないデザインにしているんです」
浜崎「普通はライヴ・カットを使いますからね」
松永「そう。それも〈音だけの印象を受け取ってほしい〉ということなんです」
――このライヴはどんなコンセプトだったんですか?
浜崎「〈天使と悪魔の対決〉ですね。天使が先攻、悪魔が後攻で、会場のお客さんやニコ生の視聴者のみなさんにどっちが良かったかを投票してもらって、勝ったほうがアンコールに登場するという内容で。どっちになるか最後までわからないという演出をしたライヴは初めてだったから、楽しかったですね」
松永「つまり〈自分vs自分〉ですよね。アーバンギャルドは分裂症気味と言いますか、ネガティヴとポジティヴ、自己肯定と自己否定がないまぜになっている表現が多い。その2つの側面を天使と悪魔になぞらえたのが、このライヴだったということです。あと、幕間の時間を使って僕のソロもやったんですよ。“詩人狩り”(2015年作『昭和九十年』収録)という曲を演奏したし、松永天馬vs松永天馬の1人フリースタイル・バトルもやりました」
浜崎「これ、誰が得するんだろう?と思って観てましたけどね」
松永「僕が得するんですよ!」
――1人でフリースタイル・バトルをやるっていう演出も、アーバンギャルドの解離性につながっているのかも。
松永「そうですね。現代人は何層ものペルソナを持っているし、〈自分〉というものが解離していると思うので。10年くらい前は〈ネットか現実か〉という単純な図式でしたけど、いまはTwitterとFacebookで人格が違うのはあたり前だし、Twitterのなかでもリアル・アカウント、裏アカウントに、恋人アカ、腐女子アカとか、4つくらい持ってたりするじゃないですか。アーバンギャルドもそれに近くて、一層だけで伝えるのは難しいんですよね」

――音楽的な側面で言えば、キーボードのおおくぼけいさんの存在は非常に大きいですよね。このライヴ盤でも素晴らしい演奏を披露されていて。
浜崎「よくぞ仰ってくれました! おおくぼけいがいなかったら、ライヴ・アルバムは出せなかったので」
松永「そうかもしれないですね。ここ2年くらいでライヴでの演奏も向上したし、メンバーそれぞれが見せ場を作れるようになったんですよ。それがライヴ・アルバムを出そうという気持ちにつながったというか。そのきっかけはやっぱり、彼の加入だったので。まず、演奏に対する意欲が高まりましたからね」
浜崎「おおくぼさんはすごくライヴを重視しているんですよ。ライヴでどう聴かせるかを常に意識しているし、リハのときもアンサンブルとかヴォーカルの引き立たせ方、〈ここは楽器隊が一丸になったほうがいい〉みたいなアドバイスをくれる」
松永「スタジオ・アルバムとライヴでの表現の違いもしっかり考えてますからね、彼は」
浜崎「そうだね。この前も対バンしたバンドのキーボードの方に〈鍵盤の人、すごいですね〉って言われたんですよ。〈最初、音源を流してるのかと思いました〉と。私もその日のリハで、おおくぼさんに〈今日は特別に上手いね〉と言ったところだったんですけど、同じキーボードの人からそんなふうに言ってもらえたのが嬉しくて」
松永「以前、彼が在籍していたザ・キャプテンズもめちゃくちゃライヴをやるバンドだったから、そこで体得したことも大きかったんだと思います。対応力もすごいですからね。(ライヴ中に)〈ここで着替えるから、ピアノ・ソロ5分よろしく〉みたいなことを言っても……」
浜崎「即対応してくれるっていう」
松永「僕がライヴで朗読をするときも、テキストの内容に合わせて即興で演奏してくれて。アーバンギャルドの演劇的な要素にも呼応した人物だと思います。一方、ギターの瀬々信はメタル的な側面を持っているし、異色の組み合わせですよね。さらに浜崎さんは繊細な声色だし、僕みたいな本来音楽的ではない人間もいるし(笑)、サウンド的にはテクノや打ち込みの要素もあって。それぞれに突出していて、歪みがあるんだけど、それがライヴという場でひとつの塊になる」
――極めて過剰だし、独創的でもあって。こんなアンサンブルを体現しているバンドはほかにいないと思います。
松永「嬉しいですね、そう言ってもらえると。演出に関してもまだいろいろとやりたいことがあるんですよ。血の雨を降らしたり、ドローンを使ったり。プロジェクション・マッピングもそうですけど、技術はどんどん進歩しているじゃないですか。ただ、予算の関係で実現できないことも多くて……。僕がやりたいことをやるために、みなさんライヴに来てください(笑)!」

AIの電源を早く落とさないと
――当時に比べてライヴに対する考え方も変化していますか? この10年くらいでアーティストの活動の重点はパッケージからライヴへと移り、その影響はアーバンギャルドにも及んでいると思うのですが。
松永「もちろん、われわれもライヴのおもしろさは追求しています。僕はもともと演劇をやっていたので、アーバンギャルドでもたまにセリフを入れることがあって。そこはほかのバンドとは違うのかなと。ただ、スタジオ・アルバムの可能性もすごく信じているんですよ。スタジオ・アルバムを作ることでアーティストの内面は深化されると思っているので。いまはスタジオ・アルバムがないがしろにされているとまでは言わないですけど、どうしても昔とは変わらざるを得なくなってるじゃないですか。その時代や、その時点におけるアーティストの作家性を固定して閉じ込められるのがアルバムだと思うんですが、近年はそこでフィックスするのではなく、作品をネットで育てるという側面もあって。リスナーがSNS上でコメントしたり、シェアすることによって、作品に別の光を当てるというか」
――〈所有から共有へ〉ということも言われますからね。
松永「そうそう。もう1つはコミュニケーションですよね。例えば現代美術の世界でも、観賞者と作者や、観賞者同士のコミュニケーションをテーマにした作品がここ10年ぐらいで急増した気がします。先日、森美術館でN.S.ハルシャの展示を観てきたんですが、お客さんが床に寝転がって天井に設置している鏡のなかで絵と一体化するというものがあって……そういった作品が増えている。それはそれでいいですよね。でも、スタジオ・アルバムはもう少しリスナーを拒絶するようなところがあってもいいのかな、とも思ったり。……すみません、しゃべりすぎました。浜崎さん、どうぞ!」
浜崎「いいよ、ずっと喋ってても」
松永「いやいや。どうですか、ライヴについては」
浜崎「そうですね……。ライヴやイヴェントが儲かるぞってことになって、わけのわからないフェスが増えてますよね。まあ、私たちも〈鬱フェス〉というわけのわからないものをやってますけど」
松永「やってますね(笑)」
浜崎「それによって音楽に対する気持ちが分散しているというか、希薄になってると思うんですよ。以前は〈音楽によって救われる〉という聴き方をしていた人も多かったけど、いまはそうじゃなくて。もちろん音楽がなくても生きていけるんだけど、音楽に対する欲望が薄れているんじゃないかなと。それは寂しくもあり、危険でもあると思うんですね」
松永「危険ですよね。少なくともわれわれの業界にとっては」
浜崎「音楽だけじゃなくて、本や映画もそうですけど、芸術は人間の栄養素だと思うんです。もっと積極的に摂取していかないと感情は育たないし、それを表現することもできないですからね。だから〈ヤバイ〉とか〈マジすごくない?〉みたいなことしか言えなくなってるという」
松永「〈優勝〉とかね」
浜崎「そうそう(笑)。芸術やエンタメを含めて、すべてが身近になりすぎて、酸素みたいな感じになってる気がして。ある日、それがなくなったらどうするんだろう?って思っちゃいますね。音楽だっていつでもネットで聴けますから」

松永「Apple Musicなんかもそうですよね――アレンジしているときに〈こんな感じで〉ってサンプルを聴かせたりできて便利なんですが――あれは悪魔の機械ですね。便利すぎて、人をダメにします」
浜崎「そうだね」
松永「ああいうものを使っていると、音楽のBGM的な側面が強くなると思うんです。商業施設で流れているのと同じというか」
浜崎「だから〈空気〉なんだよ」
松永「歌詞をしっかり聴いて風景を想像することもなく、ただシームレスに流れるだけという。そうやって音楽がシェアされていくことで、音楽を作る人に対する尊厳や作り手の創造性みたいなものも追いやられているのかなと。あと30年くらいしたら、芸術もロボットで補完されるかもしれないですからね。AIに小説を書かせて、文学賞を取れるかどうかという実験も始まってるし」
浜崎「AIの電源を早く落とさないと。気付いたら機械に乗っ取られてた、という可能性だってありますよ」
松永「予測検索もそうだよね。Amazonの〈オススメ機能〉に顕著だけど、好きなものを自分でではなくて、機械に決めてもらってる感じもありますから。だからこそわれわれは人間だからこそできることを追い求めるべきだし、リスナーにも〈物事を自分の頭で考えて決める〉という意識を持ってほしいんですよね」
――マーケティングありきのモノ作りも問題なのかもしれないですね。
松永「そうですね。あらかじめリスナーの反応を想定しているというか」
浜崎「〈泣ける〉って前もって言っちゃいますからね」
松永「〈笑える〉〈泣ける〉ってね。特に邦画はキャスティングとか主題歌、予告編を含めて、この映画はこういうマーケティングで作ったんだなというのが丸わかりなので。僕としては、もう少し観客の解釈に委ねるものを作ってほしいんですよ!」
――評論の責任もあると思います。音楽や映画のレヴューもそうですが、ともすればマーケティングの話だけで評が埋め尽くされてることもあるので。
松永「なるほど。もうひとつ気になっているのが――ハリウッド映画などもそうですが――ポリティカル・コレクトネスが進みすぎて、作品が作りづらくなってることなんです。キャスティングにしても〈白人が多すぎるのはおかしい〉みたいな批判がすぐに起きる。『ラ・ラ・ランド』にもそういう批判がありましたよね。〈ジャズの話なら、もっと黒人が出ていないとおかしい〉と。それって、すごく窮屈だと思うんですよ。芸術はそういうものから自由であるべきなので。芸術作品とは、その作者の偏見に基づいているし、そこから完全に逃れることは絶対にできない。以前、会田誠さんの作品が人権団体からの抗議によって出展できなくなったり、椎名林檎さんの〈フジロック〉のパフォーマンスが右翼的だと言われたりしたじゃないですか。作品の受け取り方にはいろいろあると思うけど、作品自体を発表できない状況にはしないでほしいんですよね」
――アーバンギャルドの表現も、社会の在り方によって影響を受けてますか?
松永「あるでしょうね。バンドも成熟するし、自分たちも年齢を重ねているので、そのなかで変化している部分もあるだろうし。ただ、リスナーの気持ちを考えすぎたり、配慮しすぎる点についてはやっぱり懐疑的なんですよね。それも大事なことだと思うけど、いまはそういうものがあふれているので、自分たちはそうじゃないことをやりたくて。個人的には自分自身に興味があるんですよ、いま」
浜崎「前からそうでしょ?」
松永「いやいや、そんなことないですよ(笑)。でも、いまは自分の孤独に立ち返った表現をやりたいんですよね。さっきも言いましたけど、いまはコミュニケーションを取ろうとする芸術が多いっていうのもあるし」
浜崎「私、普段はコミュニケーション、取りたくないですからね」
――ライヴでもですか?
浜崎「そうですね。極論を言うと盛り上がらなくてもいいので」
松永「それはすごいね(笑)」
浜崎「ちゃんと聴いてくれたらそれでいいんですよ。周りとリズムに合わせて体を揺らしたりとか曲に合わせたノリ方があってもいいけど、それができなくてライヴに踏み出せない人もいると思うので。そんなの気にしなくていいんですよ。いちばん後ろの方で腕組みして、彼氏ヅラ、彼女ヅラして観てくれればいいです」
松永「地下アイドルの現場で、下手の後ろのほうにいる人だね(笑)」
――あれって、彼氏ヅラをしてるんですか?
浜崎「そうらしいですよ(笑)。私はそれで全然いいし、もっと気軽に来てほしいんですよね。〈どういう服を着て行ったらいいかわからない〉とか、過剰に考えてしまう子もいますから。大丈夫、周りはあなたのことなんて見てないからって思うけど」
松永「ハハハハハ(笑)」
浜崎「だって、お客さんはステージを観るために来てるわけですからね。あと〈ヘンなところでキャーって言って、すみませんでした〉っていうお手紙をもらったり、それぞれ好きなように楽しんでくれたらいいんですけど、そういうことが気になるのもSNSの影響なのかもしれないですね」