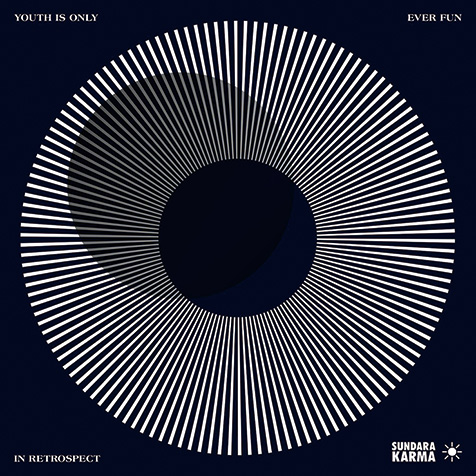DON'T LOOK BACK INTO THE SUN
[ 緊急ワイド ] UKロックの次なる覇者は誰だ?
大物バンドのリユニオンも重なって復調著しい英国ロック界。しかし若手の底上げがあってこそ、ムーヴメントは未来へ繋がっていくというもの。期待の新星が続々と登場している2017年。本当の盛り上がりはここから始まる!

RAT BOY
不安や怒りをわめき散らす1匹のネズミ男。コイツはただのクズなのか、それとも……?
英国社会の分断と言えば、従来は階級の差や地域差を引き合いに語られることが多かった。しかし、昨年のEU離脱を問う国民投票と、若い層の圧倒的支持を得て野党労働党が躍進した6月の総選挙で浮き彫りになったのは、ずばり世代による分断線だ。おそらくパンク・ジェネレーションよりも切実に〈ノー・フューチャー〉という現実に直面し、親世代との深い溝を実感しているであろう若者たちのスポークスマンとして浮上したラット・ボーイが、満を持してファースト・アルバム『Scum』を送り出した。

MVやアルバム・ジャケットではサポート・メンバーを含めた4人組として提示されているが、21歳になるジョーダン・カーディのDIYプロジェクト。現在も基本的には、曲作り、大半のパートの演奏、プロデュース、ミックス、はたまたアートワークまでみずから手掛けており、ラット・ボーイという名も、〈ネズミに似ているから〉という理由でついた愛称だ。ロンドンの隣に位置するエセックスのチェルムスフォードで、音楽とスケボーとアートを愛して育ったジョーダンは、地元のカレッジでアートを学んでいた2014年初めに初のミックステープ『The Mixtape』を発表する。そして、瞬く間に注目を集めて〈BBC Sound Of 2016〉の候補にも挙がり、NME誌主催のアワードで新人賞を獲得するほか、次々と話題を提供。昨年の〈サマソニ〉ですでに来日済みで、ケンドリック・ラマーが最新作『DAMN.』で彼の曲をサンプリングしたことも記憶に新しい。
つまり新人として申し分ない追い風が吹くなかで登場した『Scum』は、100に及ぶストックから厳選し、曲に多数のインタールードを交えて構成した計25曲の大作だ。長丁場でありながらちっとも飽きないのは、ミックステープ作りで磨いた編集能力に加え、曲の多様性にもあるのだろう。〈インディー・ロック × ヒップホップ〉としばしば要約されるジョーダンの表現は、パンク、ブリット・ポップ、90年代のヒップホップを筆頭に、ビッグ・ビートやドラムンベースまで雑多なスタイルを消化した、実に振り幅の広いミクスチャー。と同時に、クラッシュやビースティ・ボーイズのハイブリッド術、ストリーツことマイク・スキナーのストーリーテリング力、同郷のブラーやリバティーンズのような生粋のイングリッシュネスを受け継ぐ人でもある。そのブラーのデーモン・アルバーンとグレアム・コクソン、元カイザー・チーフスのニック・ホジソン、ビースティ・ボーイズのエンジニアだったアンドレ・ケルマン、UKインディーの重鎮プロデューサーであるスティーヴン・ストリートといったコラボ相手のチョイスも、DNAを如実に物語っているというものだ。
そんな今作で彼は、3年前にひとりで録音したローファイな“Sportswear”から、ごく最近にメンバーと作った“I’ll Be Waiting”へ至る音楽的進化を辿ると共に、一途に夢を追ってきた過去数年間の自分の成長過程をドキュメント。郊外で暮らすワーキングクラス・キッズの生活を、ウィットとペーソス満々に描いている。金も仕事もなく、恋に手こずり、天気は毎日冴えないし、ヴァイオレンスと隣り合わせ。でもって、EU離脱を控えた不透明な時代を生きることを強いながら、大人たちは次の世代のことを顧みず、政府は彼らを〈社会に寄生するお荷物〉とみなしている。若者に対して不公平極まりない状況への怒りを湛えた本作のきな臭さは、スペシャルズの『The Specials』やジャムの『Sound Affects』など、いまと似た70年代末~80年代初頭の英国の郊外の風景を記録したアルバムを想起させなくもない。
でも厳しい現実を眺めるジョーダンの視線に、よくありがちな逃避願望は感じられず、伝わってくるのはむしろ〈Scum(=クズ)〉としての誇りとホームタウンへの愛着だ。憧れのミュージシャンと音楽を作り、世界中をツアーしたいまも、彼にとっては地元で仲間とつるんでいる時が一番ハッピーなんだろう、きっと。