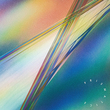ソフトなサイケ・サウンドを端緒としてドープにポップに広がるSF世界。新体制となって初の作品で表現する〈何とも言えない違和感〉の先にあるものは?
何とも言えない違和感
2010年代後半におけるジャパニーズ・サイケの新たな地平を切り拓き続けるTempalay。今年6月にベーシストの竹内祐也が脱退するも、以前からサポートを務め、ソロ・アーティストとしても活動するAAAMYYY(コーラス/シンセサイザー)が7月に加入し、新体制の初作となるミニ・アルバム『なんて素晴らしき世界』を完成させた。
「わりと個性がバラバラの3人で、そのバランスを取ってたのが前のベーシストだったと思うんですけど、その歯止めがなくなっちゃって、今はロケット花火みたいな状態っていうか。個性がパンパンパンパン!って弾けてる(笑)。ファンカデリック然り、インターネット然り、僕は個性の集合体みたいな見え方が好きなので、今後はその強みをもっと出していきたいなって」(小原綾斗、ヴォーカル/ギター)。
「ベーシストが抜けて、〈何かができなくなった〉みたいな感覚はないんですよね。むしろ、今までのTempalayよりも確実にヴァージョン・アップしてると思うし、AAAMYYYの加入っていうのは、そこですごくプラスに働いたと思います」(藤本夏樹、ドラムス)。
竹内の脱退後、Aun beatzのKenshiroをサポートに迎え、前作『from JAPAN 2』に続いて奥田泰次がエンジニアを担当した本作のコンセプトは〈地球の誕生から滅亡まで〉。そのSF的な世界観は、坂本慎太郎やOGRE YOU ASSHOLEといった先達ともリンクしつつ、ドープでありながらもポップな抜群のバランス感覚で作品化されている。
「世界観としては、もやがかかってるというか、〈何とも言えない違和感、おどろおどろしさ〉みたいなのをめざしました。よく映画のサントラを聴いていて、『バンコクナイツ』とか『ファントム・オブ・パラダイス』、あとはスタンリー・キューブリックの映画の〈暴力的なシーンでクラシックがかかってる恐怖感〉とか、ああいうのはずっと好きです」(小原)。
「サントラって、だいたいは映像が先にあって、それに合わせて音を付けるわけじゃないですか? なので、音だけで聴いたら過剰で、やり過ぎてるような感じもするけど、それが逆に新鮮で、おもしろかったりもして。今回ドラムのアレンジも過剰な部分が多々ありますね」(藤本)。
ブルージーなイントロダクション“誕生”で幕を開けると、シタールとトレモロのかかったギターが独特のムードを作り出すソフト・サイケ“素晴らしき世界”で本編がスタート。〈相思相愛じゃもの足んないよ どうしよう〉というラインが印象的な“どうしよう”は、キャッチーなソングライティングが光る。
「“どうしよう”は今の自分におけるポップの限界ですね。ずっとサビみたいな感じなので、これでもかってくらい腹いっぱいにしたろかなって。ただ、歌詞は曲調とは対照的なんです。これ以上(ポップなほうへ)寄ると自分を見失っちゃうから、ギリギリのラインをめざしました」(小原)。
TR-808によるビートにAAAMYYYのラップも加わった“テレパシー”は、〈ギター/ベース/ドラムスの3ピース・バンド〉という枠から解放された、新体制での曲作りを象徴する一曲。一方、AAAMYYYの加入発表と同時にMVが公開された“SONIC WAVE”は、ジミ・ヘンドリックス~ホワイト・ストライプス好きを公言する小原の豪快なギター・リフと、〈あまりにも毎回同じ内容〉〈期待してるよみんな いかれたサウンド〉という尖った歌詞が何ともTempalayらしい仕上がりだ。
「“テレパシー”はブロックハンプトンにスーパーオーガニズムのファニーな部分を足した感じ。最初はスーパーオーガニズム的なファニーな電子音のなかに、生ギターが特徴的に入ってるみたいな作りがいいと思ってたんですけど、僕、そのバンドが流行っちゃうと好きじゃなくなっちゃうっていう中二みたいな感覚がまだ残ってて(笑)、ラップやノイズも入れちゃおうってなりました。“SONIC WAVE”は〈おそらく次はこうなるだろう〉っていう予想の逆を行きたくて、暴力的なものに……まあ、カマしたかったんですよね(笑)」(小原)。
「私は普段引き算をしたがる人間なんですけど、Tempalayに関しては周波数とかを埋めたくなるんです。あとライヴではソフト・シンセを使ってるんですけど、レコーディングは絶対実機の質感が合うと思ったので、実機を使いました。“SONIC WAVE”のなかのオルガンはすごく気に入ってて、音に厚みが出せたし、しかもそれがバッキングだっていうのが自分のなかでは熱くて。ライヴだと手が足りなくて弾けないんですけど(笑)」(AAAMYYY)。
皮肉と希望
インタールードの“THE END”を経て、いよいよ物語はクライマックスへ。近年のジャズ×ヒップホップ以降のよれたビートに乗せて、〈地球最後の2人〉を歌う“ラストダンス”から、滅亡した地球を探索に来た宇宙人の歌をヴォーカル・エフェクトで表現し、最後はノイズの海に包まれるというモンドなテイストの“カンガルーも考えている”でアルバムは締め括られる。
「これまでのコーラスは、いかに綾斗の声を聴こえやすくするかを考えて、芯のある声は使わないようにしてたんですけど、“ラストダンス”は芯のある声を急に入れたり引いたりする歌い方をして、いい感じになったかなって」(AAAMYYY)。
「〈景色〉を言葉にするのが好きで、“ラストダンス”の〈新東京から混沌とした地平線〉〈バイパスの蜃気楼〉〈色彩のトンネル〉とかは、『AKIRA』的な世界観というか、もう機能してない都市の描写です。“カンガルーも考えている”に関しては、僕は結末がわかりやすいものはあまり好きではないので、基本、聴き手に委ねています。これがどういう状況なのか、想像力を働かせることができるような、余白のあるものが好きですね」(小原)。
本作はまさに『なんて素晴らしき世界』というSF映画のサントラのようであり、曲を聴いてもらえれば、このタイトルが持つ皮肉の効いたニュアンスもきっと伝わるだろう。
「僕は渋谷なんてシラフじゃ歩けないし、ホント今の世の中は狂ってるなって思ってて。まともなものなんて何一つないけど、でもそんななかでも新しい生命が生まれたり、美しい側面もあるわけですよね。それって俺らがやってることも一緒っていうか。認められようと作品を作ってるわけですけど、周りから見たらそんなの傲慢な話だし、〈何やってんだ?〉ってことになる。常にいろんな視点があって、こっちが見てるってことは、見られてるってことでもある。そういう場所で生きていて、発信してるっていうのは、皮肉でもあり、希望でもあるなって。今の音楽シーンにも、今の東京っていう街にも、すごくフィットするタイトルなんじゃないかと思います」(小原)。
12月には若手バンドの登竜門とも言うべき東京・恵比寿LIQUIDROOMでワンマンを開催。もちろん、新体制となったばかりのTempalayにとっては、この日も通過点に過ぎないはずだ。
「まだ2人の知らない部分も私には多いと思うから、いっぱい活動をして、もっと2人のことを知ったうえで、より良い作品を作りたいなって。3人とも日々進化してるから、バチッてハマる瞬間が来たら、めっちゃすごいと思う。今はそこに向けての途中段階で、これからもっともっと良くなると思います。まだ出し切ってないですから」(AAAMYYY)。
「それはめっちゃそう。今はまだ転換期で、今回の作品は次の作品への伏線にもなってるから、次もぜひ楽しみにしていてほしいですね」(小原)。
Tempalayの作品。
Tempalayのメンバーが参加/楽曲がサンプリングされた作品。