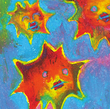マイペースな個人経営ながら、Hawaiian6やTHE CHERRY COKE$、RADIOTSやTHE FOREVER YOUNGなど多くのパンク・バンドを輩出してきたSTEP UP RECORDSが、今年20周年を迎える。レーベルオーナーのRYOSUKEはFUCK YOU HEROES/TOYBEATSでも活動中で、バンドマンの現場感覚を何より重視する彼の姿勢にリスペクトを寄せる仲間は多い。
その象徴が名物コンピレーション『…OUT OF THIS WORLD』であり、何かあるたびに仲間たちが集う作品としてシリーズ化されている。レーベル10周年の2009年には全63バンド60秒しばりの企画盤『…OUT OF THIS WORLD 4』が作られたが、今回ふたたび、全60バンド60秒しばりの特別盤『…OUT OF THIS WORLD 6』が完成した。
生粋のパンクスに限らず、ATATA、My Hair is Badの椎木知仁、Dizzy Sunfistにbachoなど、世代も居場所も違うメンツが限られた時間で己を表現していく、いわばバトルとでも言うべきこのフォーマットは、RYOSUKEという男の優れたフェアネスから生まれたものだ。レーベルの歴史と思想、そして現状の問題について、赤裸々に語ってもらった。場所は彼のホームであるライヴハウス、新宿ACB HALLである。
笑っていられる環境を作るためスタートした
――STEP UP RECORDSの歴史は99年にリリースしたコンピ『…OUT OF THIS WORLD』から始まります。資料コメントにもありますけど、当時は「まだ無名な友達のバンドを知ってもらいたい」という動機だったんですか?
「ほんとそれだけですね。20年前、僕はまだ大学生でしたけど、インディーズって言葉が出てきだした。それこそ〈インディーズ・マガジン※〉とかあったし、コンピもいっぱい出てきた頃ですよね。で、僕らの仲間内でも誘われたコンピに入る人がいれば、〈いや、俺たちでやっちゃえばよくない?〉っていう人もいて。後者のひとりが俺だったっていう。
〈出してあげるよ〉とか話しかけてくる人は胡散臭かったし、あと僕、当時事故に遭って慰謝料がブワッと入ったんですよ。〈お金できちゃったし、やっちゃおっか!〉って(笑)。だからめざすイメージとかもなくて、売れても売れなくてもいいから笑っていられる環境を作りたかった。〈俺たちの遊び場はこんな感じですよ〉って言いたかった。それだけですね」
――最初のコンピはHawaiian6やNICOTINEら全10バンド。昔からRYOSUKEさんは友達が多いですよね。バンド同士で壁をあまり作らない。
「性格でしょうね。基本、〈嫌い〉はないから。〈苦手〉はあっても〈嫌い〉っていうのはなくて。胡散臭いセンサーはすぐ働くんですけど、同じくらい、好きなもの、カッコいいなと思う人に対してはずんずん行っちゃう」
――好きになるセンサーはどこにあるんですか?
「なんだろうな? でも会話から入るっていうよりは、バンドはライヴを観て〈あ、カッコいいな〉って思えば、それでもう好きなんですよね。(ACBで)ブッキングをやってた時代は、まず興味が出てきたら話しかける。もちろん話してみて〈あれ、なんか違うな〉っていう人もいましたけど、年齢とか動員とかは関係なく、フラットに接してくれる人とはすぐ友達になれるし」

――ACB HALLのブッキング担当は、いつ頃からいつまでやってたんですか?
「そんなに長くないですね。2000年から2003年くらいその時期にこのハコを持ってたオーナーがちょっと続けらんなくなって、(高円寺のライヴハウス)GEARの店長だった人に相談に来たんです。ちょうどその店長とPAがGEARを辞めたところだったので、2人がACBをやることになって。で、僕は『…OUT OF THIS WORLD』のレコ発をGEARでやったくらい、GEARが遊び場だったので。〈じゃあ若いバンドのブッカーとして来てくれない?〉と誘われた。それが24歳くらいですね。一緒に3人で作っていこうって。
それまでのACBってオジサンしか出ないようなハコだったんですよ。だんだんそれも変わっていきました。僕もいたし、店長の趣味もあって、若いメロコアがワーッと集まってきたんです。あとHawaiian6のヴォーカルの(安野)勇太もブラブラしてたんで〈お前もバイトで入れ〉ってことになって受付にいたし、PAにはANDREW(FUCK YOU HEROES)もいて」
――いわゆる〈AIR JAMブーム〉のあとの、その次の世代のパンク・シーン。それを自分たちで作りたかったんですか?
「2000年の夏に、僕が当時やってたLEGGOってバンドとHawaiian6の企画をACB HALLでやったんですよ。それが〈AIR JAM2000〉と同じ日で。でも、当時それなりにいたお客さんを全部〈AIR JAM〉に取られたんです。そこから〈あぁ、もう俺らで作んなきゃいけない〉って。
僕らの先輩と言える人たちは〈AIR JAM〉のなかでも若手って感じで、もちろんそうした先輩たちも決して頼ったというわけじゃないと思うけど、ハイスタとかに引っ張られてきた世代だと思うんですね。僕らもほんとはそこに入りたかったけど、そういう関係性ではなかったから。〈マジで客いねぇ、どうする?〉〈じゃあ僕らだけで何ができるんだ?〉って、けっこう本気で話したのはいまも覚えてます。だからまず横のつながりで広げようと思って」