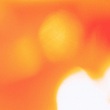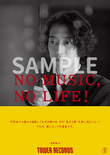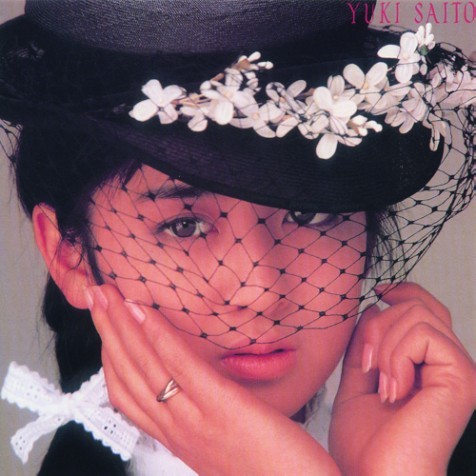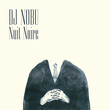ポップスの現場で目にした奇跡の瞬間
「当時はポップスに興味がなくて。帰国してからはアングラでのライブが多かったですね(笑)。やっぱり即興と朗読が中心で。もちろんそういうのは今も好きなんですけど、とにかく暇で時間もあったからいろいろ作れたんだと思います」
――前衛的な。
「人によってはそう見えるのかもしれないです。〈これが俺のやりたいことだ!〉っていう気持ちが強かったですね。イキってた。ポップスには興味がなかったし、ジャズの方が高尚な音楽って思ってました」
――どうしてですか?
「当時の僕にとってポップスは〈削いである音楽〉だったし、ジャズは〈詰め込んである音楽〉だった。頭でっかちの俺は〈ジャズの方が詰め込まれてて、よりレヴェルの高い音楽だ〉って考えてたんですよ。強烈なイキり。〈ポップス? んなもん5秒あれば書けるわ!〉みたいな」
――でも、ポップス要素の強いバンド(CRCK/LCKS)をはじめた。
「そうそう。CRCK/LCKSは当時の象眠舎とは違ってポップス寄りのバンドだけど、始まったら想像以上に楽しいし勉強になることが多くて、どんどんのめり込んでいった。その頃から作曲・編曲の仕事をもらえるようになって、Charaさんとか、TENDREの(河原)太朗ちゃん、中村佳穂ちゃんとかとの、いろんな出会いがあったんです」
――意図せず入ったポップスの世界で〈勉強になったこと〉とは?
「ポップスをバカにしてたわけですが、何を言っていたんだと(笑)。ポップスの凄みを目の当たりにしたんです」
――ポップスの凄み。どんなときに感じたんでしょうか?
「TENDREの初めてのワンマン・ツアーかな……ステージで太朗が大号泣したことがあって、嗚咽を漏らしながらピアノを弾いて、お客さんもみんな感極まって泣いていたんです。真摯な気持ちで音楽が伝わっている瞬間を見た、と感じました。
Charaさんは、もうイントロを演奏しているだけでお客さんがすごく高揚しているのがわかるし、彼女が登場するだけで最前の人たちは泣くこともある。それって、Charaさんが真摯に音楽を信じ続けて気持ちを伝えてきたから、お客さんたちが彼女の音楽を〈自分のもの〉にしてきたからなんだなって。そういうフックがあるからこそ、思い出の一端になる。
伝えようとする姿勢を貫いてきた人たちの奇跡みたいな瞬間を見てると、ポップスの力を感じざるを得なかったんです」

ポップスなめんなよ
――ポップスって大衆音楽なわけだから、迎合しているように見えてしまうけど違った、みたいな?
「なめんなよって感じですよ(笑)。作ってみてポップ・ミュージックの難しさに気がつきました。
例えば歌詞だと、“少年時代”(井上陽水)にでてくる〈風あざみ〉とか、“クロノタシス”(きのこ帝国)で〈350ml〉が〈スリー・ファイヴ・オー・エム・エル〉と歌われるとか。普段聞かない言葉なのにスッと入ってくるし、歌詞とメロディーが合わさった瞬間に景色が広がる。発明だと思う。
“bad guy”(ビリー・アイリッシュ)の〈Duh〉もすごい。音としては、〈ダー〉でしかないのに、歌詞として腑に落ちる。〈I‘m the bad guy... Duh〉って言った瞬間、納得してしまう。
伝わりやすさを意識すること、削ぎ落とすことは難しいし、ポップスにはすでに長い歴史がある。そのことにCRCK/LCKSを始めてからの数年で気がつきました。
自分が信奉していたジャズも元々ポップ・ミュージックだし。フランク・シナトラとか、ハリー・コニックJr.とか、トニー・ベネットとか、往年のアイドルとしてちゃんと名を刻んでるわけですしね。村上春樹も野田秀樹もポップなエンタメなんだよな。子供のときはそれに気がついてなかったけれど。
それで、アメリカで気がついた演劇的、映画音楽的、実験的な自分の音楽性に、日本に戻ってきてからポップスの現場に立って勉強したキャッチーさを混ぜ込んでいこうと思ったんです。
実は、今回リリースした“Lycoris”は2年ぐらい前にレコーディングしていたもので……。バンドの活動が忙しくなっちゃったから間があきつつ、この2年で得た知識とか技術とか実験を混ぜ込んだ形になってます」
――2年前!
「象眠舎はエンジニアのモリタさん(Seiji Morita)と組んで音楽を作ってるんですけど、忙しかったとはいえ、あまりに時間が経っていたのでモリタさんに〈いい加減やろうよ〉と怒られました(笑)。
ちょうどCRCK/LCKSの音楽が自分の中でひとつ区切りがついたので、久しぶりにゴテゴテのエゴむき出しの象眠舎に向きあおうと」