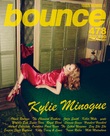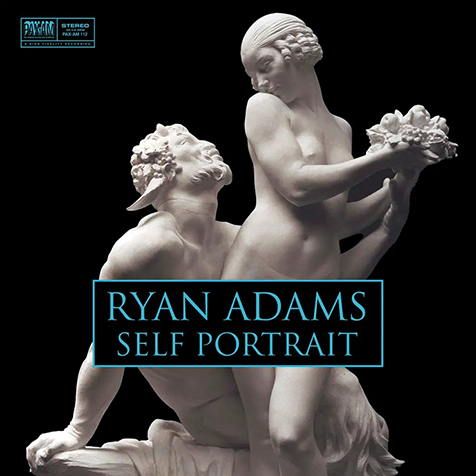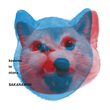樋口恭介が本作を題材に綴る、新たな物語=記憶「Long Road Home」
これは私的な記憶の反復、あるいはこれから出会う新たな思い出のための、ささやかな練習として書かれている。
*
私はこの原稿を2020年の10月19日に書いている。仕事を終えて、駅の喫茶店でコーヒーを飲み、ヘッドフォンで音楽を聴きながら、ときどき思い出したように少しずつ、パタパタと指先のキーボードを鳴らしている。今は夜の10時。原稿は進んでいないが、そろそろ家に帰らなければ、と私は思っている。私はコートを羽織り、席を立ち、会計を済ませて外へ出る。
コートのポケットの中には、去年聴いてそのままにしていたカセットプレイヤーが入っていて、中には見たことのないカセットが入っている。たぶん、一度か二度だけ聴いて、それがどんな音楽だったのかも、そもそもそんなカセットを買ったことすらも、忘れてしまっていたのだろう。
私はヘッドフォンを耳にかけて、それから再生ボタンを押す。カセットテープからはどこかのラジオ放送の録音が流れ始める。それは懐かしい音楽のような気がしたが、なんの曲かはわからなかった。私はそれを、どこかで聴いたことがあるような気もしたし、そうではないような気もした。私はその音楽を聴きながら歩き始めた。
*
全ての音楽は偶然の音楽である。偶然は混信の比喩で語ることもできる。ダニエル・ロパティンはそのことを知っている。
*
ダニエル・ロパティン。一般にはワンオートリックス・ポイント・ネヴァーの名で知られる。彼は記憶の作家であり、混信の作家であり、そして混信する無数の記憶を提示し続ける作家である。それは、2007年にリリースした『Betrayed In The Octagon』(『Rifts』所収)から、最新作『Magic Oneohtrix Point Never』に至るまで変わらない、彼の本質的な特徴である。
ダニエル・ロパティンは自身の記憶を切り刻み、何度も断片を並べ替え、それを、再帰的に見いだされた、一つの整合性のある物語として語り直す。たとえば幼少期の記憶。風景。音楽。イメージ。存在しない思い出。不可能なノスタルジー。雨粒。ガラス戸を叩く音。それとも泥のついた黄色い長靴。水たまりに映る街灯の光。静かに炸裂する、線香花火の炎。
存在しないラジオが、存在しない記憶を語り始める。
*
ところで、私は普段、出かけるときに音楽を聴くことが多い。私は歩いて移動するのが好きだが、仕方なく電車に乗ることもある。だから私は歩きながら音楽を聴き、電車の中で音楽を聴く。聴く音楽はノイズやアンビエントやドローンが多い。それらに共通して言えるのは、いずれも静けさを湛えた音楽であるということだ(ノイズの熱心なリスナーには理解いただけると思うが、ノイズとは、本質的に静かな音楽である)。それらの音楽は静かなものであるがゆえ――さらには私が使うヘッドフォンが安物であることもあって、純粋な作品それ自体として聴くことは決してかなわず、絶えずヘッドフォンの外で鳴り続ける無数の音と混じり合う。
静かな音楽は、まるで交通事故のような偶然の出会いを許容する。あるいはそれは、交通事故のような偶然の出会いをあらかじめ想定しているとさえ言える。そこには落ち葉を踏む私自身の足音もあれば、国道を抜けてゆくトラックのエンジン音、地下鉄のホームでしゃべる高校生たちの声、あるいは嬌声や怒声、何かを引きずる音や何かを引き裂く音、何かが破裂する音なども含まれる。高い音もあれば低い音もあり、中くらいの音もある。大きな音もあれば小さな音もある。音程感やリズムのある音もあれば、そうでないものもある。それらの音が入り混じり、つねに作品と干渉し合い、私の中に、そのたびごとにかけがえのない、固有の体験を生んでいる。
こんな話もある。大学生の頃、私は毎日ニコニコ動画をながめて過ごしていた。私は〈歌ってみた〉とか〈演奏してみた〉といったタグをたどって延々動画を再生し続け、気に入った動画のプレイリストを作っていった。そこには、覚えたばかりの楽器を使って、曲とも言えない曲を奏でる、名もなき少年や少女たちがいた。演奏はお世辞にもうまいとは言えず、曲の質も音の質も、市場に出回る商業音楽とは比べるべくもなかったが、彼らの演奏動画には、商業音楽にはない、生生しい魅力があった。それは、市場という制度が設ける優劣の基準によって刈り取られる前の、技術以前の技術であり、文化以前の文化であり、むきだしの生そのものだった。私はそれらの動画を愛していた。私は名前も知らない楽曲の、名前も知らない作家たちを愛していた。
その頃のプレイリストは今はない。その頃観ていた動画はもう、作家自身の手によって削除されてしまったからだ。彼らのアカウント名ももちろん覚えてはいないし、たぶん消えてしまっているだろう。私は彼らの曲のことを、彼らの演奏のことを、彼らが残したコメントのことをよく覚えているが、もう二度と聴くことはないだろう。けれど、それでいいとも私は思う。