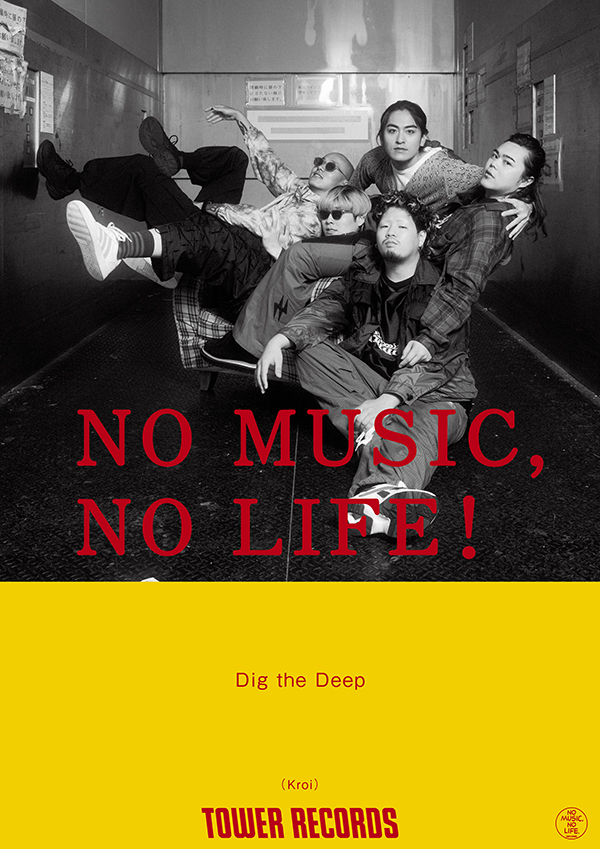子どもの頃、死の恐怖を鋭敏に感じる時期というのはきっと誰しもにあるものだが、その時期が人一倍長かったというKroiの内田怜央(ヴォーカル/ギター)は、「この世に自分の分身を残そう」と思ったのだという。そして、それがいまのKroiの作品に繋がっているのだと、この日演奏された“Fire Brain”のブレイク部分で彼は語った。また、彼はこの日、こんなふうにも言っていた。「みんなが作りたいものを作って、それがたくさんの人に届く。そんな世の中をめざします」。Kroiの音楽には、精神の世界への肯定と、創作への祝福がある。
心に肉体を与えたような、美しくも異形なファンク・ミュージック。まるで気の置けない友人と一緒にいるときのような、親密さ。そういったものたちに濃密に満たされていく、素晴らしい時間だった。

2月1日、神奈川・ぴあアリーナMMで開催されたライヴは、Kroiにとって初のアリーナ会場でのワンマンライヴだった。昨年6月にリリースされたサード・アルバム『Unspoiled』に合わせたリリース・ツアーのファイナル公演ではあるが、ひとつのアルバムを象徴するというより、Kroiというバンド自体を象徴するようなライヴだった。過去最大規模のワンマンだからと言って、派手な演出や衣装を纏うこともない。もちろん、彼ららしいサイケデリックな照明演出などはあったが、基調となるステージ・セットは、背景に掲げられたラフな筆致の〈Kroi〉のバンド・ロゴのみ。以前はもっと過激に装飾的だった彼らのライヴは、キャリアを積み、規模を大きくするにつれてシンプルなものになっている。そこにあるのは〈ストイックさ〉というより、〈ナチュラルさ〉と呼ぶべきものだろう。

セッションから“HORN”になだれ込む、バンド・ミュージックとしての魅力満点なライヴの幕開けも、“Monster Play”で内田と益田英知(ドラムス)がパート・チェンジをし、もともとはギター少年だったという益田がギター・ソロを情感たっぷりに弾き狂った自由さも、アンコールの“トレンド”演奏時にモニターに映し出された、上半身裸のメンバーが風船のように膨らんでは破裂する謎シュール映像のいたずら小僧のような茶目っ気も(何年か前に内田が3Dモデリングソフトにハマっていると言っていたが、それで作ったのだろうか……?)。それに、冒頭に書いたような、ステージに立つ人間として言えることは言葉にして伝える、真摯さと社会性も。そのすべてが、肩肘張らず、でも背負うべきものは背負う、そんないまのKroiのナチュラルなバランス感や温度感から生まれているもののように感じられた。そんな彼らの世界観だからこそ、観客である自分もまた、自然体にその音楽にコミットすることができる。どんなポップスターやロック・バンドとも違う、Kroiにしか醸し出せない空気感が、心地よくぴあアリーナを包んでいた。


演奏はもちろん素晴らしかった。屋台骨としても、主人公としても、アンサンブルの中で存在感を放つ関将典のベース。ときに壁を作るように、ときに空気を切り裂くようにギターを奏でる長谷部悠生。キーボーディストの千葉大樹は変幻自在にマジカルに音を奏で、“Balmy Life”では情熱的にトークボックスを響かせる。益田のドラミングは興奮と変化を伝え、内田のヴォーカルは、呟きから絶唱までの距離をひとっ飛びで往還する。5人それぞれが、ミュージシャンとしても、人としても、特別なタレント性を持つKroiだからこその、多彩さ華やかさ。そして、そんな5人が合わさったときに生まれる魅惑的な一体感。特に、中盤で披露されたライヴの定番レパートリー“Shincha”でのアンサンブルの、神秘的なほどの美しさには息を呑んだ。



それに“明滅”や“Jewel”のような、最近のKroiの音楽性に表れはじめた〈ファンク・フォーク〉とでも形容したくなるような、穏やかさと驚きに満ちた楽曲たちにも、鮮烈なビジョンを想起させる響きがあった。“明滅”に“Jewel”、それに太陽が沈む直前の閃光を意味する“Green Flash”もそうだが、近年のKroiの楽曲のモチーフになるのは、光の情景をイメージさせるものが多い。彼らの内側にある理想が、楽曲に表れていることの証左だろう。内田は、「Kroiは、行けるところまで行きます」と言っていた。Kroiはまだまだ、彼らにとっての美しいものを見に行くつもりである。