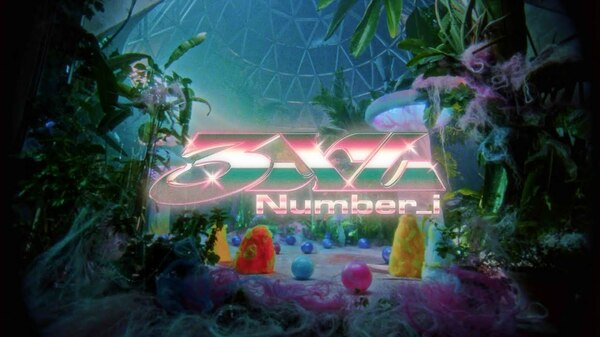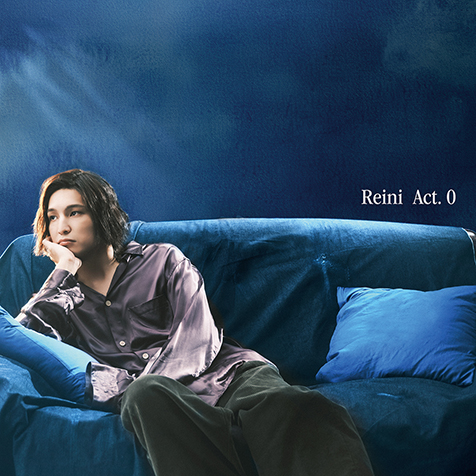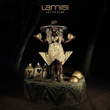成功とは言えない人生を讃え、心に差す影を見つめ、居場所のない人々を受け入れる――次のステージへと進んだ週末のソウルバンドは、エンドロールの後に何を歌う?
2017年リリースの“ダンスに間に合う”が中井貴一と小泉今日子によるデュエットでカヴァーされ、TVドラマ「続・続・最後から二番目の恋」のエンディング・テーマに起用されたことで俄かに注目度が高まっている、思い出野郎Aチーム。レアグルーヴに大きな影響を受けたバンドの代表曲である8年前の楽曲が、レアグルーヴのように再発見されたことについて、自身はどう感じているのか?
「あの頃はメンバー間で〈何歳になっても聴ける音楽が出来たらいいね〉って話をしつつ、自分たちはまだ30代前半だったし、あまり考えないでクラブに遊びに行く視点からパッと書いた曲だったんです。でも、その後にコロナがあったり、社会が変化したりするなかで、今回取り上げてもらえたのは、聴いた際に染みる度合いが高まるタイミングだったからのかなって。曲の感想を見ても、〈再チャレンジの背中を押されました〉とか、〈人生を応援されている気持ちになります〉とか、自分の意図していなかった意味や時代を超える普遍性を帯びたことが不思議でもありますね」(高橋一、トランペット/ヴォーカル)。
〈歌は世につれ世は歌につれ〉という言い回しがあるように、音楽は社会の変化と共に移ろい、また音楽の変化が社会の移ろいにも影響を与えるものだ。
「前作『Parade』(2023年)はコロナ禍の最中にスタジオを設立したり、メンバー2人が活動休止したりするなか、新しいことにトライしようとした、悩みが大きい作品だったんですけど、そういう時期を乗り越えて、この歳になって、〈自分は自分でしかないし、できることは限られているよな〉って、いい意味でようやく諦められたというか、今回は何も考えず、現状をただ曲にすればいいやって。ただ、“ダンスに間に合う”の頃からは大きな変化もあり、自分に子どもが生まれて、今年で2歳になったんですけど、そういう経験から書くことが増えて、結果的に人生観が出たんだと思います」(高橋)。
経済の尺度にとらわれない些細な日常における幸せに光を与える“人生は失敗だった”や、お笑い芸人ハナコの単独公演のエンディング・テーマとして書き下ろされ、ステージが終わった後も続く人生に思いを馳せる“エンドロールの後に”、あの夜の続きをそれぞれが逞しく生きていることを想像する“僕らは踊らなくなった”といった楽曲が物語るように、ニューEP『エンドロールの後に』はソングライターである高橋の眼差しの移ろいが音楽と人生の在り方を捉えるより広い視野をもたらし、普遍的な説得力を生み出している。戦争や紛争を前に無力さを感じながら、それでも音楽の力を信じる“BGM”、ありのままに生きることとと、その多様性を肯定する“帰らなくていい”のような思い出野郎Aチームらしいメッセージは、より直接的で力強くなった。そして、ワシントン・ゴー・ゴーのリズムを敷いた“はじめての感情”では人生における生の輝きや喜びを謳歌している。
「僕らがバンドを始めた頃は、ソウルのマナーがひとつの確立したスタイルになってしまっていた。でも、ヴィンテージ・ソウルの代表的なレーベル、ビッグ・クラウンを率いるリオン・マイケルズがプロデュースを手掛けたノラ・ジョーンズとクレイロのアルバムや、ブルーノ・マーズとアンダーソン・パークが結成したシルク・ソニックがそうであるように、最近はかつてマニアックだったヴィンテージ・ソウルが市民権を得て、ポップなものとして機能するようになりましたよね。だからこそ、好きなことをやりつつ、外に広がっていくバンドでありたいと思い続けてきた僕らとしては、勇気をもらっている気分なんです」(斎藤録音、ギター)。
人生を投影した歌詞と躍動するソウル・ミュージックのオーセンシティー。成熟を深める思い出野郎Aチームの活動は本作を足掛かりに、新たなフェーズへと突入した。
思い出野郎Aチームの作品。
左から、2023年作『Parade』、2019年作『Share the Light』(共にKAKUBARHYTHM)
思い出野郎Aチームの関連作やメンバーの参加作。
左から、小泉今日子と中井貴一の2025年のシングル“ダンスに間に合う”(ビクター)、RYO-Zの2024年作『Obsession』(SImones)