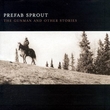タワーレコード新宿店~渋谷店の洋楽ロック/ポップス担当として、長年にわたり数々の企画やバイイングを行ってきた北爪啓之さんによる連載〈聴いたことのない旧譜は新譜〉。そのタイトル通り、本連載では旧譜と称されてしまった作品を現在の耳で新譜として紹介していきます。
第11回では、プリファブ・スプラウトを大特集。2026年2月にメンバーのマーティン・マクアルーンの来日公演も控えるなか、バンドがこれまでに発表した9枚のオリジナルアルバムを北爪さんが全力でレビューしました。 *Mikiki編集部
知らない人は知らない、知っている人は好きなポップバンド
プリファブ・スプラウトは、1980年代以降の英国シーンにおいて最も優れたソングライターの1人であるパディ・マクアルーンと、弟のマーティン・マクアルーン、紅一点のウェンディ・スミスを中心に結成されたポップバンドである。パディの作る楽曲はひねりの効いた歌詞もさることながら、細部にまで巧緻を極めたメロディの豊潤さにおいて比肩するものがない、眩いほどの強い個性を放っている。
そのためなのかトレンドとはあまり縁のない彼らは、有り体にいえば〈知っている人は好きだけど、知らない人は全然知らない〉という存在でもある。
そんなプリファブの楽曲をライブで体験できる貴重な機会がまもなく訪れる。来る2026年2月、病によって音楽活動の中断を余儀なくされているパディに代わり、弟のマーティンがソロ名義での来日公演を行うのだ。それは名盤『Steve McQueen』の40周年を記念した全曲再現ツアーの一環であり、同作以外からのナンバーも多数披露されるとのことである。
今回はその公演に先がけてプリファブ・スプラウトのオリジナルアルバム全9作品を、私見も交えつつレビューしてみたい。
『Swoon』(1984年)
デビュー作にして、後年のどのアルバムとも異なる質感を持った1枚。それはパンク以降の混沌とした時代の空気感がまだここには濃厚に漂っているからに他ならない。
たとえば、シャウトも交えた性急なボーカルの“Don’t Sing”。硬質なギターカッティングがコールドファンクのようでもある“Here On The Eerie”。ギターにファズがかかった“Technique”。ようするに、いまの耳で聴くと〈プリファブらしからぬ〉要素が随所に垣間見れるのだ。
ところがそれとは裏腹に、パディの書くメロディはすでに驚くほど強靭なのである。やりすぎなほどトリッキーな展開をみせる曲が多いため、即座に口ずさめるような形で提示されていないのがもどかしいが、卓抜なメロディが未整理のまま楽曲を形成していることこそが本作の面白味なのだ。とはいえ、エルヴィス・コステロがカバーした“Cruel”や“Elegance”のように比較的ストレートに楽しめる曲もあるので、臆せず聴いてほしい。
『Steve McQueen』(1985年)
前作にあったポストパンク的な尖った感触は薄まり、各楽器が明確な輪郭を保ちながらも柔らかく溶け合ったサウンドへと変化した2作目にして、初期の代表作。
その最大の要因はプロデュースにトーマス・ドルビーを迎えたことで、シンセを多用しつつも有機的な人肌感覚を残した彼の音作りが本作にタイムレスな魅力を与えたことは間違いない。加えて、パディの作曲がより整理されてわかり易くなったことも大きいだろう。とくに2曲目の“Bonny”から連続する4曲の繊細で瑞々しいポップネスは格別で、ファン人気も高い。
しかし私的なハイライトはその次に控えた“Hallelujah”である。ジョージ・ガーシュウィンの名を織り込むことで自身のルーツを明示した歌詞と、どこかに着地しそうでしない(でも美しい)メロディにプリファブの一筋縄ではいかない個性が凝縮されているように思えるからだ。
余談ながら“Goodbye Lucille #1”は、タイトルといい曲中のシャウトといいリトル・リチャードへのオマージュではないのか?と勘ぐっているのは僕だけだろうか。
『From Langley Park To Memphis』(1988年)
爽やかなジャケットどおりの開放感溢れるサードアルバムで、プロデュースは再登板のトーマスとパディを加えた4人が担当している。
エルヴィス・プレスリーの故郷であるメンフィスをタイトルに掲げながらも、その出発点は彼らの地元にほど近いラングレー・パーク(ほぼ無名の地)であるところに、アメリカに対する奇妙な距離感を感じずにはいられない。
アルバムはそのエルヴィスの異名を冠しつつも落ちぶれたロックスターの悲哀を歌う“The King Of Rock ‘N’ Roll”と、ブルース・スプリングスティーンの詞世界に対するアンチテーゼとおぼしき“Cars And Girls”で幕を開けるが、どちらの曲もとことん明快なポップチューンに仕上げているのがかえって皮肉めいている。そのくせ“Hey Manhattan!”なんて素直なNY賛歌のうえに作風は明らかに70sソウルを意識しているし、何より“Nightingales”にはスティーヴィー・ワンダーがハーモニカで参加している。
かように米国音楽への複雑な憧憬を背景にしながらも、個々の楽曲の完成度はすこぶる高い。キャリア最高となる全英チャート5位を記録したのも頷ける、これまた文句なしの名作。